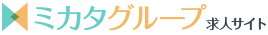ご利用者様の人生の満足度を表すQOL(クオリティ・オブ・ライフ)。
QOLは、体や心の状態だけでなく、経済的状況、人間関係などによっても大きく変化します。中でも介護職員は、ご利用者様の生活を支える役割を担っており、関わり方一つでQOLに大きな影響を及ぼしかねません。
そのため、介護におけるQOLの詳細やADLとの関連性、QOL向上のために介護職員ができることなどを知っておくとよいでしょう。
本記事では具体的なQOL改善のための手立てもご紹介しますので、ご利用者様のQOL向上に興味がある方はぜひご覧になってください。
この記事の内容
QOLとは?
QOL(クオリティ・オブ・ライフ)とは、「生活の質」「人生の質」「生命の質」などと訳され、生きる上での満足度をあらわす言葉です。
ご利用者様だけでなく、スタッフ一人ひとりも快適な生活が送れて、充実した人生の中で感じる満足や幸福などを意味します。
介護におけるQOLは、ご利用者様一人ひとりのその人らしさが尊重され、ご本人が満足や幸福を感じられているかが重要です。介護職員は、どのように関わればご利用者様のQOLが向上するか、考えて行動することが求められます。
QOLに影響を与える要素
QOLに影響を与える要素は以下の4つが考えられます。
| 影響を与える要素 | 具体例 | ||
| 身体的要因 | ポジティブ要因 | 足腰がしっかりしている 良好な健康状態 栄養バランスの取れた食事 など | |
| ネガティブ要因 | 身体機能・認知機能の低下 生活習慣病の発症 栄養状態の悪化 など | ||
| 精神的要因 | ポジティブ要因 | 生きがいがある 頼れる身内や友人がいる 適切な治療を受けられる など | |
| ネガティブ要因 | 過度の過労やストレス 睡眠障害、抑うつ、不安症状 適切な治療が受けられない状況 など | ||
| 経済的要因 | ポジティブ要因 | 生きがいがある 頼れる身内や友人がいる 適切な治療を受けられる など | |
| ネガティブ要因 | 過度の疲労やストレス 睡眠障害、抑うつ、不安症状 適切な治療が受けられない状況 など | ||
| 社会的要因 | ポジティブ要因 | 安定した年金収入がある 家族からの支援がある 支援の情報が集まる など | |
| ネガティブ要因 | 低収入、困窮 支援先などの情報を知らない など | ||
上記に示した要素はあくまで一例に過ぎません。しかし、身体的・精神的・経済的な面で充実していたとしても、社会的要因が不十分であればQOLは低下する恐れがあります。
QOLを構成する要素は多岐に渡り、それぞれがバランスを取り合っていることを覚えておきましょう。
QOLを低下させる原因
QOLを低下させる原因は、身体的・精神的・経済的・社会的な要素のいずれかに起因します。
体力や記憶力の低下、慢性的な病気を抱えている状況では、幸福感を感じられない方もいらっしゃるでしょう。
その結果、疲労感やストレスを感じ、抑うつや不安にさいなまれてしまう方も少なくありません。
さらに、貧困や頼れる人が近くにいなければ、自身で問題を解決するのは簡単なことではないはずです。
このように、QOLに影響を与える要素が相互に作用し合い、よりQOLを低下させることを、介護職員一人ひとりが知っていなければなりません。
QOLとADLの関係性
QOLと同様に、介護現場で耳にすることばにADLがあります。ADLの変化に応じてQOLも向上・低下する可能性があるため、QOLとADLは密接に関わっているのです。
以下で、QOLとADLの違いやADLがQOLにもたらす影響などを解説します。
QOLとADLの違い
QOLとADLの違いを理解するために、まずはADLについて理解しましょう。
ADLとは日常生活動作の略称であり、食事や排泄、着替え、整容、移動、入浴などの生活の基本となる動作を指します。
ご利用者様の生活状況や障害の程度などを把握する上で、定量的な評価を行える指標です。
ADLがご利用者様の生活状況を客観的に評価できる指標に対し、QOLはご利用者様の主観によって判断される幸福度や満足度である点が最大の違いといえるでしょう。
ADLの具体的な評価方法
ADLでは、ご利用者様がどの程度介助が必要かを評価します。ADL評価の代表的なものには、BI(バーサルインデックス)とFIMがあります。
BIは、ご利用者様が最大限の努力をすれば「できる」と考えられるADLの潜在能力を評価する方法です。食事や移動、整容など10項目を「自立」「介助」「不能」の3段階で判定し、合計点数でADLを評価します。満点は100点です。
FIMは、実際におこなっているADLの実行状況を評価する方法です。セルフケア、排泄、コミュニケーションなど18項目を7段階で評価します。BIとの大きな違いは、認知機能も評価対象となる点です。満点は126点となります。
ADL評価をおこなうことで、ご利用者様の状態把握やケアプラン作成に役立ちます。
ADLについては以下の記事で詳しく紹介しています。ぜひご確認ください。
ADLがQOLにもたらす影響
ADLの変化によってQOLに影響を及ぼす場面は多く見られます。
例えば、ベッドで寝たきりの方を想像してみてください。病気やケガで一時的にADLが低下し、思うように体が動かせない状況ではQOLは著しく低下してしまいます。
オムツを着用する経験や処理を他人に任せなければならない状況は、自信を喪失するショッキングな体験と言えるはずです。
一方で、自身でトイレに行けるようになればどうでしょうか。尿意や便意を感じたタイミングでトイレに行けることで排泄に関する満足度は高まります。
このように、ADLの変化によってQOLの向上・低下が左右される場面が多いです。
ただし、QOLは精神的・経済的・社会的な要因によっても変化します。ADLが高いからといって、必ずしもQOLが高くなるわけではない点も覚えておきましょう。
ADL向上がQOLに好影響を与える具体例
ここでは、ADLが向上することでQOLに好影響をもたらす具体例を紹介します。
筆者が担当したご利用者様で自宅のお風呂が大好きな方がいました。しかし、お風呂までの移動や着替えをご家族に手伝ってもらう必要があり、大好きなお風呂に週に1度しか入れていなかったのです。
そこで、ベッド周りや廊下などに手すりを設置し、ご自身でも伝い歩きでお風呂まで移動できるように環境調整とリハビリを行いました。
着用する服に関しても、脱ぎ着しづらい被りのシャツから前開きのファスナータイプやボタンのシャツを提案し、ご自身で脱ぎ着しやすいもので練習を重ねました。
体を洗う動作や浴槽のまたぎ、湯船から立ち上がる動きなども練習し、必要そうな介助用具も選定しました。
ご家族には最低限の手助けに留めるようアドバイスし、多少時間がかかっても見守っていただくようにお願いをしたところ、少しずつできることが増えていったのです。
結果、ほとんど手伝わずにお風呂まで移動できるようになり、最低限の介助で服の脱ぎ着や入浴動作ができるようになりました。
好きな服が着れなくなってしまう、ご家族や訪問介護士、看護師の介助が必要な点など多くの課題は残ったままです。
しかし、ご本人は大好きなお風呂に入れる回数が増え、大変喜んでくださっている様子でした。ご利用者様のQOLはもちろん、ご家族や関わるスタッフのQOLも向上した事例だと思います。
ご利用者様のQOL向上のための介護職員の役割
ご利用者様のQOL向上のため、介護職員ができることとして以下の3つをご紹介します。
- ご利用者様の話を聞き、ニーズを拾う
- 行動を見守り、可能なことはやってもらう
- ともに楽しみ、ともに笑う
他にも求められる役割は多く存在しますが、まずはこの3つから始めてみてはいかがでしょうか。
ご利用者様の話を聞き、ニーズを拾う
まずはご利用者様がどのようなことができているか、してみたいか、興味があるのか話を聞いてみましょう。今現在の状況を把握しやすく、今日からのケアに活かせる情報が得られるかもしれません。
また、関係性が深まってくれば今までどのような人生を歩んできたか、どのような考えを大切にしているのかなど、ご利用者様の人生感を深掘りしてみてはいかがでしょうか。
ご利用者様にとって、介護職員が関わる以前の人生の方が圧倒的に長い年月を重ねています。積み重ねてきた年月に、その人らしさが詰まったエピソードも多くあるでしょう。ご本人だけでなく、時間を作ってご家族にお話を聞く時間を取れると、より多面的な視点でご利用者様について知れるようになるはずです。
もし雑談から話を広げる方法が苦手な方がいれば、厚生労働省が発行している「興味関心チェックシート」を活用してみてはいかがでしょうか。網羅的にご利用者様の興味関心を把握できますので、一つのツールとして活用してみてください。
行動を見守り、可能なことはやってもらう
ADLを評価した上で無理がある動作や危険を伴う動作以外、時間をかければ可能な動作は見守りながらサポートできるとよいでしょう。
良かれと思ってスタッフがサポートしすぎてしまうと、せっかく有している能力を発揮する場面が少なくなってしまいます。ADLの評価については複数のスタッフで見解をすり合わせ、どこまでを見守り、どこからサポートするかは統一するようにしましょう。
ご利用者様のADLを把握できれば必要以上の介助が減り、自信がついて満足度や幸福度の向上につながります。
ともに楽しみ、ともに笑う
日々の業務が忙しい場合、ご利用者様と楽しい時間を共有するのは難しいかもしれません。けれど、介護職員と利用者という関係以前に、私たちは同じ地域に住む隣人でもあります。
ケアする側、ケアされる側という関係ではなく、対等な人間同士で同じ時間をともに楽しんでみてはいかがでしょうか。
日々のレクリエーションをただの時間つぶしとして捉えるのではなく、本当にご利用者様が取り組みたいことはなんなのか真剣に考えてみるといいかもしれません。
テーブル拭きや掃除など、ご利用者様が自宅などで担っていた役割などから手伝ってもらえそうなことを模索できると、やりがいを再発見できますよ。
ご利用者様が楽しめる話題の提供
ご利用者様との関わりでは、笑顔を引き出す楽しい話題の提供が大切です。ご利用者様と盛り上がれる話題には、昔の生活に関するものがおすすめでしょう。
介護施設のご入居者様は、大正後期から昭和中期ごろに生まれた方がほとんどです。自分が育った時代の生活に関する話は、昔を思い出すことで懐かしさや親しみが湧き、きっと楽しんでもらえるでしょう。小学校時代の話や、昔流行った食べ物、音楽などの話題も、「あの頃はそうだったな」と共感を呼び、会話が盛り上がる可能性があります。
ご利用者様と話すときのポイント
ご利用者様と会話をする中で、おさえておきたいポイントは以下の通りです。
- 目線が合う高さで話す
- ゆっくりと適度な音量で話す
- 相槌を交え、話を引き出す
「この人はちゃんと私の話を聞いてくれている」と思ってもらえるような、共感的態度が大切です。ご利用者様が話やすくなるような、暖かいコミュニケーションを意識しましょう。
ご利用者様との話題に困ったときは、以下の記事も参考にしてください。
ご利用者様のQOL向上のために必要な連携
ご利用者様のQOL向上のためには主に3つの連携が必要になります。
- 介護職員同士の連携
- 医療職種との連携
- 家族との連携
ご利用者様のQOLを向上させるには介護職員1人では力不足です。同職種の仲間や多職種との連携、ご家族の協力があってQOLの向上につながります。
介護職員同士の連携
まずはQOLの向上を目指して介護職員同士で連携をしていきましょう。ケースカンファレンスや日常の業務の中でご利用者様の話をし、どのようなケアが適切か、どんなことに興味がありそうかなど話し合えるとよいと思います。
そのためにも、職員同士が雑談などをできる雰囲気作りが重要です。必要以上に仲良くなる必要はありませんが、ご利用者様の話を気軽に相談しあえる関係性が望ましいでしょう。
そういった相談の積み重ねを経て、ケースカンファレンスなどで質の高い議論ができれば、自然と連携もスムーズに取れるようになるはずです。
以下の記事で、コミュニケーションがうまくいかないときの対処法やコミュニケーションを学ぶ方法を解説しています。介護職員同士のコミュニケーションに不安を感じている方は、ぜひご確認ください。
医療職種との連携
介護と医療の考えは、時にぶつかり合ってしまうことがあります。看護師やリハビリスタッフと考え方が合わず、うまく連携が取れないと感じる方は少なくありません。
学んできたことが違うわけですから、考えが完全に合わないのは当然のはずです。けれど、ご利用者様のために力になりたいという考えは、どの職種も同じだと思います。
まずは介護職員同士で話すように、ご利用者様を中心に考えて議論を重ねてみてはいかがでしょうか。その中で妥協できる点を見つけ、なるべく同じゴールに向かっていけるように歩み寄る姿勢も大切だと思います。
お互いの専門性を持ち寄れば、多様な視点でご利用者様のケアができるようになります。日常生活の細かい変化や心の動きは、介護職員がまず気付く要素の一つではないでしょうか。
その変化を医療職種に共有し、よりよいケアやリハビリテーションにつながるように協力できるとQOL向上にもつながるでしょう。
家族との連携
ご利用者様のこれまでを最も知っているのはご家族です。家族との連携はQOL向上のために必要な連携となりますので、良好な関係を築けるように意識しましょう。
まずはご家族から信頼していただく必要があるため、現在の生活状況やちょっとした変化など、連絡が取れるたびに報告してみてください。
自然と話が膨らみ、職員では知り得なかった情報も聞き出せるかもしれません。ただし、全てのご家族が協力的ではないことも念頭に入れておきましょう。
うまく連携を取れない場合、別のキーパーソンやそれまで別のサービスで関わっていたスタッフなど、ご利用者様の周辺にいる関係者にアポイントを取る必要が出てくるかもしれません。
必要に応じて関係者からの情報を取りつつ、ご家族と連携できる方法も模索していくとよいでしょう。
介護におけるQOLについての質問
最後に介護におけるQOLについての質問と回答をまとめました。
なぜ介護にQOLの視点が必要なのでしょうか?
QOLとは人生の満足度や幸福度を表すことばであり、どの利用者様でも大切にしなければならない視点です。単にADLが高い状態であっても、必ずしもQOLが高いとはいえません。
そのため、身体的・精神的・経済的・社会的な要素の中でどの点が満たされているのか、または満たされていないのかを介護職員の目からも見る必要があります。
介護の視点で得た気付きは、医療職種やご家族では気付けないものもあるでしょう。
お互いの専門性や経験を持ち寄ることが、ご利用者様のQOL向上につながる糸口となるのです。
ADLとの関連性はありますか?
QOLとADLには密接な関係があります。ADLが高まればQOLも高まり、ADLが低下すればQOLも低下する場面は多く経験するでしょう。
ただし、ADLが低い状態でも家族関係に恵まれ、幸せを感じながら生活できている方も多くいらっしゃいます。一方でADLが高かったとしても、経済的な悩みや精神的な不調をきたし、著しくQOLが下がっている方も少なくありません。
必ずしも相関関係にあるわけではなく、互いが関係し合う一つの要因であることを理解しておきましょう。
まとめ
今回は、介護におけるQOLの詳細やADLとの関連性、QOL向上のために介護職員ができることなどをご紹介しました。
ご利用者様のQOL向上を目指すには、まずQOLのことを知り、どのような場合に良好・不良な状態になるか理解することから始めましょう。
その上で、ご利用者様がどのようなことができるのか、してみたいことや何に興味があるのかを、複数のスタッフで見解をすり合わせてみることをおすすめします。
介護や医療、ご家族の視点を合わせれば、より多様な目でご利用者様のQOLを捉えることができるかもしれません。
まずはよく観察し、寄り添って話を聞いて、一緒に楽しい時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。ご利用者様と同じ視点に立てば、何に幸福を感じるのか気付けてQOL向上の糸口が見えてくるはずです。
この記事を書いたのは・・・

梶原 たくま/Webライター
保有資格:理学療法士
2014年に理学療法士免許取得。生活期の病院に勤務し、入院・外来・予防・通所・訪問リハビリテーションに従事。現在は訪問看護ステーションと医療系出版社に所属しつつ、ライター活動を行っている。