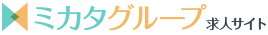「体位交換の方法がよくわからない」「体位交換がうまくできない」と悩んでいる人もいるのではないでしょうか。
間違った方法で対応した結果、ご利用者様に不快感を与えたり、最悪の場合怪我につながってしまったりする可能性もあります。
また、体位交換をうまくできないままでいると、夜勤で一人対応をしなければならないときに困ってしまうでしょう。
本記事では、体位交換の目的や手順、注意点などを解説していきます。
記事を読めば、体位交換の正しい手順や注意点がわかり、自信を持って対応できるようになるでしょう。
この記事の内容
体位交換とは
体位交換とは、自分の力で体の向きを変えることができないご利用者様の体の向きや位置を交換する介助のことを指します。
例えば、左側臥位(左横向き)になっている体制を右側臥位(右横向き)に変えることなどです。
体位交換は、ケアプランにも記載されることが多く、必要に応じて実施すべき介護ケアとなります。
体位交換の目的
体位交換の目的は大きく分けて4つあります。
ここからは、体位交換の4つの目的を具体的に解説していきます。
褥瘡を防ぐため
体位交換の一つ目の目的は褥瘡を防ぐためです。
なぜなら、褥瘡は同じ姿勢でいることで起こり得るからです。
同じ姿勢でいると一点に圧が集中します。
その圧が集中することで、褥瘡ができてしまうのです。
褥瘡ができると皮膚の炎症から水ぶくれを起こしたり、傷口から細菌感染症になってしまったりします。
リスクの高い症状となるため、徹底して防いでいきたいところです。
痛みを予防するため
体位交換の目的の二つ目は、痛みの予防です。
同じ姿勢で長時間いて、体が痛くなった経験がある人は多いと思います。
当然、高齢者も同じように長時間姿勢を変えないと体に痛みを感じるようになります。
痛みの発生を予防するためには、定期的に向きを変えることが必要です。
訪室のきっかけになるため
三つ目の体位交換の目的は、訪室のきっかけにするためです。
定期的に体位交換をすることで訪室の時間を増やせます。
特に寝たきりのご利用者様である場合、訪室の機会が減りやすく、放置状態になってしまう可能性があります。
それを阻止するためにも、時間を決めて体位交換をしていくことが大切です。
定期的に訪室することで、ご利用者様の状態の観察が可能なだけでなく、安心感を与えることができます。
日常生活上の支援の一つとして重要であるため
日常生活上の支援として、体位交換は重要な項目になります。
必要があれば、体位交換はケアプランにも記載される項目です。
実施する介護ケアとしてご家族様にも事前に説明しているため、介護サービスとしてそれを果たす義務があります。
日常生活の支援の一つとして、必要に応じて実施するのが体位交換になります。
体位の種類
体位交換での体位の種類は複数あります。
主な種類は次のとおりです。
| 呼称 | 状態 |
| 仰臥位(ぎょうがい) | 仰向けの姿勢 |
| 側臥位(そくがい) | 横向きの姿勢 |
| 腹臥位(ふくがい) | うつぶせの姿勢 |
| 長坐位(ちょうざい) | 上半身を起こし足が伸びた状態 |
| 端坐位(たんざい) | ベッドなどの端に座った状態 |
| 半坐位(はんざい) | 座位と仰臥位のあいだの状態 |
| 椅坐位(いざい) | 椅子に座った状態 |
体位は、大きく分けると寝た状態と座った状態の2つになります。
そこから細分化された姿勢・状態が上記の表のとおりです。
体位交換の手順
体位交換の基本的な手順は次のとおりです。
【寝たきりのご利用者様の体の向きを変える場合】
- 訪室し、ご利用者様に声かけをする
- ご利用者様の向いている方向の反対側に立つ
- 布団をとる
- あてていたかっていたクッションをとる
- ご利用者様の手足を巻き込まないようにコンパクトにまとめる
- ご利用者様の肩と足の下に手を入れ、自分のほうに引き寄せる
- 先ほど向いていた方向とは反対側にご利用者様の体を向ける(それか必要に応じて仰臥位にする)
- クッションをあてる
- 布団をかける
- 声をかけ退室する
基本的な流れは上記のとおりですが、ご利用者様の状態によって異なることもあります。
ご利用者様の状態に合わせながら実施するようにしましょう。
体位交換の注意点
体位交換の際には、気を付けたいポイントがいくつかあります。
ここからは、体位交換の注意点を5つ紹介していきます。
- 手足の巻き込みに注意する
- 顔色や様子を確認してから行う
- 必ず実施前に声をかける
- 一点に圧をかけないような姿勢を意識する
- 力加減に注意する
1つずつ見ていきましょう。
手足の巻き込みに注意する
体位交換の際には、手足の巻き込みに注意しましょう。
例えば、側臥位(横向き)の体制にする場合、手足に意識を向けないと、誤って巻き込んでしまう可能性があります。
手足を誤って巻き込んでしまうと、最悪の場合、骨折の原因となってしまう恐れもあります。
体位交換を行うときには、体を動かす前に必ず手足の位置を確認し、巻き込まないように配慮することが大切です。
顔色や様子を確認してから行う
体位交換の際には、ご利用者様の顔色や様子を確認してから行うことが大切です。
なぜなら、体調の悪いときに体位交換をすると、症状を悪化させてしまう可能性があるからです。
例えば、吐き気があるときにそれに気づかず体位交換を進めてしまうと、嘔吐を引き起こしてしまう恐れがあります。
体位交換の前には、必ずご利用者様の顔色や様子を確認し、違和感を覚えたら看護師などに報告するようにしましょう。
必ず実施前に声をかける
体位交換の実施前には、必ずご利用者様に声かけをしてください。
なぜなら、声かけをしないまま体位交換を無言で進めてしまえば、ご利用者様は「今何をされているのか」がわからず恐怖心を抱いてしまうからです。
ご自身に置き換えて考えれば、イメージが沸くと思います。
声かけをしないことによりご利用者様が恐怖心を抱くと、体位交換を拒否したり、緊張から体が硬直したりして、スムーズに体位交換ができない原因にもなってしまいます。
「今から反対側に向きますね」などと声をかけ、お互いに気持ちよく体位交換を行うようにしましょう。
一点に圧をかけないような姿勢を意識する
体位交換で大切なのは、一点に圧をかけないような姿勢を意識するということです。
ポジショニングのためにクッションを使用することがありますが、こちらのクッションもあて方により一点に圧が集中してしまうことがあります。
一点に圧が集中すると褥瘡の原因となりますので、そうならないようなクッションのあて方が重要です。
例えば、側臥位の際に足にあてるクッションは足全体にあてがえるような広めのものを使うなど、一点に集中しないような工夫をしていくことがおすすめです。
力加減に注意する
体位交換をする際には、力加減に注意するようにしましょう。
なぜなら、力を入れすぎると柵にぶつかり内出血を引き起こしたり、摩擦からびらんの原因になったりしてしまうためです。
力任せに体位交換を行ってしまうと怪我の原因となりますので、特に注意してください。
体位交換にはボディメカニクスを意識することがおすすめです。
ボディメカニクスについては。以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。
体位交換に関するQ&A
体位交換に関するよくある質問があります。
ここからは、よくある質問とその回答を紹介していきます。
体位交換の時間間隔は?
体位交換での時間間隔は、2時間置きが理想的と言われています。
実際に筆者も介護職員時代は、2時間置きにご利用者様の体位交換を行っていました。
ただし、ご本人の症状やさまざまな背景から、それ以外の時間間隔がベストな場合もあります。
ご利用者様の状態や状況に合わせて、ベストな時間間隔を職員間で話し合い実施していきましょう。
ポジショニングで使う道具は?
ポジショニングでよく使われる道具は「ポジショニングクッション」です。
抱き枕にできるタイプや正方形のもの、三角のものまで、さまざまなタイプのクッションがあります。
ポジショニングクッションを検索をするとさまざまな商品が出てきますので、クッションを探している場合は検索してみるのがおすすめです。
まとめ
体位交換は、ご利用者様の褥瘡や不快感を防止するための大切な介護ケアです。
正しい手順や注意点を把握し、効果的な体位交換を実施していきましょう。
記事を参考に、注意すべきポイントを掴めば、安全な体位交換ができるようになります。
安全性が高い体位交換を実施し、ご利用者様との信頼関係を深めていきましょう。
この記事を書いたのは・・・

中村 亜美/Webライター
保有資格:介護福祉士
特別養護老人ホームでユニットリーダーとして11年程勤務。
その後はフリーライターとして活動中。在宅介護者や介護事業者、介護職員向けのコラム・取材記事を執筆している。