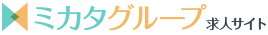介護職員として働いていると、終末期ケアに関心を持つ方もいるでしょう。ホスピスはがん末期の方を中心に、痛みや不安を和らげ、その人らしい最期を迎えられるよう支援する場所です。
本記事では、ホスピスの概要やケアの内容、入院条件、介護職員の役割について詳しく解説します。ホスピスでの仕事に興味がある方、終末期ケアの専門性を高めたい方は、ぜひ参考にしてください。
この記事の内容
ホスピスとは
ホスピスとは、末期がんのような終末期のご利用者様に対し、身体的な痛みや精神的、社会的な苦しみを和らげるケアをおこなう施設です。残された時間を穏やかに、そしてその人らしく過ごせるように支援する施設で、日本全国に460箇所以上のホスピスがあります。
ホスピスケアとは
ホスピスケアは、終末期にある方とそのご家族の苦痛を緩和し、尊厳ある最期を迎えられるように支援することを目的としています。
終末期においては、延命を目的とした治療はおこなわず、医師や看護師、ソーシャルワーカー、カウンセラーなどがチームを組み、身体的・精神的な苦痛や社会的な不安を緩和することを目指します。
痛みの管理だけでなく、家族関係や経済的な悩み、抑うつ、生きる意味の喪失などにも包括的に対応し、ご利用者様が最期まで自分らしく過ごせるよう支援することを目的としています。
病院との役割の違い
病院は病気の治療や延命を目的とするのに対し、ホスピスは治療を終了した患者が最期を穏やかに迎えられるようサポートする場です。
そのため、病院では積極的な治療がおこなわれますが、ホスピスでは痛みや苦痛を和らげることが最優先となります。
ホスピスでは、病気を治すための治療ではなく、症状を和らげること、そして心のケアに重点を置き、ご利用者様とご家族が、残された時間を穏やかに、自分らしく過ごせるようサポートします。
緩和ケアとの違い
ホスピスケアと緩和ケアは似ていますが、対象となる患者の段階が異なります。
緩和ケアは、がんなどの診断初期から治療と並行して提供される医療やケアを指します。
一方、ホスピスケアは主に終末期に焦点を当てたケアのことです。
ただし、実際の医療現場では両者の区別は明確ではなく、どちらも患者さんの苦痛を和らげ、QOL(生活の質)の向上を目指すという点で共通しています。最近では、これらを包括的に「緩和ケア」と表現することも増えているのが現状です。
ホスピスで提供されるケア
ホスピスで提供されるケアは、主に以下の3つに分類される
- 身体的ケア
- 精神的ケア
- 社会的ケア
ひとつずつ解説します。
1.身体的ケア
身体的なケアでは、ご利用者様の苦痛を和らげることが最優先の目標です。
痛みのコントロールのための医療用麻薬の投与や、呼吸困難時の酸素吸入、点滴による水分・栄養補給などの医療的ケアを提供することもあります。
さらに、体位変換や清潔ケアをおこない、褥瘡(床ずれ)の予防にも努め、食事や入浴、排泄の介助、清拭や整容など、日常生活全般のサポートもおこないます。ただし、病気の治癒を目指した積極的な治療はおこなわず、症状の緩和に重点を置いています。
2.精神的ケア
ホスピスでは、患者の精神的な負担を軽減することも重要です。
終末期には不安や恐怖、抑うつなどの感情が強まるため、カウンセラーによるカウンセリングやメンタルケアを実施しています。レクリエーションや季節のイベントを通じて心を癒す機会を設けています。
また、家族との対話の時間を大切にし、患者さんが安心して過ごせる環境づくりに努めていることも特徴のひとつです。好きな音楽を流したり、居心地の良い空間を整えたりするなど、一人ひとりの希望に沿った支援をおこなっています。
3.社会的ケア
社会的な課題に対するサポートもホスピスでのケアのひとつです。
ソーシャルワーカーが中心となって、経済的な相談や各種手続きの代行、介護・看護サービスの調整を担当します。
具体的には、以下のような場面で調整が必要です。
- 入院費や医療費の手続き
- 相続や財産分与に関する相談対応
- 介護・看護サービスの手配と調整
- 遺品整理に関するサポート
- 各種社会保障制度の活用支援
また、家族への支援も重要な役割であり、ご利用者様と家族が安心して療養生活を送れるよう、さまざまな側面からサポートを提供します
ホスピスの受け入れ条件
ホスピスの入院条件は、病院にある緩和ケア病棟と介護施設とで異なります。
緩和ケア病棟では、主に末期がんや難病など、厚生労働大臣が定める疾病を持ち、治療が困難になった患者が対象です。入院には医師の診断と紹介状が必要で、余命6か月以内が目安とされています。ご利用者様本人が積極的な治療ではなく緩和ケアを希望していることも要件のひとつです。
一方、特養や有料老人ホームのような介護施設では、病院ほど厳密な基準はなく、医療依存度が低い患者でも入居可能です。ただし、施設によって受け入れ基準が異なり、看取り対応ができるかどうかも確認が必要です。
【厚生労働大臣が定める疾病】
- 末期の悪性腫瘍(がん)
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病関連疾患
- 多系統萎縮症
- プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ライソゾーム病
- 副腎白質ジストロフィー
- 脊髄性筋萎縮症
- 球脊髄性筋萎縮症
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 後天性免疫不全症候群(エイズ)
- 頸髄損傷
- 人工呼吸器を使用している状態
ホスピスケアを提供している場所
ホスピスケアは、主に病院の緩和ケア病棟や高齢者向け住宅、介護保険施設で提供されています。本章では、それぞれの場所でのホスピスケアの内容について解説します。
病院の緩和ケア病棟
緩和ケア病棟は、充実した医療設備と専門的なケアチームを備えた医療機関です。
24時間体制で医師が常駐し、急な症状の変化にも即座に対応可能です。症状が安定すると在宅療養や他施設への移行を検討することもあります。
高齢者向け住宅
ホスピスケアに対応する高齢者向け住宅には、介護付き有料老人ホームや住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などがあります。
介護付き有料老人ホームは24時間介護スタッフが常駐し、医療機関と連携してケアを提供しています。また、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅では、訪問診療と訪問看護を組み合わせることで、必要な医療ケアも提供されます。
介護保険施設
特別養護老人ホームや介護老人保健施設、介護医療院などの介護保険施設でもホスピスケアをおこなっています。
病院と違い、明確な期限はなく、生活上の制限も少ないため、その方らしい生活を重視できるでしょう。いずれの施設も看取り介護の一環としてホスピスケアを提供しています。
介護老人保健施設で働く介護士の主な仕事内容には、前述の食事や排泄などの身体介護や体調管理に加えて、集団リハビリテーションやイベントの企画・開催なども含まれます。
集団リハビリテーションは、リハビリの専門職と協力しながら、ストレッチや体操、脳トレなどを数人から数十人のご利用者様と一緒におこなうリハビリです。
ご利用者様ごとに身体機能のレベルが異なるため、できるだけ多くの方が参加できるような工夫が求められるでしょう。
また、イベント企画・開催は、ご利用者様に定期的な楽しみを提供することを目的としておこなわれます。ご利用者様は1日を同じような生活リズムで過ごすことが多いため、普段とは違う刺激を提供し、身体機能の維持や認知症状の緩和を目指します。具体的には、季節の行事や誕生日会などの企画・開催が多いです。実施後には、ご利用者様から「楽しかった」といった感想を頂くことも少なくありません。
介護保険施設で働く介護職員の仕事について詳しく知りたい方は、「介護老人保健施設の仕事内容を紹介|給与や働くメリットもあわせて解説」の記事をご確認ください。
ホスピスでの介護職員の役割
ホスピスでは、看護師と介護職員が密接に連携しながら、ご利用者様とご家族に寄り添うケアを提供しています。本章では、ホスピスの介護職員の役割について、一般の病棟や介護施設との違いや終末期ケアに必要なスキルについて解説します。
一般病棟や介護施設との違い
ホスピスでは、治療ではなく生活の質(QOL)向上を目的としたケアを提供します。
一般病棟は病気の治療や延命処置が中心ですが、ホスピスでは積極的な治療はおこなわず、痛みや苦痛を和らげることが最優先されます。
また、介護施設では長期的なケアが主流ですが、ホスピスは終末期の患者に特化し、比較的短期間の滞在が一般的です。そのなかで介護職員は、食事・排泄・清潔保持などの基本的な介助に加え、ご利用者様やご家族の精神的なケアや看取り支援も担い、より深い関わりが求められます。
終末期ケアに必要なスキル
ホスピスでの終末期ケアには、専門的なスキルが求められます。
まず、痛みや呼吸困難など終末期特有の症状を理解し、適切な対応をおこなう知識が必要です。また、ご利用者様やご家族の不安に寄り添い、安心感を与えるための傾聴や共感力も重要です。
さらに、最期の瞬間を穏やかに迎えられるよう環境を整えるだけではなく、家族の心のケアも求められます。加えて、医療スタッフとの連携や、介護職員自身が精神的負担を抱えすぎない工夫も必要となります。
医療スタッフや介護スタッフとの連携を円滑にするには、互いの意見や立場を尊重できる関係性を作ることや、ミニカンファレンスなどの情報共有の場を設けることが大切です。
必要以上に親しくなる必要はありませんが、普段から気軽に雑談できる関係や雰囲気づくりを心がけておくと、意見がまとまりやすくなります。
また、職種が異なったり、上司と部下といった立場の違いがある場合、意見がぶつかる可能性も少なくありません。互いの考え方や思いを話し合う時間を設け、それぞれの立場を尊重しながら、意見の伝え方にも工夫してみましょう。
また、連携を取り合う中で「誰のためのケアなのか」を常に問い続けることも大切でしょう。
介護現場でのチームワークについて詳しく知りたい方は、「介護職にチームワークは必須!良くするコツやリーダーの役割は?」の記事もご確認ください。
まとめ
ホスピスは、終末期を迎えた方が、痛みや不安を抱えることなく、自分らしい最期を迎えられるよう支援する場所です。病院とは異なり、積極的な治療はおこなわず、身体的、精神的、社会的な苦痛の緩和に重点を置いています。
介護職員としてホスピスで働くことは、一般病棟や介護施設とは異なる専門的な知識やスキルが求められますが、終末期ケアに関心のある方は、ホスピスでの仕事も検討してみてはいかがでしょうか。
新しい職場を探す際は、転職支援サイトの利用がおすすめです。「介護転職のミカタ」では、専門のコンサルタントが職場選びから入職までの転職活動をサポートしてくれます。無料で利用できるので、ぜひお気軽にご相談ください。
この記事を書いたのは・・・

さとひろ/Webライター
保有資格:ケアマネジャー/社会福祉士/介護福祉士/公認心理師
介護業界で22年の経験をもつ、特別養護老人ホームの現役ケアマネジャー兼生活相談員。介護職員・ケアマネジャー・生活相談員としての経験をもとにわかりやすい記事を執筆します。