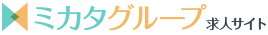「誤嚥をしたときにどう対応すればよいかわからないから、食事介助が怖くなる」と思っている介護職員の方もいるのではないでしょうか。
誤嚥に対する知識がないまま食事介助を行うのは確かに怖いことだと思います。
本記事では、誤嚥によるリスクや症状、対応手順や防ぐためのポイントなどを解説していきます。
記事を読めば、誤嚥症状がでたときの対応方法や防ぐためにできることがわかり、安心して介護現場で働くことができるようになるでしょう。
この記事の内容
誤嚥(ごえん)とは
誤嚥とは口に入れたものが食道ではなく、誤って気管に入ってしまうことを言います。
高齢者は誤嚥のリスクが高くなると言われており、介護施設やデイサービスで仕事をする際には、十分に誤嚥リスクに配慮する必要があります。
ここからは、誤嚥リスクや症状について詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
誤嚥によるリスク
誤嚥によるリスクは、大きくわけて次の2つです。
- 窒息
- 誤嚥性肺炎
誤嚥をすると食べ物や異物が気管に入るので、場合によっては窒息します。
また、誤嚥性肺炎といって、誤嚥が原因で肺に炎症を起こしてしまう可能性もあります。
上記2つのリスクは、最悪の場合、死にも直結する恐ろしいものです。
ご利用者様の健康や安全を守るためにも、誤嚥を防ぐことは大切であるともいえます。
症状
誤嚥の主な症状は次のとおりです。
- 激しくむせ込む
- 呼吸困難になる
また、誤嚥が重症な場合は、顔面が紅潮したり、手足が紫になるチアノーゼが起こったりします。
そのまま気を失ってしまうこともあるため、誤嚥に気づいたら迅速な対応が必要となります。
一刻を争うほどの重症な場合は、吸引をしながら看護師をすぐに呼ぶようにしましょう。
必要時は救急搬送
ご利用者様が誤嚥をした際の対応の1つとして、救急搬送も念頭においておく必要があります。
看護師がその場に立ち会っている場合、介護職員は看護師の指示に従い対応するのが基本となります。
ですが、事業所によって看護職員の配置基準はさまざまあるため、常時看護師が現場にいる事業所ばかりではありません。
その場合は、介護職員でご利用者様の状態を確認し、救急搬送が必要であると迅速に判断することが重要です。
対応が遅れるとご利用者様の生命に危険があるため、緊急時の対応マニュアルは必ず確認しておくようにしましょう。
また、食事の時にはご利用者様の摂取状況を日々観察し、急変にはいち早く気が付く体制をとっておきましょう。
介護職員の緊急時対応をくわしく知りたい方は、介護職員の緊急時対応を解説|落ち着いて対処するための方法をご一読ください。
誤嚥の主な原因3つ
誤嚥の主な原因は、大きく分けて3つです。
- 唾液量の低下
- 筋力の低下
- 歯が少なくなる
ここからは誤嚥の主な原因3つについて解説していきます。
唾液量の低下
誤嚥の原因の一つ目は、唾液の分泌量の低下です。
唾液の量が低下することで口腔内の乾燥が進み、食事を飲み込みにくくなるためです。
高齢になると、唾液の分泌量が減ると言われています。
薬の副作用により唾液量が低下することもあります。
高齢者は年齢的な影響に加え、疾患により薬を多く処方されているケースが多く、唾液の量が低下しやすい傾向にあります。
また、逆に唾液の量が多すぎても誤嚥の原因になります。
高齢者は、唾液の分泌量が適切でないケースが多いということが、誤嚥リスクが高い理由であるといえるでしょう。
筋力の低下
筋力の低下も、誤嚥の原因の一つです。
なぜなら、筋力は食事の飲み込みにおいて重要だからです。
例えば、喉周辺の筋肉や顔の筋肉が衰えれば、食事がしにくくなります。
うまく飲み込みができず、誤って気管に入り誤嚥を起こしてしまうのです。
歯が少なくなる
高齢になると歯が抜けて、若いときよりも数が少なくなる傾向があります。
歯が少なくなると、若いときほど食べ物をうまくすりつぶせなくなるでしょう。
食べ物をうまくすりつぶせないまま、飲み込もうとすれば当然誤嚥リスクは高まります。
歯が少なくなるというのも、誤嚥リスクにつながる一つの原因であるといえます。
食事形態が適切ではない
ご利用者様に提供する介護食の形態が適切ではない場合も、誤嚥の原因となります。
高齢になると、食べ物をかみ砕く咀嚼機能、咀嚼した食べ物を食堂へ送り込む嚥下機能が低下します。
そういった方に、正常な食事機能を持つ人と同様の食事を提供しても、うまく食べることができず、その結果誤嚥してしまう危険があります。
高齢者に食事を提供する際は、必ず食事機能の評価を行い、どういった介護食が適切で安全に食べて頂くことができるのかを確認する必要があります。
主治医・歯科医・言語聴覚士とともに、ご利用者様に食事を楽しんで頂けるよう支援をしていくことが大切です。
食事形態や介護食について、くわしく知りたい方は、介護食とは|適正な食事形態の判断方法や調理のポイントを紹介をご覧ください。
誤嚥の症状がでたときの対応手順
誤嚥の症状がでたときの対応手順は大きく分けて3段階です。
ここからは、誤嚥の症状がでたときの対応手順について詳しく解説していきます。
1:食事を中断する
まずは、すぐに食事を中断します。
誤嚥の症状がでているのに、本人が食べ続けようとしたら、声をかけて中断するように促しましょう。
誤嚥をしている状況で水を飲ませるなども危険です。
まずは中断してから次のアクションに移りましょう。
2:飲み込んだものを出してもらうようにする
食事を中断したら、飲み込んだものを出してもらうようにします。
ご利用者様が自分で出せそうな場合は、介護職員がサポートをしつつ、出してもらうようにしましょう。
サポートする際には、ご利用者様に前かがみになってもらい咳を促すようにします。
誤嚥したものの除去が難しい場合は、吸引が必要になる場合があります。
必要に応じて、この時点で看護師などに連絡するようにしましょう。
3:必要に応じて酸素濃度測定をし、看護師に相談や報告をする
誤嚥時の対応をしたあとは、口の中のものが除去され、本人が落ち着いたかを確認しましょう。
確認ができたら看護師に状況を報告し、必要があれば様子を見に来てもらいます。
また、酸素濃度測定もこの時点でしておくと安心です。
元気を取り戻したからと安心せず、起こった一連のことは他の職員に報告するようにしましょう。
介護記録にも残しておくことが大切です。
誤嚥を防ぐためのポイント
誤嚥の予防には、そのためのポイントを押さえることが大切です。
ここからは、誤嚥を防ぐためのポイント3つを解説していきます。
食事中の姿勢に注意する
誤嚥を防ぐために、まずは、食事中の姿勢に注意することが大切です。
誤った姿勢で食事を進めてしまうと、口に入れたものが食道に入らず場合によっては気管に入ってしまう恐れがあります。
例えば、腰が後ろに倒れすぎていたり、顎が上を向いていたりする状態は誤嚥のリスクが高まり危険です。
食事中の正しい姿勢は、次のとおりです。
- 顎が下がった状態
- 股や膝、足関節の角度が約90度になっている状態
- 軽い前傾姿勢
- 重心が前にある状態
- 足裏が地につき安定した状態
ただし、疾患や身体の状態により、上記のように理想的な姿勢を保てないご利用者様もいます。
そういった場合は、クッションなどで体位保持をしながら食事を進めていきましょう。
食事介助の際には飲み込み確認をする
誤嚥を防ぐためには、食事介助時の飲み込みの確認も大切です。
食事の介助を行う場合は、食事ペースが介護職員に委ねられます。
飲み込みができていない状態で次々に食事を口に運ぶと、ご利用者様の誤嚥のリスクは当然高まります。
食事介助の際には、毎回喉の動きを観察し、飲み込みが確認できた後に次の食事を口に運ぶようにしましょう。
適切な時間で食事する
誤嚥を防ぐための最後のポイントは、適切な時間で食事をするということです。
食事の際には、集中力も大切であると言われており、時間が長すぎると誤嚥のリスクが高まります。
反対に食事のペースが早すぎるのも飲み込みしきれていない可能性があり、危険です。
一回の食事における適切な時間は、30分程度と言われています。
時間内に食べきれなかった場合は一旦中止し、時間を置いて他のもので栄養を補うなど、管理栄養士や看護師と相談しながら誤嚥リスクに配慮した食事を進めていきましょう。
誤嚥を予防する方法
ご利用者様の誤嚥を予防する方法は、いくつかあります。
ここからは、介護施設でもよく実践されている誤嚥を予防する方法を3つ紹介していきます。
口腔のリハビリ体操
誤嚥を予防する方法として、口腔のリハビリ体操がおすすめです。
口腔体操をすることで、口やのどの筋肉が鍛えられ誤嚥を防ぐことにつながるからです。
誤嚥を予防する口腔体操の例は、次のとおりです。
- パタカラ体操(ぱ、た、か、らと大きな声で発生する体操)
- 舌の体操(舌を上下左右に動かす体操)
- 口の体操(大きく口を開けたり、すぼめたりを繰り返す体操)
口腔体操はリハビリとして、介護施設やデイサービスでもよく実践されています。
ご利用者様に安心してご飯を食べてもらうためにも、口腔体操を積極的に取り入れていきましょう。
口腔ケア
誤嚥を予防する方法としては、口腔ケアも有効です。
口腔ケアとは、口腔内の清潔を保つためのケアのことを指します。
口腔内を清潔に保つことで、唾液の分泌を促したり、誤嚥したときに細菌が肺に入ってしまうのを防いだりすることができます。
誤嚥予防のための口腔ケア例は、次のとおりです。
- 歯磨き
- 舌磨き
- 口腔内の保湿剤塗布
- 口腔ケア用スポンジでの口腔内の細菌除去
口腔ケアはご利用者様の状態によって、方法が異なります。
ご利用者様の心身の状態や疾患に合った口腔ケア方法を実践していきましょう。
アイスマッサージ
誤嚥予防としては、アイスマッサージもおすすめです。
アイスマッサージとは、食事前に綿棒で口腔内に刺激を与えるマッサージのことです。
食前にアイスマッサージを行うことで、口腔内の嚥下反射を誘発し、安全な飲み込みができるようにします。
アイスマッサージの方法としては、氷が入ったコップの中に綿棒を入れ、冷たくなったその綿棒をご利用者様の口腔内に当てて刺激を促していきます。スプーンを利用して実施するのもおすすめです。
嚥下機能が低下してしまったご利用者様には、アイスマッサージをしながら食事介助をすることで誤嚥を防ぐことが可能です。
まとめ
ご利用者様の安心・安全を守るためには、日頃から誤嚥予防をしていくことが大切です。
記事内で紹介した方法で、誤嚥予防をしていきましょう。
また、誤嚥症状がでた場合には、迅速な対応が必要になることもあります。
看護師と連携しながら、指示を仰ぎ適切な対応をすることが重要です。
誤嚥リスクや対応方法の知識を深め、介護現場で困らないようにしていきましょう。
この記事を書いたのは・・・

中村 亜美/Webライター
保有資格:介護福祉士
特別養護老人ホームでユニットリーダーとして11年程勤務。
その後はフリーライターとして活動中。在宅介護者や介護事業者、介護職員向けのコラム・取材記事を執筆している。