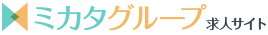「急にやる気がなくなったけど、これってもしかして燃え尽き症候群ではないだろうか」と悩んでいる介護職員の方もいるのではないでしょうか。
燃え尽き症候群の疑いがあるにも関わらず、その対処法がわからないままでは、症状はどんどん悪化してやる気を失ってしまう可能性があります。
本記事では、介護職員が燃え尽き症候群になりやすい理由や予防方法、症状や治療方法などを解説していきます。
記事を読めば、燃え尽き症候群を防ぐことができるようになるでしょう。
この記事の内容
燃え尽き症候群(バーンアウト)とは
燃え尽き症候群とは、意欲的に仕事に取り組んでいた人がふとしたきっかけで燃え尽きたようにやる気を失ってしまうことを指します。
介護職員でも、この燃え尽き症候群になってしまう人は一定数います。
特に人手不足や責任の重さから、介護職員一人に対し、負担がかかりやすい介護は燃え尽き症候群になりやすい職種でもあるでしょう。
燃え尽き症候群になると、意欲をなくし、さまざまな面に支障が出てしまうことがあります。
それを回避するために大切なのは、適切な予防策です。
しっかりと予防をすれば、燃え尽き症候群は回避できますので、ぜひ記事の内容を参考に予防していきましょう。
介護職で燃え尽き症候群になってしまう理由3つ
介護職員が燃え尽き症候群になってしまう理由は、主に3つあります。
ここからは、介護職で燃え尽き症候群になってしまう3つの理由を解説していきます。
- 責任が重くプレッシャーがかかるから
- 頑張りすぎてしまうから
- 心身ともに負担がかかりやすいから
1つずつ見ていきましょう。
責任が重くプレッシャーがかかるから
介護の仕事に対し、プレッシャーを感じてしまい燃え尽き症候群になってしまう人もいます。
介護は、さまざまな理由でプレッシャーを感じやすい仕事です。
例えば、ご利用者様やご家族からのクレーム対応や命に関わるような緊急事態への対処もしなければなりません。
責任が重く、そのプレッシャーに押しつぶされてしまうこともあるでしょう。
頑張りすぎてしまうから
介護職員で頑張りすぎてしまう人も、燃え尽き症候群になりやすいです。
頑張りすぎて心身に不調が起こると、元気を取り戻せなくなってしまう可能性があるからです。
例えば、排泄介助や食事介助など、全体業務をほとんど一人でこなそうとして頑張った結果、疲れてそのまま退職してしまったというケースもあります。
事に対し、意欲的な姿勢を見せることは大切ですが、いきすぎると自分の心身を壊してしまいますので、適度に行うようにしていきましょう。
心身ともに負担がかかりやすいから
介護の仕事で燃え尽き症候群になりやすいのは、心身ともに負担がかかりやすいのも理由の一つです。
介護現場の仕事は業務量が多いこともあり、それを頑張ってこなそうとするうちに、心身に負荷がかかってしまうこともあるでしょう。
また、介護の仕事をするうえで悩みや問題も発生しがちです。
例えば、次のようなものです。
- 人間関係の悩み
- 業務がうまく進まない悩み
- ご利用者様の課題をうまく解決できない悩み
上記のような問題や悩みを抱えていくうちに、心身に負荷がかかり、疲れ切ってしまうのです。
介護現場で問題意識を持つことは確かに大切ではありますが、悩みすぎてしまうと燃え尽き症候群を起こしてしまう可能性があるため注意しましょう。
燃え尽き症候群の症状4つ
燃え尽き症候群の症状は、主に4つあります。
ここからは、介護現場で燃え尽き症候群になってしまったときの症状4つを解説していきます。
- 生活に支障が出る
- 人と関わりたくなくなる
- やる気がでなくなる
- 感情のコントロールができなくなる
生活に支障が出る
燃え尽き症候群になると、日常生活にも支障が出始めます。
心や体が不調になり、これまでの生活が送りにくくなるためです。
例えば、次のような症状です。
- ご飯が食べられなくなる
- 夜眠れなくなる
燃え尽き症候群が原因で、食事や睡眠がとれなくなることがあります。
そうすると健康のバランスは乱れ、通常どおりの生活が送れなくなってしまうのです。
人と関わりたくなくなる
人と関わりたくなくなるのも、燃え尽き症候群の症状の一つです。
燃え尽きてしまうと、心が疲れてしまい、人との関わりが億劫になります。
例えば、次のような症状が出たら要注意です。
- ご利用者様との会話が面倒に思えてくる
- 以前なら泣いたり笑ったりする場面でも感情が沸かない
- ご家族との関わりに疲れる
- 職員と連携して働けなくなる
介護の仕事は、人との関わりが基本です。
本来はできていたはずのコミュニケーションが億劫になったり、できなくなったりしたときは燃え尽き症候群の症状が出ている可能性があります。
人との関わりに疲れたら、まずは心を休めるようにしましょう。
やる気がでなくなる
介護職員が燃え尽き症候群になると、やる気がでなくなることがあります。
なぜなら、介護の仕事に対し力を使い果たして燃え尽きてしまうと、疲れからやる気を失ってしまうからです。
例えば、仕事に対し、何もやりたくなくなったらそれは燃え尽き症候群かもしれません。
疲れたときにやる気がでなくなることは致し方のないことなので、自分を攻めすぎず、まずは休むようにしましょう。
感情のコントロールができなくなる
感情のコントロールができない場合も、燃え尽き症候群の可能性があります。
介護職員として燃え尽きると、心の疲れにより冷静でいられなくなってしまうからです。
例えば、次のような症状が出たら燃え尽き症候群かもしれません。
- 常にイライラする
- 無性に涙が出てくる
- 些細なことで激怒してしまう
燃え尽き症候群により疲労が溜まっている可能性がありますので、上記のような症状が出た場合は、一旦他者との距離を置くようにしましょう。
燃え尽き症候群を防ぐ方法
燃え尽き症候群を防ぐ方法は、主に3つです。
ここからは、介護職員の燃え尽き症候群を防ぐ方法を3つ解説していきます。
仕事との適度な距離感をもつ
介護職員の燃え尽き症候群を防ぐ方法の一つめは、仕事との適度な距離感をもつということです。
仕事に対し意欲的なのはいいことですが、行き過ぎると体も心も疲れてしまい、燃え尽き症候群を引き起こしやすくなります。
プライベートと仕事との時間をきっちりわけるなど、仕事に対して適切な距離感を持つことが大切です。
仕事から家に帰ったら、業務の悩みは一旦横に置いて、まずはプライベートな時間を楽しむようにしましょう。
仕事のことを忘れられるような、没頭できる趣味などをみつけるのも、おすすめです。
生活を整える
生活を整えることも、燃え尽き症候群予防に繋がります。
なぜなら、燃え尽き症候群は生活の乱れにより、悪化することがあるからです。
例えば、次のようなことがおすすめです。
- 夜はスマホから離れ、良質な睡眠をとるように意識する
- 食事は栄養価の高いものを優先に摂るようにし、バランスを意識する
- 適度に運動をする
生活を整えると、心身の状態も良好になり、燃え尽き症候群が発生しにくくなります。
悶々としていて燃え尽き症候群になってしまう恐れがあると感じている人は、まず生活を整えることから始めてみてください。
ときどき自分と会話する
介護職員の燃え尽き症候群を予防する方法として、ときどき自分と会話してみるのもおすすめです。
なぜなら、自分と会話することで感情を理解し、客観視できるようになるからです。
例えば、ノートに自分の感情や想いを綴り、それに対して「自分が言ってほしい言葉」を付け加えてみると効果的と言われています。
悩んだときには自分と会話するように気持ちを整理していくことで、燃え尽き症候群を防ぐことができるようになります。
燃え尽き症候群になってしまったときの対処法
介護職員として働いているうちに燃え尽き症候群になってしまった場合、どうしたらよいのでしょうか。
ここからは、燃え尽き症候群になってしまったときの治療方法を解説していきます。
1:今の状況・状態を理解する
まずは、今の状況や自分の状態を理解することが大切です。
難しいかもしれませんが、今大切なのは自分の心の状態を客観視するということです。
「やる気が出ず、何もしたくない」と思ったら、心や体が疲れているサインであるということに気づきましょう。
状況や状態の整理が難しければ、紙に箇条書きに書き出してみることがおすすめです。
今の自分の状態や想いを、簡単に紙に書き出し、眺めてみると客観視できるようになります。
2:視野が広がるようにルーティンから外れてみる
燃え尽き症候群になる原因の一つが、視野の狭さです。
「〇〇すべき」の固定観念に縛られて、自分で追い詰めてしまうということもあります。
そういった思考は、余計に自分を苦しめてしまいますので、まずはそこから離れるようにしましょう。
また、いつもとは違う行動をしてみるのもおすすめです。
例えば、食器洗いの順番を変えてみたり、掃除の仕方を変更してみたりすることです。
業務に差支えのない範囲で、いつものルーティンから外れることで、視野が広がることがあります。
燃え尽き症候群の症状を感じたら、ルーティンから外れたちょっとした行動を実践してみるようにしましょう。
3:焦らず回復を待つ
燃え尽き症候群の症状を感じたら、焦らず回復を待つことも大切です。
なぜなら、時間が解決してくれることもあるからです。
焦って解決させようとしてしまうと、余計に感情が乱れ、症状が悪化してしまう可能性があります。
焦らず自分を信じ、回復を待つようにしましょう。
介護職員の燃え尽き症候群を予防した体験談
筆者も介護職員として燃え尽き症候群になりかけて、それを予防した体験がありますので、紹介します。
筆者が介護職員として働き始めて5年目の頃です。
特別養護老人ホームでユニットリーダーを任されることになり、周囲の期待に応えたいという気持ちが高まっていました。その気持ちが強くなるあまり、さまざまなことを取り入れてみました。
ユニット内の目標を立て、それに向けて実行していくのですが、なかなかうまくいかない日々。
周囲にもその想いを理解してもらえず、自分一人で頑張っているような気になっていました。
そんな日々が続き、疲れてしまった筆者は、仕事中常にイライラしてしまうようになったのです。
これは「燃え尽き症候群かもしれない」と感じた筆者は、一旦仕事との距離感を冷静にみるようにしました。
すると、四六時中仕事のことばかり考えていた自分に気づきました。
それからは、仕事とプライベートを切り分けるようになり、なんとか燃え尽き症候群を回避することができたのです。
そのとき、自分一人で頭でっかちになり、頑張った気で業務量を増やすだけでは、よい介護ケアには繋がらないどころか自分の心身も壊してしまうということに気づきました。
仕事には適度な距離感があると思います。
適度な距離感を持ちながら、自分にできる範囲のことを実践していくことが大切なのだと感じました。
まとめ
介護の仕事は燃え尽き症候群の症状を引き起こしやすいとも言われています。
しかし、適切な距離感を持つことで、燃え尽き症候群を防ぐことができます。
本記事内の方法を参考に、燃え尽き症候群を防ぎ、前向きに仕事ができるような環境を整えていきましょう。
この記事を書いたのは・・・

中村 亜美/Webライター
保有資格:介護福祉士
特別養護老人ホームでユニットリーダーとして11年程勤務。
その後はフリーライターとして活動中。在宅介護者や介護事業者、介護職員向けのコラム・取材記事を執筆している。