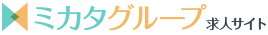介護職員で「妊娠をしたかもしれないけど先のことが不安」と思っている方もいるかもしれません。
妊娠は喜ばしいことであるはずなのに、不安ばかり取りつかれてしまえば、気持ちが不安定になり仕事へのモチベーションも下がってしまう可能性があります。
本記事では、介護職員で妊娠をしたら仕事を続けられるのかの疑問にお答えし、報告手順や注意点などを解説していきます。
また、実際に介護職員として二度の妊娠中勤務を経験した筆者のお話しも紹介していきます。
記事を読めば、妊娠後や出産後の仕事の仕方がわかり、安心して働き続けることができるでしょう。
この記事の内容
介護職員が妊娠したら、仕事を続けられる?
介護職員が妊娠したら、介護職を続けられるのでしょうか。
ここからは、その答えとその後の働き方について解説していきます。
結論:続けられる
介護職員が妊娠しても、仕事は続けることができます。
なぜなら、職員が妊娠中でも仕事を続けたいことを希望した場合、職場はそれを拒否できないことが法律で決まっているからです。
厚生労働省「働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定について」では、女性労働者の妊娠中や産前産後休暇の扱いについて、次のように記載しています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
事業主は、女性労働者が妊娠・出産・産前産後休業の取得、妊娠中の時差通勤など男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や深夜業免除など労働基準法による母性保護措置を受けたことなどを理由として、解雇その他不利益取扱いをしてはなりません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用:厚生労働省「働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定について」
ただし、安全で健康な体を維持するため、妊娠中の働き方については注意が必要です。
妊娠中の働き方や注意点については、記事内でさらに詳しく紹介していきます。
妊娠中の働き方
妊娠中であっても、介護職員として担当する仕事は基本的には同じです。
ここからは、妊娠中に行う業務と避けるべき業務をそれぞれ紹介していきます。
妊娠中行う業務
妊娠中は多くの場合、比較的体に負担のない業務を担当します。
具体的な業務例は、次のとおりです。
- 食事介助
- 配膳、下膳
- 排泄介助
- 整容介助
- 掃除や片付け
- 洗濯等
ご利用者様のタイムスケジュール上で、妊娠中でも比較的安心してできる業務を任されるでしょう。
職場によっては、上記の他にレクリエーションなどの仕事が入ることもあります。
妊娠中避けるべき業務
妊娠中は、体に負担がかかったり、危険度が高かったりする業務は避けるべきです。
特に、転倒の危険がある入浴介助や体に負担がかかりやすい移乗介助は可能な限り行わないようにしましょう。
また、これまでフルタイムで働いていた場合、一人で対応する時間があるような早番・遅番・夜勤の仕事は避け、日勤帯での勤務に移行されることも多いです。
妊娠しても介護職員として仕事を継続する場合の働き方は、職場によって若干異なるため、気になる方は事前に確認しておきましょう。
出産後の働き方
出産後8週間は労働基準法により就業できないことになっていますが、それ以降で医師が問題ないと判断した場合、本人が望めば就業できることになっています。
ただし、出産後は約1年ほど育児休暇をとった後で、復帰することが多いです。
また、復帰後は育児の時間が必要なことから、時短制度を利用して短時間勤務を選択する人もいます。
筆者の場合は、第一子のときに10か月、第二子のときに1年で復帰し、時短制度を利用しながら、9時から16時までの短時間勤務をしていました。
仕事内容は妊娠前と変わらず、入浴介助や移乗介助も含む全ての業務を担当していました。
時短制度は職場によって期間が異なりますが、復帰後からスタートし、3歳から小学校卒業頃まで取得できるのが一般的です。
妊娠した?と思ったらどのように報告すべきかを解説!
介護職員として働いていて、妊娠の予感を抱くことがあるかもしれません。
そんなときには焦ってしまうものですが、できるだけ冷静に必要なステップを踏んで、必要な報告をしていきたいところです。
ここからは、介護職員が「妊娠した?」と思ったら実施すべき手順を3つ解説していきます。
まずは病院受診をする
まず、妊娠の兆候を感じたら、早めに病院受診をしましょう。
今後の動きを決めるうえで、現時点での状況を確認する必要があるからです。
病院受診は、最寄りの産婦人科等がよいでしょう。
今後通う可能性も考えたうえで、近くて雰囲気のよい病院を選ぶとよいかもしれません。
不安な場合は、距離や病院の口コミなどを事前に確認しておくことがおすすめです。
上司へ報告する
病院受診で妊娠が発覚したら、次は上司に報告します。
心配になり報告をためらうこともあるかもしれませんが、上司にはなるべく早めに報告することをおすすめします。
なぜなら、事前に知らせておけば急な体調不良の際にもフォローしてもらえるからです。
また、上司にとっても今後の人員配置を考えるうえで、なるべく早く把握しておきたい可能性が高いからです。ただし、異性の上司である場合、妊娠が言いにくいということもあるでしょう。
そういった場合は、信頼できる同僚やリーダー、また場合によっては管理者に相談してみるのもおすすめです。医師に言われたことや現在の体調などを報告も一緒にするようにしましょう。
同僚への報告時期を上司と相談する
今後の体調が心配で、早々に同僚に報告することを躊躇ってしまうという方もいるでしょう。
そういった場合は、上司に相談しても問題ありません。
実際に筆者の前職にも、「同僚には落ち着いた頃に報告した」という人が複数人いました。
ただし、体に負担がかかる入浴介助などは避けてもらう必要があります。
「どうしても同僚にまだ言いたくない」という場合は、同僚に報告したい時期をあらかじめ上司に考えておき、うまく協力してもらうようにしましょう。
介護職員が妊娠して仕事を続ける際の注意点
妊娠したあとも、介護職員として仕事を続けたいという方もいるでしょう。妊娠後、安全に仕事を続けるためには、いくつか注意すべき点があります。
ここからは、その注意点を3つ解説していきます。
体調が安定しないときには、早めに相談する
体調が安定しないときには、無理せず早めに相談しましょう。
体調が優れない状態で無理に仕事を続けてしまうと、悪化したり、回復が遅れたりする可能性があるためです。
例えば、「つわりが辛い」「最近お腹が張っている気がして心配」と思う場合には、医師とも相談したうえで上司にその旨を報告しましょう。
厚生労働省「働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定について」では、妊娠中の配慮義務について以下のように記載をしています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
妊娠中及び出産後の女性労働者が、健康診査等を受け、医師等から指導を受けた場合は、その女性労働者が受けた指導を守ることができるようにするために、事業主は勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければなりません。
※ 指導事項を守ることができるようにするための措置
○ 妊娠中の通勤緩和(時差通勤、勤務時間の短縮等の措置)
○ 妊娠中の休憩に関する措置(休憩時間の延長、休憩回数の増加等の措置)
○ 妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置(作業の制限、休業等の措置)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
つまり、妊娠中の体調不良により、医師から配慮するよう指示があった場合には、職場はそれに従う必要があるということです。
体調が優れない場合には、遠慮することなく医師・上司に相談するようにしましょう。
避けるべき業務を引き受けない
妊娠中は避けるべき業務がありますが、上司や同僚にお願いされても引き受けないようにしましょう。
同僚や上司は、それが「妊娠中に行うべき業務ではない」ということをわかっておらず、お願いしている可能性もあるからです。
そのため、あなたが引き受けてしまうと「お願いしてよいもの」として認識されてしまいます。
体に負担がかかる業務は断るようにして、何度もお願いされる場合は上司や管理者に相談することをおすすめします。
周期に応じて体調観察をする
妊娠中は、周期に応じて体調観察をしましょう。
周期によるよくある症状や注意点について、次の表にまとめました。
| 周期 | よくある症状 | 注意点 |
| 妊娠初期(~15周期) | つわり、頻尿 | 流産リスクが高い時期と言われています。重たいものを持ったり、走ったりする行為は可能な限り避けましょう。 |
| 妊娠中期(16~27周期) | 腰痛、貧血 | 安定期と呼ばれていますが、早産・流産リスクが全くないわけではありません。無理せず体調を休めながら仕事をしていきましょう。 |
| 妊娠後期(28周期~) | お腹の張り、睡眠不足 | お腹が大きくなる時期です。普段よりも動きにくくなるため、転倒などには特に気を付けましょう。 |
参照:働く女性の健康支援事業「妊娠初期から産後まで 母体の変化と仕事への影響」
妊娠中、安定期と呼ばれる時期もありますが、基本的にはどの周期にも油断は禁物です。
症状を鑑みながら、無理のない範囲で仕事を進めていきましょう。
介護職員が妊娠・出産時に利用できる制度
介護職員が妊娠・出産時に利用できる制度は、いくつかあります。
ここからは、利用できる制度を3つ紹介していきます。
産休・育児休暇制度
出産後は、産休・育児休暇制度を利用できます。
厚生労働省「育児休業制度特設サイト」では、産休・育児休暇制度について以下のように説明しています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
育児休業とは、原則1歳未満のこどもを養育するための休業で、育児・介護休業法という法律に定められています。
育児休業の申出は、それにより一定期間労働者の労務提供義務を消滅させる意思表示です。
もし、お勤め先の就業規則に育児休業に関する規定がなくても、
法律に基づき育児休業を取得することができ、会社側は休業の申し出を拒めません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
記載されているとおり、出産と育児をするための休暇制度であり、介護職員が希望すればそれを職場は受理する義務があります。
多くの場合、出産予定日の6週間前から子供が1歳になる頃まで、この休暇を取得します。
育児休業給付金
出産後、育児休業給付金を利用できます。
厚生労働省「育児休業等給付について」では、育児休業給付金について次のように記載しています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
原則1歳(注)未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
育児のために休業している期間も、給付を受けられる制度です。
給付の金額については、条件により異なるため、気になる場合は職場の総務課に質問してみるとよいかもしれません。
その他、職場による手当・お祝い金等
その他、職場により、福利厚生としてさまざまな手当やお祝い金が用意されていることがあります。
職場で用意されている場合は、条件を満たせばそれを利用することができるでしょう。
例えば、次のような福利厚生があります。
- 出産お祝い金
- 子育て手当
- 保育料援助
- 家族手当
独自の福利厚生は、職場によって異なるため、気になる人は事前に聞いてみるとよいでしょう。
【体験談】妊娠時期でつらい時期の乗り越え方
筆者も介護職員時代に二度、妊娠中から産休に入るまでの間、仕事をしていました。
つわりやお腹の張りなどを経験し、妊娠中に仕事を続けることの難しさを痛感しました。
また、精神的にも不安定になりやすく、同僚やご利用者様に少しでも嫌な顔をされると傷ついて落ち込んでしまっていたことを思い出します。
妊娠中は心身のバランスが崩れやすく、ネガティブな思考に陥ってしまう人もいるかと思います。
筆者は、適度に家で休憩し、夫に話を聞いてもらうことで、前向きな気持ちを取り戻していました。
人によってリフレッシュの仕方はそれぞれですが、適度に休息する時間は大切です。
無理をしすぎず、体を第一に、二の次に仕事というような気持ちで仕事と向き合ってもよいかもしれません。
まとめ
介護職員が妊娠した場合、仕事を続けることはできますが、働き方には注意が必要です。
体調を鑑みながら無理のない範囲で仕事をしていきましょう。
業務のことで心配がある場合は、上司や管理者に相談してみるのもよいかもしれません。
妊娠や出産、育児は、大きなライフイベントになります。
安心して乗り越えられるように、必要な事前準備をしっかりとしておくことがおすすめです。
この記事を書いたのは・・・

中村 亜美/Webライター
保有資格:介護福祉士
特別養護老人ホームでユニットリーダーとして11年程勤務。
その後はフリーライターとして活動中。在宅介護者や介護事業者、介護職員向けのコラム・取材記事を執筆している。