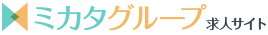「介護記録を書くのが苦手」
「介護記録は何を書いたら良いかわからない」
「そもそも介護記録って何のためにあるの?」
このように思ったことはありませんか?
介護職員になると、介護記録を記載しなければいけない場面が必ず訪れます。
介護記録を負担に思ったり、毎日後回しになって時間外に記載していたり、文章を書くことが苦手と思っている介護職員には、気が重い業務ですよね。
本記事では、施設ケアマネジャーとして職員に介護記録の研修をしてきた筆者が、介護記録の記載方法に不安がある方向けに介護記録の基本からわかりやすく解説します。
ぜひ、参考にしてください。
この記事の内容
介護記録とは
介護記録とは、ご利用者様の日常の様子や提供したサービス内容など、くわしい対応を記した書類のことです。
介護保険制度では、介護サービスの提供記録の作成が義務づけられています。
以前は紙の介護記録が主流でしたが、現在は、パソコンやタブレットなどで介護記録を記載する電子カルテを導入し、記録時間の短縮をしている事業所も多くなっています。
正確な介護記録が書けるように、以下でくわしく解説します。
介護記録の基本の書き方
介護記録を書くには、基本的なルールを理解しておく必要があります。
以下、5つのルールについて説明します。
- 語尾は「である・だ」調にする
- 記載が必要な事柄を把握する
- 専門用語や略語は使わない
- 客観的な事実を書く
- 正しい日本語で書く
ひとつずつみていきましょう。
語尾は「~である・~だ」調にする
介護記録の文章は、「~である・~だ」調の「常体」に統一して記載しましょう。
介護記録は、法的に重要な役割を持つものなので、説得力や信頼性を与える常体を使用するのが通例です。
以下、例文を用いて解説します。
【NG例文】
ナースコールで呼ばれたので、訪室しました。ご本人様より「トイレに連れてって」と言われたので、トイレまで誘導をすると、自己にて排泄されました。
【OK例文】
ナースコールにより訪室する。ご本人様より「トイレに連れてって」と訴えあり。トイレ誘導すると、自己にて排泄される。
NG例文とOK例文を比較した場合、OK例文の方が明確で、起きた事象を断定的に伝えることができています。
介護記録は、公的に利用できる文書であるため、記載者がわかりやすく物事のありさまを伝える表現である「常体」が望ましいとされています。
また、物事のありさまを具体的に伝える方法として、会話は「」を使用し、そのときの口調通りに記載するとご利用者様の様子がわかりやすくなります。
記載が必要な事柄を把握する
介護記録に記載しなければいけない事柄は、事前に理解しておくと漏れなく記載ができます。
以下は、最低限介護記録に記載しなくてはいけない事柄です。
- 日時
- 記載者名
- ケアプランに位置づけられている事柄
- 緊急時の様子や職員の対応
- 事故報告書が提出される事柄
順番に説明します。
日時
介護記録の冒頭に必ず書くのが、日時です。
日時を記載する際、新人職員からよく質問をされるのは、発生時の時間を記載するのか、それとも記載した時間を書くのかです。
結論からいうと、発生した日時を記載します。
理由は、ご利用者様にサービス提供をした際、迅速かつ適切に対応をしたことをリアルタイムで記載した方が信頼性が獲得されやすいからです。
例えば、14:00にご利用者様が体調不良を訴えたことを記載する場合、訴えられた時間を記載する方が、スピーディーな対応をしたことの証明になります。
14:00に体調不良の対応をしたが、記載したのは16:00だった時に16:00と書いてしまうと、2時間もタイムラグが生まれ、迅速な対応をしたことを伝えられません。
ご利用者様にサービス提供した後、介護記録はすぐに記載するのが望ましいということを覚えておくといいでしょう。
記載者名
介護記録には、記載した職員の氏名を必ず書いてください。
直筆で書いても捺印を押してもどちらでもよいですが、誰が書いた記録かわかるようにすることで、その後の対応や説明が必要な場合に段取りよく動けます。
ケアプランに位置づけられている事柄
前述でも紹介したように、介護記録は介護サービス提供の書類です。
ケアプランに基づいて介護サービスを提供していることの証明が必要であるため、ケアプランに位置づけられている事柄は必ず記載する必要があります。
例として、ケアマネジャーが作成したケアプランの内容から、どのように介護記録を書いたらいいか、わかりやすく解説します。
| 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 | 頻度 | 期間 | ||
| 楽しく充実した生活が送れる | 他のご利用者様と会話など交流をし、友人が作れる | レクリエーションに参加を促す | 毎日 | 2025/1/1 ~ 2025/3/31 | ||
上記のようなケアプランの場合、まずはサービス内容と頻度に注目します。
このケアプランの場合、提供しなければいけないサービス内容は、レクリエーションに参加して頂くように毎日声かけをすることだとわかります。
では、これを実施した後、どのように記載すればよいでしょうか。
| 日時 | 対応 | 記載者 | ||
| 1月20日 14:00 | 訪室し、「風船バレーがはじまりますので参加しませんか?」とレクリエーションの声かけをする。 「はい、行きます」といつもと同じようにフロアへ出てこられる。 隣に座ったご利用者様と「今日も寒いね。」と言葉を交わされ、風船バレーを一緒に楽しまれる。 両腕を使い、よく動かれ体調良好の様子。 | 〇〇 | ||
ケアマネジャーが立てた目標は、「ご利用者様がレクリエーションを実施することによって、他のご利用者様と交流ができ友人を作ることができる」ことです。その目標に沿った介護記録になっているかどうかが記載する際のポイントになります。
ケアプランに沿ったサービス内容を提供していることがわかるような記載をし、さらにケアマネジャーがケアプランを継続するか変更するかの判断ができるように様子を含めて記載することを徹底しましょう。
これに加えて、頻度が「毎日」となっているので、上記のようなレクリエーションについての介護記録は毎日記載する必要があります。
ケアプランに基づいた介護記録を完璧に記載するのは負担が大きいですが、〇×のような記号で表せる要約表などを活用して、ケアプランを網羅できるよう工夫することをおすすめします。
緊急時の様子や職員の対応
緊急時については、介護職員や看護職員など関わった職員が必ず記載するべき事柄です。
緊急時の対応を記載した介護記録は、ご家族様への説明、受診病院の医師への説明、さらには法的な役割など非常に大切な内容になります。
【例文】
2:00 巡視
巡視時、呼吸をしていない〇〇さんを発見する。
頸動脈ふれず、声かけに反応なし。
2階フロアの介護職員△△を内線で呼び、応援を依頼する。
2:05 心肺蘇生開始
2階フロアの介護職員△△に心肺蘇生を変わってもらい、救急連絡をする。
心臓マッサージを継続するも、〇〇さんの反応なし。
2:15 救急隊到着、心臓マッサージ交代する。
□□病院に搬送される。
対応した職員は、時系列で誰がどのように対応したか、ご利用者様のご家族へは誰がいつ報告したかなど、くわしく記載するようにしてください。
緊急時の対応方法も事前にチェックを
緊急時の介護記録は「緊急時に適切な対応ができた」という証明としても残す意味があります。
なぜなら、緊急時の対応によっては、訴訟などのトラブルに発展してしまうリスクがあるからです。
例えば、緊急時に適切に対応できず、ご利用者様の病状が悪化してしまった場合、ご家族から訴えられる可能性もあるでしょう。
そういったリスクを避けるためにも、適切な介護記録を残すことはもちろん大切ですが、前提として緊急時の対応が適切である必要があります。
しかし、いざご利用者様の急変時に立ち会うと、職員も人間なので動揺してしまい適切な対応方法がわからなくなってしまうこともあるでしょう。
そういった事態に陥らないためには、事前に緊急時の対応を把握しておくことが重要なポイントになります。
緊急時の対応に不安がある方は、ぜひこちらの記事をご覧ください。
事故報告書が提出される事柄
事業所内で起こった事故などの記載も必ず必要です。
上記の緊急時の記載と同様に、職員の対応や、ご家族様への報告などのため、日時から細かく記載するようにしてください。
また注意点としては、別紙で提出される事故報告書の内容と介護記録が合致するようにしましょう。
介護記録と事故報告書の内容が異なっていると、報告書としての信憑性が薄まってしまうからです。
同じ文章を2回記載するのは負担なので、筆者の施設では、介護記録には軽く事故概要を記載したうえで「事故報告書参照」とし、事故報告書の写しを添付してもらっていました。
施設ごとの記載の仕方を確認してみましょう。
事故報告書を記載する際のポイントについては、こちらの記事でくわしく紹介しています。あわせてご覧ください。
専門用語や略語は使わない
介護記録は、専門用語や業界用語のような略語は使用せず記載します。
理由は、読む人が事業所内の人だけではないからです。
以下のような場合、ご利用者様の家族や連携している他の事業所の人などに提示する場面があります。
- 転倒事故などでくわしい状況を開示する時
- 遠方から来られるご家族様が、ご利用者様の日常生活の様子を知りたい時
- 運営指導や監査などで、介護記録の内容を精査される時
このような場合に、介護記録に専門用語や略語が記載されていると、内容の理解ができず誤って認識されてしまう心配があります。
また、読みづらい文章だと、ご利用者様の様子がわかりにくくなってしまいます。
介護記録は、誰が読んでも状況が明確にわかる文章を書くのが望ましいです。
客観的な事実を書く
介護記録は、客観的な事実を正確に書きましょう。
客観的な表現とは、ご利用者様の言動や、職員の対応をありのまま文章にすることを指します。
よくある例としては、転倒などの事故があった場合の介護記録の書き方です。
事故報告については、状況や対応を介護記録に正確に残す必要があります。
【OK例文】
〇時〇分、居室内の床にあおむけで倒れているご利用者様を発見する。
「大丈夫ですか?どうされましたか?」と声をかける。「ベッドから落ちてしまった」と返答あり。痛みはあるかと伺うも首を横に振られる。その他特に痛み傷なし。
介護記録を読んだ人が、同じシチュエーションをイメージでき、情報の共有が図れるような文章にしましょう。
正しい日本語で書く
介護記録は、誰がみても伝わるように正しい日本語で書くように努めましょう。
きれいな字で書くのはもちろん、分からない漢字はひらがなにするのではなく、できる限り調べて漢字を使用してください。
業務に追われて忙しい中、慌てて介護記録を書く場合も多いかと思います。
ですが、読む人のことを思って相手に伝わる文章を書くようにすると、よりよい介護記録になります。
介護記録が必要な3つの理由
介護記録には、さまざまな役割がありますが、その中でも3つの必要性について紹介します。
- ご利用者様の日々の生活の情報共有のため
- ケアプランに沿って介護をしている証明のため
- 有事の際の証拠としての役割のため
どれも介護現場において介護記録を必要とする大切な事柄ですので、ぜひ一読ください。
ご利用者様の日々の生活の情報共有ため
ご利用者様の日々の生活を記録することは、職員間での大切な情報になります。
介護現場では、シフト制であるため職員の入れ替わりが多くあり、顔を合わせて申し送りができない職員がたくさんいます。
そんな時に必要なのが、介護記録でご利用者様の様子を把握することです。
- 食事量に変化はないか
- レクリエーションにはどのくらい参加しているのか
- 他のご利用者様との交流はあるのか
携わる職員がそれぞれ丁寧に介護記録に記載し、日々こつこつと書き留めることで、ご利用者様の日常生活の移り変わりがよくわかってきます。
職員は介護記録を上手く活用し、ご利用者様の生活をよく見定め、変化に対応し介護の質を向上しましょう。
ケアプランに沿って介護をしている証明のため
介護記録は、大前提としてケアプランの内容に沿った介護をしているか確認するためのものでもあります。
前述でも紹介しているように、介護記録はケアプランに沿って記載することが重要です。
ケアプランに沿った内容を記載することで、サービス提供をしている証明になるからです。
筆者が職員に介護記録の研修をしていた時には、介護記録はサービス提供をした証明であって、その証明がされるから介護報酬を受けることができ、介護職員の給料に反映されると伝えていました。
介護職員の中には、記録物は「苦手」「時間外になってしまう」などネガティブなイメージを持っている人もいたり、なぜ介護記録を書かなければいけないのか知らない人もいます。
そういった介護職員に向けて介護記録を記載する意味を伝え、必要性を伝えるのに努めていました。
有事の際の証拠としての役割のため
介護記録は、有事の際に職員が迅速かつ適切に対応をしたという証拠になる大切な役割を持ちます。
万が一、ご家族様から職員の対応について信頼性を欠いた場合に、事業所としての対応を証明することができるものなので、日頃から介護記録は丁寧に記載するクセをつけておくようにしましょう。
そうすれば、いざというときに慌てずに済みます。
【シーン別】介護記録の記載例
本章では、シーン別の介護記録の記載例を紹介します。
今回は、以下の5つのシーンについて具体的な良い例と悪い例を比較し、解説します。
- シーン① 食事の記録
- シーン② 排泄の記録
- シーン③ 入浴の記録
- シーン④ レクリエーションの記録
- シーン⑤ 体調不良時の記録
シーン① 食事の記録
食事についての記録は、食事や水分の摂取量などについて毎日必ず記載する必要があります。
ですが、大切なのは摂取量の数字ではなく、摂取時のご利用者様の様子です。
【NG例】
12:00 昼食を食べられる。主食10割、副食10割で摂取良好。
悪い例は、客観的事実が書かれていますが、これだけでは、ご利用者様の食事時の様子がイメージできません。
【OK例①】
12:00
昼食を配膳すると笑顔で「ありがとう」と言われ、献立を確認される。
隣のご利用者様と時折「おいしいね。」と会話をしながら、食べ進められる。
主食10割、副食10割。食事中むせなく、摂取良好。
【OK例②】
12:00
昼食を配膳すると笑顔で「ありがとう」と言われ、献立を確認される。
隣のご利用者様と時折「おいしいね。」と会話をしながら食べ進められる。
このように、ご利用者様の食事時の様子がイメージできるようなことを記載していきましょう。
筆者が指導していた施設では、摂取量は別に用意された摂取表に記載をし、介護記録には残さないように伝えていました。勤務している施設により書き方は異なるため、施設ごとの書き方を確認しましょう。
シーン② 排泄の記録
排泄についての記録は、食事と同様に数字や記号で記載が可能です。
そのため、別紙に排泄の回数や量などの記載をしても良いでしょう。
【NG例】
11:00 トイレ誘導をする。排尿を確認する。
上記のような記載だと、次にトイレ誘導をする職員はどのような身体状況でどういった介助が必要なのか伝わりません。
【OK例】
11:00
トイレ誘導の声掛けをすると、「今は行きたくないけど、一応行っておくか」と言われトイレに向かわれる。立位保持良好。自己にて下衣の着脱をされるため、見守る。普通尿中等量みとめる。
このように、トイレ誘導時には、職員はどういった介助をしたのか記載するとその後に続く職員への情報提供になります。
シーン③ 入浴の記録
入浴についての記録は、介助後すぐに記載することが難しいため、何か気になることや普段とは違うことがあれば、業務の合間にメモをしておくことをおすすめします。
入浴前にはバイタルサインの測定をして体調の確認をおこない、記録に記載しておきましょう。
【NG例】
10:00
入浴のため浴室に誘導する。入浴拒否をされたため、少し時間をあけてから再度声かけをする。
入浴については、ご利用者様によって拒否的言動を取る方もいらっしゃいます。
また、認知症状によって入浴する理由が理解できず、「入りたくない」とご立腹される場合もあります。
この場合は、気持ちよく入浴できるようにご利用者様を誘導するアイデアが必要になります。
職員間での情報共有として「〇〇を試したけど、本日は上手くいかなかった」や「今日上手くいった」などを介護記録として書き留めておけば、ご利用者様に入浴して頂く手順書が作成できます。
【OK例①】
10:00
訪室し、「〇〇さん、今日は一番風呂で気持ちよく入れますので一緒に浴室まで行きませんか?」というと、「一番風呂か、たまにはいいな」と拒否みられず。浴室までスムーズに誘導する。
【OK例②】
10:00
訪室し、「〇〇さん、お風呂の時間です。私がお連れしますので一緒に行きませんか?」と声かけをする。「私はひとりで入りたいんだ、今日は入らん」と言われ誘導できず。
入浴に拒否があるご利用者様については、日々試行錯誤しながら介護のアイデアを探す必要があります。
介護記録は、各職員のアイデアを集計させ適切なサービス提供のために、有効に活用できます。
シーン④ レクリエーションの記録
レクリエーションについての記録は、ご利用者様の様子やシチュエーションがわかりやすいよう、文章に反映しましょう。
レクリエーションの実施の際には、ご利用者様がみんな同じ様子であることはありません。
他のご利用者様と仲良く参加される人、遠くから全体を見渡すように様子をみられている人、実施している職員に対しコミュニケーションをとってくれる人などがいます。
レクリエーションの介護記録は、ご利用者様それぞれに個性あふれる介護記録になる事柄なので、実施中の様子や会話をしっかりと記載すると良いでしょう。
【NG例】
14:00
レクリエーションに参加される。風船バレーを他のご利用者様と楽しまれる。
上記にあるような文章では、状況がつかめずご利用者様が本当に楽しんだのか、わかりづらいです。
【OK例】
14:00
時間になると、ご自身でフロアに出てこられレクリエーションに参加される。隣の席の〇〇さんと一緒に、「今日は同じチームだね。」と笑顔で話しながら風船バレーを楽しまれる。上半身を使い、積極的に風船を追いかけられる。
レクリエーションは、職員がそれぞれのご利用者様を観察し、介護記録に落とし込むと、ご家族様が来られた際にも、情報提供の材料になります。
テンプレートのようになってしまいがちなレクリエーションや余暇活動の様子だからこそ、ご利用者様それぞれの様子をしっかりと記載しましょう。
シーン⑤ 体調不良時の記録
体調不良時の記録については、必ず記載が必要です。
では、よくある発熱時の記録を例に説明します。
体調不良時の記録は、時間や対応に正確性が必要です。
理由は、介護記録の内容をみて、体調不良になった経過を説明する場面が多いからです。
【NG例】
7:00
起床介助のため、訪室し声かけをする。返答がなく、顔面紅潮を確認する。
体温38.6度、脈90、血圧156/90、SPO₂96% 看護師へ報告する。
上記の例は、一見事実を記載しており、必要な情報もあるようにみえます。
ですが、体調不良時には、もう少しご利用者様の様子を忠実に表現する必要があります。
【OK例】
7:00
起床介助のため、訪室し「おはようございます。」と言うと、返答がない。顔素みると頬が赤くなっており息苦しそうな様子。バイタルチェックをおこなう。
体温38.6度、脈90、血圧156/90、血中酸素濃度96%
頭部クーリングをおこない、そのまま寝てもらう。この旨、看護職員に報告する。
特に起床介助は、夜勤明けの職員が対応することが多いです。
そのため、自分の対応が正確なものであったかや、初動の対応で行ったことなどが職員間で伝わりやすい文章にしましょう。
日勤帯に入り、外部受診にお連れする場合のことも考え、必要事項は漏れなく記載することが重要です。
こういった場合に記載漏れがあったり、文章の分かりづらさから誤った情報となってしまった場合は、対応がスムーズにいかなかったり、夜勤明けで帰宅した後に職場から確認の連絡が入ることも十分に考えられます。
そのためにも、有事の際の介護記録は漏れなく正確な情報を記載しましょう。
わかりやすい介護記録を書く3つのコツ
わかりやすい介護記録はどう書けばいいのか、以下3つのコツを紹介します。
- 会話内容を入れる
- 時系列で整理して書く
- 日常会話を聞き逃さない
この3つのコツを実践すれば、ご利用者様それぞれの生活が手に取るようにわかり、情報あふれる介護記録が書けますので、参考にしてください。
会話内容を入れる
介護記録に何を書いていいかわからない時は、ご利用者様と直接会話をした内容を記載するのをおすすめします。
介護職員は業務に追われていて、大切な業務であるはずの介護記録の記載が面倒と考える職員も多くいます。
そのため、以下のようなご利用者様全員に当てはまるようなテンプレートを繰り返し使いがちです。
- 〇〇のため、訪室する。
- レクリエーションを楽しまれる。
- おいしそうに食事をされる。
客観的な事実を書くことも大切ですが、あわせて大切なことはご利用者様にはそれぞれの生活があって個性豊かなので、介護記録にもその個性を反映させることです。
テンプレートのようなお決まりの文言ではなく、その場その場でご利用者様と会話をし、それをそのまま「」を使用して記載すれば、介護記録に個性がでます。
時系列で整理して書く
介護記録は、時系列で整理して記載するようにしましょう。
介護記録は、その事象が起こってから記載するものなので、基本的には過去形で記載します。
ただ、現在も続いている場合には、現在進行形で記載しても良いです。
例えば、腰痛が続いている場合、「湿布貼付するも、腰痛は継続されている。」というように記載します。
時系列で整理して書くことは、他の職員が把握しやすくするためでもあります。
誰が目を通しても、事の成り行きがわかりやすいように記載してください。
日常会話を聞き逃さない
介護記録を書くときのポイントは、ご利用者様の日常会話を聞き逃さず、ストックしておくことです。
介護記録は、勤務帯によって記載担当が決められていることが多いです。
記載担当になる日は、日中にご利用者様と会話をしたり、会話しているのを聞いて内容を覚えておき、日常会話として介護記録に記載するとよいです。
職員に声を掛けた言葉や、他のご利用者様と話している会話など遠くからでもいいので観察し、介護記録に記載していると、ご利用者様の言葉数が少なくなってきたり、会話の内容に違和感があるなど早い段階で変化を見つけられます。
介護記録についてのよくある質問
施設ケアマネジャーとして介護職員に介護記録の研修をしていた経験もある筆者が、介護記録についての質問に回答します。
毎日変化のないケアでも、その都度介護記録を書かなければいけないのか?
ケアプランに位置づけられている内容で毎日実施になっているものは、記載の必要があります。
ただし、記号で済むような内容であれば、要約表として〇×△や数字などを活用し、記載の負担を減らすのもいいでしょう。
【要約表の例】
| 1日(日) | 2日(月) | 3日(火) | 4日(水) | 5日(木) | ||
| 食事摂取量(朝) | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | |
| (昼) | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | |
| (夜) | 7/10 | 6/10 | 5/10 | 7/10 | 10/10 | |
| 排尿回数 | 9回 | 10回 | 8回 | 8回 | 7回 | |
| 排便回数(状態) | 2回(◎) | 2回(◎) | 1回(◎) | 1回(〇) | 1回(〇) | |
| 【ケアプラン内容】 | ||||||
| #1-1 レクリエーション | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × | |
| #2-1 個別リハビリ | 〇 | 〇 | ||||
| #3-1 入浴 | 〇 | 拒否 | ||||
| #1-1 花の水やり | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| #1-3 洗濯物たたみ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
要約できる介護記録で、記載量を減らしながらよりよいご利用者様の介護記録が作れるような工夫があると良いでしょう。
施設によって、体温表・チェック表・要約表など呼び名や書類の形式はさまざまです。
介護記録はまとめて書いてもいいのか?
一番望ましいのは、サービス提供をしたらすぐに記載することです。
ただし、現実的に排泄や食事や入浴といった事柄などは、ひとり対応したら介護記録を書くなどというようなことはできません。
サービス提供が一度始まってしまうとご利用者様を待たせてしまったり、業務効率が悪くなるからです。
一般的には1つの介助について、すべてのご利用者様の対応が終わり、一段落した際に、まとめて記載する場合が多いです。
また、事業者によっては記載時間が設けられており、決まった時間に記載する施設もあります。
介護記録を修正したい場合はどうすればいいのか?
介護記録は、公的文書としての役割があるので、修正したい場合には正式な方法で修正する必要があります。
間違えた箇所に二重線を引き、その上に修正印を押しましょう。
修正ペンなどの使用はできません。
介護記録は記載しておくだけでよいのか?
ご利用者様の日常生活上の出来事を、介護記録に残しておくことは職員間の情報共有においても大切です。
しかし、それだけでは情報共有に漏れが発生する可能性もあります。
なぜなら、介護記録に記載を残していたとしても、他の職員の確認するタイミングが遅ければ、情報を把握するまでにタイムロスが発生するからです。
また、介護記録の記載部分を見落としてしまうこともあるでしょう。
そういったヒューマンエラーは、可能な限り避けていきたいところです。
情報共有を円滑におこないたい場合は、介護記録に記載した内容を元に、職員間で申し送りをおこなうようにしましょう。
適切な方法で申し送りをすれば、情報共有の漏れを防ぐことができ、また効率的な業務の引継ぎをおこなうことが可能です。
円滑な情報共有の方法が知りたい方はこちらの記事をぜひチェックしてみてください。
介護記録は、基本を抑えてわかりやすく書こう!
今回は、介護記録の基本的な書き方とおさえるべきポイントを例文を交えて紹介しました。
介護記録は、ご利用者様やご家族様、事業所が連携し適切な対応をしているという証明にもなります。
抑えるべきポイントを把握しながら、自分なりの書き方を見つけ、ご利用者様にとってよりよい活用ができる介護記録をつくっていきましょう。
この記事を書いたのは・・・

小玉 有紀/Webライター
保有資格:介護福祉士/介護支援専門員/介護事務士
福祉系専門学校を卒業したのち、老健で介護福祉士として6年勤務。生活相談員を経験したのち、ケアマネージャーとして5年経験。現在は育児のかたわらライターとして活動中。