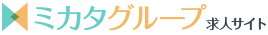「介護職の年間休日はどのくらい?」
「他の業種と比べて休みは少ない?」
「土日休みや連休は取れるの?」
介護職員は24時間365日体制でご利用者様を支えるため、シフト制勤務が基本で休日が不規則になりがちです。そのため、休みが十分に取れないと感じる方も多いでしょう。
本記事では、介護職員の年間休日の平均や施設形態・雇用形態ごとの違い、有給休暇の取得状況などについて詳しく解説します。法的なルールもふまえ、転職時に役立つ情報になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
この記事の内容
介護職員の年間休日の現状
介護職員の勤務はシフト制勤務が基本であり、他業種と比べて不規則であることが特徴のひとつです。厚生労働省の調査によると、医療・福祉業界の平均年間休日数は112.8日です。
最も多い休日数帯は100〜109日(40.4%)、次いで110〜119日(24.7%)で、120日以上の施設も19.4%存在しています。
| 年間休日数 | 割合 |
| 69日以下 | 1.0% |
| 70~79日 | 1.0% |
| 80~89日 | 0.2% |
| 90~99日 | 3.9% |
| 100~109日 | 32.3% |
| 110~119日 | 27.1% |
| 120~129日 | 31.9% |
| 130日以上 | 2.5% |
ちなみに、筆者はこれまで転職や異動を含め5つの施設で勤務経験があります。それぞれの施設の年間休日は以下の通りです。
- 118日:月9日+夏休5日+冬休5日
- 120日:月10日
- 108日:月9日
- 113日:月9日+夏休3日+冬休2日
- 115日:月9日+夏休4日+冬休3日
このように、年間休日の日数は施設ごとに異なるため、面接の際に確認するとよいでしょう。
また、同調査では、全業種の平均年間休日数は115.3日で、医療・福祉業界との差は2.5日程度です。
| 業種 | 平均年間休日総数(日) |
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 111.8 |
| 建設業 | 114.9 |
| 製造業 | 118.1 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 122.5 |
| 情報通信業 | 122.3 |
| 運輸業、郵便業 | 107.8 |
| 卸売業、小売業 | 113.8 |
| 金融業、保険業 | 121.1 |
| 不動産業、物品賃貸業 | 104.7 |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 108.2 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 104.7 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 108.2 |
| 教育、学習支援業 | 115.1 |
| 医療、福祉 | 115.1 |
| 複合サービス事業 | 119.0 |
| サービス業(ほかに分類されないもの) | 115.3 |
金融業・保険業(121.1日)や情報通信業(122.3日)よりは少ないものの、医療・福祉業界よりも少ない業種も複数あるため、医療・福祉業界が極端に低いわけではないことがわかります。
介護施設形態別の年間休日
介護職員の年間休日は、勤務する施設の形態によって大きく異なります。入所施設では24時間365日体制での勤務が求められる一方、通所系サービスや訪問系サービスでは日中のみの勤務が中心です。ここでは、各施設形態ごとの年間休日の特徴を解説します。
入所施設の場合
特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの入所施設では、24時間365日体制でご利用者様のケアを提供するため、施設としての休みはなく、平日・休日問わず勤務します。介護職員は日勤・夜勤の2交代制や早番・遅番・夜勤の3交代制で勤務し、交代で休みを取る形です。
具体的には、早番(7:00~16:00)、日勤(8:30~17:30)、遅番(12:00~21:00)、夜勤(16:00~翌9:00)といったシフトが一般的です。常勤スタッフは週休2日制を基本としていますが、シフトの都合で週1回の休日になることもあります。
そのため、週ごとの休日数ではなく、「月に9日」といった、月毎の休日数が定められています。土日に休めないこともありますが、平日に休みを取ることで、混雑を避けた外出ができるといったメリットがあります。
通所系サービスの場合
通所系サービスは日帰りのサービスを提供しており、土日または日曜日を定休日としている施設が多くあります。たいていの施設は日中のみの営業となり、夜勤業務はありません。
例えば、「完全週休2日制」や「日曜日+平日1日の週休2日制」といった休日の形態になります。勤務は日中のみですが、早番と日勤といった形で勤務時間を区別している施設もあります。土日にしっかり休みたい人やプライベートの時間を確保したい人に向いている勤務で、家庭との両立もしやすく、安定した生活リズムを築きやすいでしょう。
訪問系サービスの場合
訪問介護のような訪問系サービスでは、介護職員がご利用者様宅に訪問し、身体介護や生活援助を提供しています。大半の事業所では日中のみの勤務ですが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護のように夜間も対応している事業所や年中無休の事業所もあり、その場合はシフト制で休日を取得しています。
通所介護系サービス同様「土日休みの完全週休2日制」や「日曜日+平日1日の週休2日制」を採用している事業所が多く、家庭との両立や柔軟な働き方を求める人に向いています。
訪問系サービスは比較的自由度の高いシフト調整が可能で、自分のライフスタイルに合わせた働き方を選びやすい環境と言えるでしょう。
雇用形態別の年間休日
施設で働く介護職員は正規職員とパート・アルバイトのスタッフが多いですが、人手不足が原因で、契約社員や派遣職員の雇用も増えているのが現状です。ここでは、雇用形態別の休日の特徴について解説します。
正規職員
正規職員の場合、シフト制勤務が基本です。また、特別養護老人ホームやグループホームなどの入所施設では夜勤を含む交代制で、4週8休が一般的です。
年間休日は100~109日が多く、有給休暇や、施設ごとに定めている特別休暇(夏休・冬休など)も取得できる場合があります。月に2〜3日程度、休日の希望を出せることが多いですが、他のスタッフと希望が重なる場合は調整を依頼される場合もあります。
人手不足の場合には休日出勤を求められることもあるでしょう。シフトの人員が足りていれば希望休が通りやすい一方で、休みの融通は他の雇用形態より少ない傾向があるのが現状です。
パート・アルバイト
パート・アルバイトは正規職員と比べると柔軟に働くことができます。理由は、勤務日数や1日の勤務時間を選びやすく、祝日も休みやすいことです。
例えば、勤務日数は週に3回で1日5時間の勤務であっても、子どもが中学生になり、1日の勤務時間を8時間にするといった変更も可能になります。そのため、子育てや家事、介護などをしながら働きたい方には適した雇用形態と言えるでしょう。
一方で、正社員ほど手厚い福利厚生を受けられない場合があります。プライベートを優先しながら働きたい人には理想的な雇用形態ですが、待遇面については事前に確認する必要があります。
契約社員
契約社員は正規職員と同様にシフト制勤務であり、土日祝も出勤することが一般的です。4週8休または週休2日制が基本で、有給休暇や特別休暇も取得可能です。ただし、施設によって取得できる日数に差異があるため注意が必要です。
また、契約期間が定められており更新制となる点が特徴です。そのため、契約終了後の更新可否に不安を感じる場合もあります。正社員と似た待遇を受けられる一方で、不安定さを軽減するためにも就業規則や契約条件を事前に確認しておくことが大切です。
派遣職員
派遣職員は派遣先施設との契約内容によって勤務日数や時間を自由に選べます。週5日のフルタイム勤務から週2~4日の短時間勤務まで幅広く対応可能で、自分のライフスタイルに合わせた働き方ができるのが特徴です。
有給休暇や特別休暇は派遣会社の規則に基づき取得しますが、施設側からは直接付与されない場合もあります。また、施設のスタッフが福利厚生で受けられる給食費やインフルエンザワクチンのような予防接種の費用の補助を受けられないこともあります。就業前に、派遣元・派遣先双方と条件面について確認する必要があるでしょう。
介護職員の休日に関する法律
介護職員に限らず、労働者の休日や休暇は、労働基準法によって最低限の基準が定められています。週1日以上の休日や休憩時間、有給休暇の付与義務など、法律で保障された権利を理解することで、適切な働き方を実現するための指針となります。
労働基準法での定め
労働基準法では労働者の休日について、以下のように定められています。
- 「週1日以上の休日」または「4週間で4日以上の休日」(35条)
- 6時間を超える労働には45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩(34条)
- 6か月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に10日間の有給休暇を付与(39条)
また、2019年に労働基準法が改正され、企業は、労働者に年間5日以上有給休暇を取得させることが義務付けられました。これが守られない場合は事業所に30万円以下の罰金が課せられる場合があります。
介護職員もこれらの規定に基づき、最低限の休日・休暇が保障されています。自分が働く職場がこの基準を満たしているか確認することはとても大切です。
###有給休暇の取得状況
介護職員の有給休暇取得率は約66.8%です。全産業平均は65.3%なので、やや高い水準と言えます。しかし、シフト制勤務や人手不足により、連続した有給取得が難しい現場もあるのが現実です。
特に年末年始やお盆の時期は、希望者が多く、思うように休みが取れないこともあります。転職活動の際には、有給取得率がどの程度かも確認できるとよいでしょう。
介護職員が年間休日の多い施設を探すための注目ポイント
介護職員が年間休日の多い施設を探すための注目ポイントは以下の2つです。
- 年間休日数は「見える化」しているか
- 職員の入れ替わりはどの程度か
ひとつずつ解説します。
1.年間休日数は「見える化」しているか
休みやすい環境のある施設は「どの程度休みを取得できるか」をホームページや求人情報に明示しています。
- 年間休日数110日以上
- 有給取得率80%以上
- 週休2日制
施設を探す際に、上記のような情報が公表されていれば、その分の休日は確保されており、あなたの条件に合った施設を探す際の参考になるでしょう。
2.職員の入れ替わりはどの程度か
職員の入れ替わりが多い施設は、雰囲気が悪く、休みを取得しにくい可能性があります。人手不足によって休日出勤が続き、スタッフが肉体的にも精神的にも疲弊している場合も少なくありません。
一方で、休みが十分に取れている施設では、スタッフがいきいきと働いていることが多いです。面接時には「職員の定着率」や「有給取得状況」について質問してみるとよいでしょう。
また、事前に施設を見学して、スタッフの表情やご利用者様との関係性を見ることもおすすめです。笑顔で接しているスタッフが多ければ、休暇体制も整っている可能性が高いです。
介護職員の年間休日を理解して、職場選びの基準のひとつにしよう
介護職員の年間休日は、施設形態や雇用形態によって大きく異なります。シフト制勤務が基本で不規則な働き方が多い一方、通所系や訪問系サービスでは比較的休みやすい環境もあります。転職活動では、年間休日数や有給休暇取得率などを確認し、自分に合った職場を見つけることが重要です。
自分に合った職場を見つけるには、転職サイトを活用するのがおすすめです。「介護転職のミカタ」では、専門のコンサルタントが施設探しから入職までのサポートをしてくれるため、安心して転職活動を進められます。サービス利用は無料なので、まずはお気軽にご相談ください。
この記事を書いたのは・・・

さとひろ/Webライター
保有資格:ケアマネジャー/社会福祉士/介護福祉士/公認心理師
介護業界で22年の経験をもつ、特別養護老人ホームの現役ケアマネジャー兼生活相談員。介護職員・ケアマネジャー・生活相談員としての経験をもとにわかりやすい記事を執筆します。