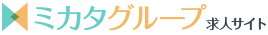介護施設では、ご利用者様や患者様の急変の現場に立ちあう場面があります。ベテランの職員でも、一人で完璧な対応をするのは難しいものです。あまり経験のない介護職員は、さらに不安を感じるのではないでしょうか。
本記事では、介護職員として働き始めた人や緊急時対応の経験が少ない人に向けて、ご利用者様の急変に対応する際の手順や救急要請の目安について解説しています。
いざというときにきちんと迅速な対応でご利用者様を守れるよう、最後まで読んでみてください。
この記事の内容
介護現場で「緊急時」とされる状況とは
介護施設で緊急とされるのは、大きく分けて以下の3パターンです。
- ケガをしたとき
- 病状が悪化したとき
- 急に体調が変化したとき
順番に見ていきましょう。
ケガをしたとき
介護の現場では、転倒や転落によるケガをしたときに緊急の扱いとなります。
高齢者は骨がもろいため、わずかな衝撃でも骨折や打撲につながり、深刻な状況に陥るケースもあるからです。
【ケガが発生しやすい状況】
- 自宅の庭で転倒する
- 居室や廊下でつまずく
- 入浴中に水滴で足が滑る
- トイレでの方向転換でふらつく
- ベッドから降りようとして転落する
高齢者がケガをする原因として、体力や筋力の衰えのほか、視力や判断力の低下も影響します。
介護の現場では、日ごろから安全に過ごせる工夫が必要です。
病状が悪化したとき
高齢者は複数の持病を抱えている方が多いため、介護職員はご利用者様の病状の悪化に備える必要があります。
血糖値の急激な上昇や低下、肺炎の悪化による呼吸困難、脳梗塞の後遺症による麻痺の悪化など、さまざまなケースを想定し、どのような場面でも対応できるよう努めねばなりません。
日ごろからご利用者様の健康状態を観察し、早い段階で異常を発見するよう意識しましょう。
急に体調が変化したとき
高齢者は、急に体調を崩す場合があります。脳や心臓、消化器の疾患が原因となり、命に関わる場合もあるため、迅速な対応が必要です。
【急変の例】
- 脳卒中による意識の低下や手足のしびれが出る
- 心筋梗塞で胸の激しい痛みや息苦しさが表れる
- 腸閉塞(イレウス)による激しい腹痛や吐き気が起こる
- ヒートショックによる血圧の大きな変動や意識消失がみられる
さっきまで元気だった方の状態が、急に悪くなる確率はゼロではありません。
顔色や話し方、動きの変化を見逃さず、異常を感じたらすぐに周りの介護職員や施設内の医師・看護師に報告しましょう。
救急車を要請する基準
「救急車を呼んでいいのか判断に悩む」と考えている人もいるでしょう。
生命の危機的状況においては迷わず救急車を要請するべきですが、症状によっては様子見すべきか迷うケースもあるのではないでしょうか。
ここでは、バイタルサインと症状に分けて救急車を呼ぶ基準を解説していきます。
バイタルサイン
| 体温 | ・38℃以上の高熱 ・35℃以下の低体温 | ||
| 血圧 | ・収縮期血圧90mmHg未満または200mmHg以上 ・急激な血圧の変動があるとき | ||
| 脈拍 | ・100回/分以上(頻脈) ・60回/分未満(徐脈) ・不規則で弱いとき | ||
| 呼吸 (血中酸素濃度) | ・10回/分未満または30回/分以上 ・呼吸音に左右差があるとき ・呼吸に異常がみられるとき ・SpO2(血中酸素濃度)が90%以下のとき | ||
症状
| 部位 | 症状 | ||
| 頭 | ・激しい頭痛 ・急に高熱が出る ・意識が無い、もうろうとしている ・ふらつきがあり立っていられなくなる | ||
| 顔 | ・視野が狭くなる ・ものが二重に見える ・ろれつが回りにくい ・顔半分が下に下がる、歪む ・顔半分が動きにくい、しびれている | ||
| 手足 | ・突然のしびれが出る ・片方の腕や足に力が入らない | ||
| 胸・背中 | ・痛む場所が移動する ・急に激しい痛みが出る ・突然の息切れや呼吸困難が起こる | ||
| お腹 | ・吐血 ・激しい痛みが出る | ||
そのほか、けいれんや大量出血を伴うケガ、火傷、食べ物を喉に詰まらせるなどの場合もためらわず救急車を呼びましょう。大切なのは一刻も早い対処で人命を守ることです。
介護施設や訪問介護における緊急時対応の手順
本章では、ご利用者様の緊急時対応を7つのステップに分けて解説します。
【緊急時対応7つのステップ】
- 名前を呼び、反応の有無を確認する
- その場から応援を呼び様子を確認する
- 安全な体勢を確保して応急処置をおこなう
- 医療職への相談や救急車の要請をする
- 救急車が着くまでに伝達事項をまとめる
- ご家族様に連絡する
- 報告書を作成する
①名前を呼び、反応の有無を確認する
ご利用者様の異変に気付いたら、まず側で名前を呼び、肩を優しく叩くなど刺激を与えて反応があるか確認します。
「◯◯さん、聞こえますか?」など、何度か声掛けし、反応がない場合は呼吸や脈拍を速やかにチェックします。パニックにならないよう、冷静に対応しましょう。
②その場から応援を呼び様子を確認する
次に、その場で他の職員に応援を求めます。
「誰か呼ばないと」と焦るあまり、ご利用者様から離れて他の職員を呼びに行くのは危険です。短時間の間に、急変する可能性もあります。
直接声を出して呼んだり、ナースコールやPHSなどの端末を使ったりして周りの職員に来てもらいましょう。
夜勤時は職員が少ないため、あらかじめ緊急時の役割分担を決めておくと連携がとりやすくなります。
③安全な体勢を確保して応急処置をおこなう
応援の職員と協力し、ご利用者様を安全な体位にします。
呼吸が止まっている場合は胸骨圧迫心臓マッサージに取り掛かり、AEDを使用する場合があります。
骨折の可能性がある場合は、無理に動かさず痛みが出ない姿勢を保つようにしましょう。
何かが喉に詰まって窒息の可能性が高いときは、吸引や背部叩打法や腹部突き上げ法などを試みます。
④医療職への相談や救急車の要請をする
対応にあたる職員と手分けして、応急処置と同時にご利用者様の症状を医療職に報告します。医師や看護師の判断を仰ぎながら、ご利用者様の症状に応じた応急処置や見守りを続けましょう。
⑤救急車が着くまでに伝達事項をまとめる
救急車が着くまでの間に、ご利用者様の既往歴や現在の状態、発症時の状況などの情報を整理します。
【救急隊員に伝える情報の例】
- いつからの症状か
- どのような症状か
- 現在のバイタル
- 過去の病歴
- 現在内服している薬
- アレルギーの有無
- 緊急連絡先
応急処置の内容なども含めて、救急隊員に詳しく情報を伝えるましょう。救急車の中や搬送先の医療機関で、ご利用者様にとってベストな対応がとりやすくなります。
⑥ご家族様に連絡する
次に、ご家族様への連絡をおこないます。救急搬送の有無に関わらず、速やかに状況を伝えましょう。
発見時の状況や現在の症状、搬送先の医療機関名など、落ち着いて説明します。
緊急時対応の経験が浅い人は緊張したり慌てたりするかもしれませんが、一番心配なのはご家族様と心得て、丁寧に伝えましょう。
救急搬送となった場合は施設の職員も付き添うケースがほとんどです。付き添った職員はご家族様の到着を待ち、あらためて現状を伝えます。ご家族の不安な気持ちに寄り添う気持ちを忘れずに関わりましょう。
遠方にお住まいのご家族には、状況に応じて定期的に経過を報告し、なるべく安心していただけるよう配慮しなければなりません。
⑦報告書を作成する
緊急対応後は、5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を意識し、報告書を作成します。
| 日時 | 発見時の日時 | ||
| 場所 | フロアや細かい場所(居室のベッド付近・トイレ など) | ||
| 対応者 | 発見した職員や、対応に当たった職員名 | ||
| 状況 | ご利用者様の氏名と発見時の状況をくわしく記載 | ||
| 対応内容 | どのような対応をおこなったかを記載する。 応急手当や救急車の要請、ご利用者様の状態の変化についても細かく記録する | ||
| 結果 | 対応の結果を記載する 「救急搬送の結果入院となる」など | ||
緊急時対応のNG行動
ご利用者様の急変には、ベテランの介護職員でも動揺するものです。経験が浅い場合は、慌てるあまり間違った対応をする可能性もあります。
ここでは、緊急時対応においてやってはいけないNG行動について解説します。
【緊急時にやってはいけないこと】
- ご利用者様の身体を動かす
- 血液や吐瀉物に素手で触れる
- 独断でご利用者様に服薬させる
ご利用者様の身体を動かす
状況によっては、ご利用者様の身体をむやみに動かすと事態を悪化させることになります。
たとえば、骨折の疑いがある場合、身体を動かすと骨がずれたり、内出血を引き起こしたりする可能性があります。
判断に迷ったら、必ず先輩職員や医療職の指示を仰ぎながら対応しましょう。
血液や吐瀉物に素手で触れる
血液や吐瀉物に素手で触れるのもNGです。血液や吐瀉物にはさまざまな病原体が含まれている可能性があり、感染症を引き起こす危険性があります。
ご利用者様の血液や吐瀉物を処理するときは、必ずマスクや使い捨ての手袋やエプロンを着用しましょう。処理したあとは、手袋やエプロンを職場のルールに従って廃棄し、石けんと流水で手を丁寧に洗います。アルコール消毒も忘れずにおこないましょう。
独断でご利用者様に服薬させる
介護職員が独断でご利用者様に服薬させるのもNG行動のひとつです。薬の種類や服用量を誤ると、身体に悪影響を及ぼす危険性があります。
例えば、利用者が強い頭痛を訴えたとき、過去に服用していた鎮痛剤を職員の判断で飲ませてしまうと、薬の成分が持病と合わず血圧が急上昇する可能性があります。
緊急を要する場面でも、医療職の指示のもと安全な対応を徹底しましょう。介護職員はご利用者様の命を守る責任があります。安易な判断が事故につながると心得て、一つひとつの行動に細心の注意を払う姿勢が大切です。
介護施設や訪問介護でよく起こる緊急時対応の例
ここからは、介護の現場でよく見られる緊急時対応について見ていきましょう。
意識が消失したり、転倒などで骨折が疑われたりするケースや、入浴時のヒートショックなどを例に解説します。
どのような場合でも、一人で対応せず周りに助けを求め、万全の体制でご利用者様をケアしていきましょう。
意識が消失した場合
ご利用者様が意識消失した場合、以下の対応が必要です。
- 気道の確保
- 呼吸の確認
- 脈拍の確認
- 体を横向きにする
- 嘔吐物の有無を確認
これらの応急処置をおこないながら、救急隊の到着を待ちます。救急隊員には、利用者の氏名や年齢、既往歴などの詳しい情報と、発見時の状況やおこなった処置を正確に伝えて引き継ぎます。
骨折した疑いがある場合
ご利用者様が転倒や転落によって骨折した疑いがある場合、動かさないように注意しながら以下の点を確認します。
- 痛みの程度
- 腫れや変形
- 皮膚の状態
- 意識の状態
骨折が疑われる場合は、患部を固定し、安静を保ちます。腫れが酷いときは冷やしたり、患部を固定したりしましょう。
入浴時に急変した場合
高齢者は、浴室と脱衣所の寒暖差によりヒートショックを引き起こす可能性が高いです。
万が一ご利用者様が入浴中に急変した場合は、以下の手順で対応します。
- 速やかに浴槽のお湯を抜き、浴槽から引き上げる
- バスマットの上で安全な体位にする
- バスタオルなどで保温する
- 呼吸と意識状態を観察する
寒い時期はとくにヒートショックの可能性が高まる傾向です。介護職員は浴室での緊急時にも備えておく必要があります。
現役介護士が実際におこなった緊急時対応の体験談
現役介護士が実際におこなった緊急時対応の体験談を紹介します。今回は、以下2つの介護施設の形態別に、夜間帯に発生した緊急時の対応について見ていきましょう。
- 特別養護老人ホーム
- グループホーム(認知症対応型共同生活介護)
特別養護老人ホーム
ある夜勤中に、ご利用者様がトイレで転倒し、頭部を強く打ち出血しているのを発見しました。すぐにバイタルを確認し応急処置をした上で、夜間対応の看護師に連絡し救急車を手配。
救急車には、対応した夜勤の職員が同乗し、病院に向かいました。夜勤の職員が現場から離れている間は、夜間緊急時対応の職員が現場の業務を担当。
頭部を打っているため念の為入院となり、その状況をご家族にも連絡し説明後、病院までこられました。
日頃から緊急時対応の勉強会やマニュアルの共有を徹底していたため、当日もスムーズに対応できました。
特別養護老人ホームでは、医療依存度の高い利用者が多いため、緊急時の対応力が非常に重要です。
なお、ご紹介した介護施設の特別養護老人ホームの仕事内容については、以下の記事で詳しく解説しています。
特別養護老人ホームの仕事内容|現役介護福祉士が給与やシフトも解説
グループホーム(認知症対応型共同生活介護)
とあるグループホームでの夜勤中、ご利用者様が嘔吐と下痢を繰り返す事態が発生。感染症の可能性もあるため、まずは居室で隔離し、他のご利用者様と接触しないよう配慮しました。
その後、管理者と夜間担当の看護師に電話連絡し、具体的な指示を仰ぎました。バイタルの異常がなかったため、その他の症状や急変がない限りは様子観察することに。
その後は特変なく朝まで経過し、感染症ではありませんでしたが、万が一感染力の高いウイルスの場合は、緊急時の初期対応が非常に重要になります。
緊急時の対応では、最悪の事態を想定し、可能な限りリスクを減らす対応が求められます。日頃からマニュアルを確認したり研修会をおこなったり、職員間で情報共有しておきましょう。
以下の記事では、グループホームの夜間の仕事内容や、メリット・デメリットを解説しているので参考にしてください。
グループホームの仕事内容は?現役介護職員が職種や給与事情も解説
緊急時対応のために普段からできること
ご利用者様の予期せぬ急変に慌ててしまうかもしれませんが、普段から対策しておくといざというときに慌てることなく対応できます。
【緊急時対応の備え】
- 緊急時対応の訓練をおこなう
- 職場の緊急時対応マニュアルを読み込む
- 介護のセミナーや講習会に参加する
- ご利用者様の普段の様子を観察する
順番に見ていきましょう。
緊急時対応の訓練をおこなう
日ごろから、定期的に緊急時の対応について訓練しておきましょう。誰がご利用者様の対応にあたるのか、医療職や管理者への報告は誰がおこなうのかなど、あらかじめ決めておくと緊急時対応でパニックになりにくいです。
救急車を要請した場合に備えて、救急隊員にスムーズな情報提供ができるようテンプレートを作っておくのもおすすめです。
【筆者の経験談】
筆者が以前勤めていた病院で急変があったとき、介護職員が感染症の流行でいつもより少ない人数だったことがありました。
看護師の判断で救急車を呼びましたが、相談員や管理職は不在で、介護職員や看護師もバタバタしていたため、救急隊への情報提供は事務員さんがしなければなりませんでした。
しかし、事務員さんはこうした対応に慣れておらず、結局搬送直前に付き添いの看護師が救急車の中で情報提供をしたのです。
こうしたケースは珍しくありませんが、「少ない人員でも前もって緊急時対応の訓練をしておけば、もっとスムーズに連携が取れたのでは」との意見もきかれました。
常に職員がたくさんいるとは限りません。さまざまな事態を想定し、ご利用者様の急変にも即座に対応できるよう役割分担を明確にし、実際のシミュレーションをおこなうことが大切です。
職場の緊急時対応マニュアルを読み込む
介護施設の大半が救急搬送に関するマニュアルを作成しています。厚生労働省の資料によると、救急搬送の要請についてマニュアルを作成している施設の割合は特別養護老人ホームが86.4%でした。訪問看護の事業所も半数以上がマニュアルを常備しています。
緊急時対応マニュアルは、経験の浅い介護職員でも迷わずに動けるように作成されています。一見すると難しく感じるかもしれませんが、実際の緊急時に慌てないためにも普段から目を通しておき、わからない部分は先輩職員に確認するなどして不明点が無いようにしておきましょう。
介護のセミナーや講習会に参加する
定期的にセミナーや講習会に参加するのもおすすめです。
とくに救急対応に関する研修は、実践的なスキルを学べるため、実際の現場で役立つ知識と技術が身につきます。
また、医療技術について学ぶと、より適切なケアを提供できるようになります。
施設内での勉強会やオンラインセミナーなど、学習の機会を積極的に活用し、日々の業務に役立てましょう。
ご利用者様の普段の様子を観察する
緊急時対応の備えとして、ご利用者様の普段の様子を観察しておくのも有効です。
普段の様子がわかっていれば、「いつもと違う」とすぐに気づき、適切な対応ができます。
ご利用者様の身体の状態は日々変化します。普段の歩き方や話し方、食事量を把握しておくと、小さな変化にも気づきやすくなるでしょう。
例えば、いつもはよく食べるご利用者様の食事が進まない場合、脱水や体調不良が隠れているかもしれません。また、ハキハキ話す方の返事が遅くなったり、歩行が安定している方が大きくふらついたりする場合は脳梗塞の可能性が考えられます。
日ごろの状態を細かく観察できていれば、ご利用者様のささやかな異変を早い段階で察知できます。ご利用者様の生活に寄り添いながら「いつもの姿」をしっかり把握しておきましょう。
介護職の緊急対応に関するよくある質問
ここでは、介護職員からの緊急時対応に関する質問に回答します。
夜勤の緊急時はどう対応すべきですか?
夜勤中にご利用者様の緊急時対応にあたる際には、まず冷静になりましょう。職員の人数が少ない夜間は、想像以上に焦りと緊張がこみ上げてきます。しかし、そういうときこそ落ち着かなればなりません。
日中と違い、夜間は介護職員がかなり減ります。効率の良い対応がご利用者様の生命を守ることにつながると考えましょう。事前に役割分担を決め、必要に応じてマニュアルを更新することも必要です。夜間であっても、ご家族様への連絡も忘れずにおこないましょう。
救急車を呼ぶか迷ったときの判断基準を教えてください
利用者の緊急時に救急車を呼ぶか迷った場合、命に関わる症状があるかを基準に判断しましょう。迅速な対応が必要なためです。
以下のような状態が見られたら、ためらわず救急車を要請してください。
- 大量の出血がみられる
- 意識がない、または反応が弱い
- 高熱で意識がもうろうとしている
- 呼吸が苦しそう、または停止している
- 激しい胸の痛みや突然の手足の麻痺が起こっている
もし判断に迷ったら、すぐ医療職や上司に相談し、指示を仰ぎましょう。迷っている時間は、ご利用者様の治療の遅れにつながります。ひとりで抱え込まず、助けを求めて職員みんなで協力することがご利用者様を守ることにつながります。
緊急対応後、家族に報告するときのポイントは?
ご家族様への報告は、冷静かつ簡潔におこないましょう。
何が起こったのか、どのような対応をしたのか、現在の状態や今後の対応についてなど、わかりやすい言葉で伝えます。
ご家族様は驚きや不安を感じています。連絡するときは、その思いに寄り添う意識を持ちましょう。
自然災害による緊急時はどう対応したらいい?
自然災害時には、まずご利用者様の安全を最優先に考え、迅速に避難行動を取らなければなりません。事前に避難経路や安全確保の方法を確認しておきましょう。
施設にある、緊急時のマニュアルの周知は不可欠です。
停電や断水などのライフラインへの備えも万全にする必要があります。定期的な防災訓練をおこない、職員が落ち着いてご利用者様と自身の安全を守れるよう準備しておきましょう。
まとめ
介護の現場では、ご利用者様のケガや持病の悪化など、緊急時対応を求められる状況が少なくありません。迅速に対応するためには、日ごろからご利用者様の様子を把握し、普段と違う様子にいち早く気付けるように心がけることが大切です。
さらに、職場の緊急時対応マニュアルを定期的に確認し、職員みんなで訓練を重ねれば急を要する事態になっても落ち着いて行動できます。職員間の連携と適切な判断で、ご利用者様の命を守りましょう。
この記事を書いたのは・・・

佐藤 恵美/Webライター
保有資格:介護福祉士/社会福祉士
回復期リハビリ病棟で7年勤務したのち、社会福祉士を取得し、
生活相談員を経験。現在はフリーのWebライターとして活動中。