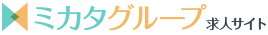介護現場では、利用者の安全や業務の効率を優先するあまり、無意識のうちに「スピーチロック」と呼ばれる言葉の制限を行ってしまうことがあります。
スピーチロックは、言葉によりご利用者様の自由を奪い、行動意欲や認知機能の低下を引き起こす恐れがあるため、適切な対策を行うことが重要です。
本記事では、スピーチロックの概要や発生要因、ご利用者様への影響などを、現役介護職の経験をもとに解説します。さらに、具体的な防止策を紹介しているので、スピーチロックに悩んでいる介護現場の方は、ぜひ参考にしてください。
この記事の内容
スピーチロックとは
スピーチロックとは、介護の現場で使われる言葉で、高齢者の行動を制限するような声かけのことです。
たとえば「立ったらダメ!」「危ないから歩かないで!」「できないからしなくていい!」といった言葉が該当します。
スピーチロックは安全を考慮して出てくる言葉ですが、ご利用者様は自分の意思を抑えつけられ尊厳を傷つけられている可能性があります。
介護職はご利用者様に対して、適切な言葉選びをすることが大切です。スピーチロックを防ぐことは、高齢者の生活の質を守ることにつながります。
3つのロックとは
介護現場のロック(拘束)は、主に以下3つに分けられます。
| ロック(拘束)の種類 | ロック(拘束)の内容 | |
| スピーチロック | 不適切な声かけによる行動制限 | |
| フィジカルロック | ベッド柵や介護つなぎなど身体的拘束による行動制限 | |
| ドラッグロック | 薬の過剰投与や不適切な投与による行動制限 | |
上記の中でも、スピーチロックは無意識にしているケースもあり、介護職の意識を変えることで改善できる可能性があります。
ここからさらに、スピーチロックの要因や具体的な防止策などを見ながら、スピーチロックの減少や介護サービスの質の向上に活かしていきましょう。
スピーチロックが起きる要因
スピーチロックが起きる要因は、主に以下の3つです。
- 人員不足によりストレスが溜まっている
- 情報共有が不足している
- 安全だけを優先しすぎている
それぞれ具体的な内容を確認しましょう。
人員不足によりストレスが溜まっている
多くの介護の現場では、慢性的な人手不足が続いており、職員一人あたりの負担が大きくなっています。その結果、仕事に追われ精神的な余裕がなくなり、ご利用者様に対する接し方が雑になったり、効率を優先して命令口調になったりすることがあります。
介護職の本来の役割はご利用者様の自立支援ですが、人手不足によるストレスから、無意識のうちにスピーチロックをしているのが実情です。
適切な人員配置や業務負担の軽減を図ることで、職員の余裕を確保し、スピーチロックを防ぐことが重要です。
介護職でイライラがとまらない場合は、適度なストレス発散を
介護職員として働いていて、イライラがとまらないという声を耳にすることがあります。
さまざまな原因がある中の一つが、人員不足です。
しかし、ストレスを放置してしまうと、ご利用者様へのスピーチロックにつながるほかにも、さまざまな弊害が生じます。
例えば、対応が雑になりご利用者様からの信頼を失ってしまうなどです。
ご利用者様の心身の安全を守ることに集中し、適切なコミュニケーションがとれるようになるためには、介護職員として心身ともに健全な状態にしておくことが大切です。
イライラがとまらないときには、感情のコントロールができる「アンガーマネジメント」をすることにより、冷静な自分を取り戻すことができます。
アンガーマネジメントは手法を知れば、誰でも簡単に取り組むことが可能です。
「イライラがとまらずいつかスピーチロックをしてしまうかもしれない」と不安な方は、ぜひこちらの記事をご参照ください。
情報共有が不足している
ご利用者様に関する情報共有が十分にできていないと、スピーチロックを発生させる原因になります。
たとえば「あるご利用者様はふらつきはあるものの、ご自分で歩くことでリハビリをしている」という情報があっても、共有されていないと「危ないから座ってください」という声かけをするかもしれません。
口頭での情報共有だけでなく、申し送りノートや情報共有アプリ(LINEのグループ機能等)を活用し、効率的にこまめな情報共有をすることが大切です。
安全だけを優先しすぎている
ご利用者様の安全を優先することは重要です。しかし、安全だけを優先しすぎると、ご利用者様の行動を制限してしまいます。
たとえば、転倒を防ぐために歩かせなかったり、失敗を防ぐためにその方の役割を奪ったりすることが挙げられます。介護職はご利用者様の安全に配慮しつつ、その方の能力や意欲を最大限活かすことが大切です。
過度な安全重視ではなく、バランスの取れた支援を心がけることで、スピーチロックを防ぎ、利用者の生活の質を向上させられるでしょう。
スピーチロックがダメな理由と与える影響
スピーチロックは、ご利用者様に以下のような影響を与える恐れがあります。
- 行動意欲や身体能力が低下する
- 認知症症状を悪化させる恐れがある
- 職員の負担が増える可能性がある
ご利用者様にとっても介護職にとってもいいことはありません。それぞれの影響を理解した上で、効果的にスピーチロックを減らしていきましょう。
行動意欲や身体能力が低下する
「危ないからやらなくていい」「転ぶから座っていてください」といったスピーチロックの言葉をかけられ続けると、ご利用者様は自分で動こうとする意欲を失ってしまいます。
とくに高齢者は、日常的に体を動かさないと筋力や関節の柔軟性が低下し、転倒リスクが高まるため、長期的にリスクを増大させる要因にもなります。
介護職は、安全に配慮しつつ「一緒に歩きましょう」「できることを続けましょう」など前向きな言葉を心がけ、ご利用者様が可能な範囲で自分の力を発揮できるよう支援することが大切です。
認知症症状を悪化させる恐れがある
認知症の方に対してスピーチロックを多用すると、自分で考える機会が減り、認知機能の低下を加速させる恐れがあります。
たとえば「危ないから触らないで」と言われ続けると、日常生活の中で判断する力や記憶を使う機会が少なくなり、認知機能がさらに衰えてしまうかもしれません。
また、命令口調や否定的な言葉は、ご利用者様のストレスや不安を増大させ、BPSD(認知症の行動・心理症状)の悪化につながることもあるでしょう。
スピーチロックをできるだけ避け、前向きな言葉を心がけることで、ご利用者様の意欲を促し、生活の質を向上させる鍵となります。
職員の負担が増える可能性がある
スピーチロックによって利用者の自立が妨げられると、結果的に介護職の負担が増加します。
本来であればご利用者様ができることも、職員がすべて行わなければならなくなり、業務量が増えてしまうからです。
たとえば「転ぶと危ないから歩かなくていい」と言い続けると、ご利用者様の歩行能力が低下し、トイレや移動のたびに職員の介助が必要になります。
また、ご利用者様の不満やストレスが溜まることでトラブルが増え、職員の精神的な負担も増加するでしょう。
職員の負担を減らすためにも、利用者の能力を引き出し、できることは積極的に行ってもらうことが重要です。
スピーチロックの具体例と防ぐための方法
スピーチロックを防ぐために必要なことを、以下の項目別に解説します。
- スピーチロックを防ぐための人員配置の工夫
- スピーチロックを防ぐ勉強会の進め方
- 職員のチーム力を高める
- 適切な声かけに変えるポイント
それぞれの具体的な内容を見ていきましょう。
スピーチロックを防ぐための人員配置の工夫
スピーチロックを防ぐには、職員が余裕を持って対応できる環境を整えることが重要です。
とくに、人員不足による業務の忙しさが原因で、職員が効率を優先した結果、スピーチロックが増えている場合、人員配置を工夫することで改善できる可能性があります。
具体的には、適切なシフト管理を行い、ピーク時に応援スタッフを配置したり、早番や遅番業務の時間を柔軟に変更したりするなどが効果的です。
筆者の場合は、休憩時間を柔軟に変更し、忙しい時間に人手が不足しないよう工夫しました。
特定の職員に負担が集中しないよう余裕を持った人員配置をすることが、スピーチロックを減らす第一歩です。
スピーチロックを防ぐ勉強会の進め方
スピーチロックを防ぐためには、職員全体で正しい理解を深めることが重要です。
具体的な取り組みとして、定期的な勉強会の開催が挙げられます。実際の現場でどのような言葉がスピーチロックに該当するのかを、グループワークやロールプレイングなどを通して実践的に学ぶのが効果的です。
また、職員同士で事例を共有し、どのように声かけを改善すべきか話し合うことで、現場での意識を向上させる効果も期待できます。
勉強会は定期的に開催し継続することで、職員の意識が高まり、継続的なスピーチロックの防止につながるでしょう。
筆者の職場では、毎月行う職員会議の際に、身体拘束に関する議題があるため、そこでスピーチロックに関する反省会を行い、職員の意識の定着につなげています。
職員のチーム力を高める
スピーチロックを防ぐためには、職員で協力し合えるチーム力を高めることも大切です。
なぜなら、スピーチロックは職員が感情的に不安定になっているときに起きやすく、その原因が職員の負担感の重さであることが多いからです。
例えば、チームワークがうまくいっていない場合、職員同士で協力・連携ができず、一人当たりの負担感が高くなってしまうこともあるでしょう。
逆にチームワークが良好であれば、協力し合えるため、一人当たりの負担感は減ります。
その結果、業務負担によるストレスが軽減され、スピーチロックがおきやすい環境を改善することができます。
職員間のチームワークを円滑にすることは、ご利用者様にとっても利益となるでしょう。
介護職のチームワークをよくする方法について、さらにくわしく知りたい方はこちらの記事をぜひご参照ください。
適切な声かけに変えるポイント
スピーチロックを防ぐには、命令口調や制限的な言葉を、利用者の意欲を引き出す言葉に変えることが大切です。
たとえば「危ないから座っていてください」ではなく「ちょっと休んでから一緒に歩いてみませんか?」と提案すると、ご利用者様の自立を促すことにつながります。
また「やらなくていいですよ」と伝え、すべて職員が行うのではなく「ここはどうしますか?」とご利用者様の意向を確認しながら対応することも重要です。
筆者も意識的に命令口調や制限的な言葉を禁止することで、今では前向きな言葉をかけることが習慣化しました。
次の章で、具体的な言葉の言い換え例を紹介しているので、あわせてご覧ください。
スピーチロックにあたる言葉の言い換え表現
スピーチロックを防ぐためには、制限的な言葉をできるだけ避け、ご利用者様の気持ちや意欲を尊重する声かけが大切です。
たとえば「危ないから立たないで!」と言うと、ご利用者様は意欲を失い、自立支援の妨げにつながります。
以下の表のように、言葉を少し工夫するだけで、ご利用者様にとって前向きな声かけに変えることが可能です。
| スピーチロックの例 | 適切な言い換え例 |
| 危ないから立たないで! | どうされましたか?(要望を聞く) |
| ちょっと待って! | あと〇分待っていただけますか? |
| やったらダメ! | できることからやりましょう |
| 転ぶから歩かないで! | 一緒に歩きましょう |
| 触らないで! | これが気になりますか? 何がしたいですか? |
相手を尊重する言葉に変えることで、ご利用者様の自信や意欲を引き出すことができるため、ADLやQOLの向上につながるでしょう。
スピーチロックが発生しやすい職場の特徴
スピーチロックが発生しやすい職場には、以下のような共通点があります。
- 人手不足が深刻
- 情報共有が不足している
- 安全を優先しすぎる
人手不足が深刻になると、職員が業務に追われ、効率ばかりを優先してしまい、行動を制限するような声かけが増える恐れがあります。
ご利用者様の状態やサービス内容が職員間で共有されていない場合も、適切な声かけができずスピーチロックにつながるかもしれません。
安全を優先しすぎると、ご利用者様の身体機能や意欲の低下を招くリスクもあるでしょう。
上記のような環境では、職員のストレスも増え、スピーチロックが常態化しやすくなります。職場全体で意識改革を行い、ご利用者様の尊厳を守る対応を心がけることが重要です。
まとめ
スピーチロックは無意識にしていることが多く問題視されていないケースが多くあります。
しかし、スピーチロックによりご利用者様の尊厳を傷つけ、心身にさまざまな悪影響を及ぼしているのが実情です。
スピーチロックの影響を把握し、効果的な防止策を実践すれば、ご利用者様のADLやQOLの改善につながり、介護サービスの質も向上します。
ぜひ本記事で紹介した内容を活かして、職場のスピーチロックの減少や改善を実現していきましょう。
この記事を書いたのは・・・

津島 武志/Webライター
保有資格:介護福祉士/介護支援専門員/社会福祉士
業界17年目の現役介護職兼ケアマネージャー。
さまざまな介護系メディアでWebライターとしても活動し、多くの検索上位記事を執筆。
介護職以外に転職メディア「介護士の転職コンパス」や自身のライフスタイルや介護系コンテンツを発信するYouTubeチャンネル「かいご職TV」等を運営。