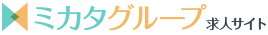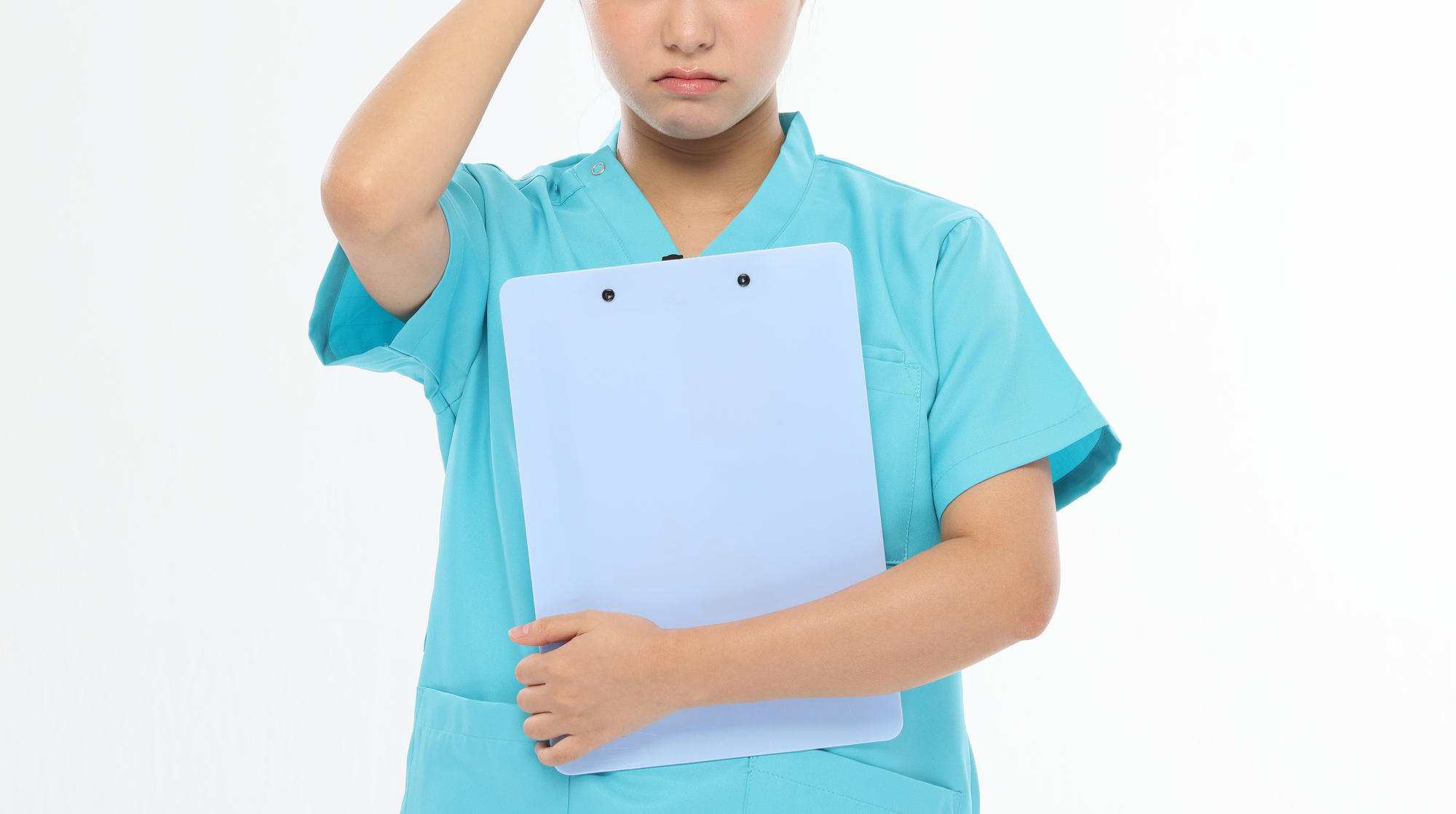
「介護の仕事は嫌いじゃないけどイライラしてしまうときがある」と悩んでいる人もいるのではないでしょうか。
介護の仕事でイライラが収まらず、そのままの感情をご利用者様にぶつけてしまえば関係は悪化してしまうどころかクレームなど思わぬトラブルにも発展してしまう可能性があります。
本記事では、介護職員のイライラの原因やアンガーマネジメントの方法、解消法などを紹介していきます。
記事を読めば、イライラを解決する方法がわかり、気持ちよく業務を遂行することができるようになるでしょう。
この記事の内容
介護職員がイライラしてしまう原因4つ
介護職員がイライラしてしまう原因は大きくわけて4つあります。
- 忙しいから
- 連携がうまくできていない
- 思い通りにいかないことが多い
- 責任が重い
ここからは、介護職員がイライラしてしまう原因4つについて詳しく解説していきます。
忙しいから
介護職員がイライラしてしまう原因の一つは が忙しいからです。
介護現場は慢性的な人手不足に悩まされていることが多く、多忙である傾向にあります。
また、ご利用者様への要望対応や常時の見守りなど、常に動いている必要がある環境であればなおさら心の余裕がなくなってしまうでしょう。
そうした背景から、イライラしてしまう介護職員は多いです。
筆者は、転倒リスクの高いご利用者様が動き回っているときに、さまざまなことを他のご利用者様から頼まれると気持ちに余裕がなくなることがありました。
転倒リスクが高いご利用者様が動き回ることで、常に見守りが必要になる状況で、他のことを同時にこなしていくことは至難の業です。
多忙な状況により、どうしてもイライラしてしまう職員がいるのは、筆者の経験からも理解できます。
連携がうまくできていない
職員間の連携がうまくできていないことも、イライラを引き起こしてしまう原因の一つです。
連携ができていないことで、業務にロスが生じたり、職員一人あたりの負担が大きくなってしまったりするからです。
例えば、情報の共有が上手くできていない場合は、必要な情報を把握していない状態で介護ケアにあたるためミスを引き起こします。
介護ケアのミスが続くと、ご利用者様に迷惑をかけたり、それを修復するための作業が増えたりと負担がより重くなってしまいます。
そうした結果、業務が上手く進まずイライラにつながってしまうのです。
仕事上のイライラを回避するためには、職員間の協力やスムーズな連携が必要不可欠となります。
思い通りにいかないことが多い
介護の仕事は、思い通りにいかないことの連続です。
なぜなら、対人の仕事であり、ご利用者様の疾患や症状、性格によってスムーズにコミュニケーションをとれないことがあるからです。
例えば重度の認知症で転倒リスクの高いご利用者様が動き回ろうとされていた場合、口頭説明では上手く伝わらないことが多いでしょう。
上手く阻止できず、ご利用者様が動き回った結果、転倒をしてしまうというケースは介護現場では結構よくある話です。
筆者も過去に同じ経験をしたことがあります。
こうした背景から、どうしたらよいかわからずイライラしてしまうこともあるでしょう。
思い通りにいかないことによるイライラの回避方法は、その対処法を知ることです。
例えば動きまわるご利用者様に対し、常に困っているのであれば、臨時会議を開き職員間で解決方法を探していくのがよいでしょう。
責任が重い
イライラの原因の一つが、介護の仕事の責任の重さです。
介護の仕事は、ご利用者様の命と隣り合わせの側面があり、その緊張感からイライラしてしまうこともあります。
例えば、体調が思わしくないご利用者様が多いときに人手が少ないと、限られた職員で対応をしなければなりません。
対応方法を一歩間違えれば命に関わる状況下でありながら、それでも他の業務もこなさなければならないと思うと、気持ちは常にピリピリとしてしまうでしょう。
人の命を預かる大切な役割を担っている責任感から、イライラしてしまう介護職員は多いです。
【イライラしないために】アンガーマネジメントのすすめ
イライラしないための一つの方法として、アンガーマネジメントがあります。そこで、ここからはアンガーマネジメントについて詳しく解説していきます。
アンガーマネジメントとは
アンガーマネジメントとは、自分の怒りの感情をコントロールするための手法です。
怒りの感情を持ち続けることで、空気はピリピリとし、丁寧に接することができなくなります。
その結果、ご利用者様を嫌な気持ちにさてしまうのです。
また、怒りを心に住まわせながら接することで、目の前の出来事をフラットな感情で精査することができなくなります。
例えば、ご利用者様からお願いごとをされたときに、イライラしたままでいると快く引き受けることができなくなってしまいます。
そういった負の状況を改善するために、自分自身の「怒りの感情」と向き合い、うまくコントロールしていくのがアンガーマネジメントです。
ご利用者様に安心感を与えられるような介護ケアを実施していくためにも、アンガーマネジメントは重要なのです。
アンガーマネジメントの方法
アンガーマネジメントの方法はいくつかあります。
簡単に実践できる特におすすめなのは次の方法です。
- 怒りを感じたときに「1、2、3…」と数を数えて気持ちを落ち着かせる
- 自分の中の「すべき」という固定観念を疑う
- 深呼吸をする
- 怒りにレベルをつける
怒りの感情に気づいたら、まずは一呼吸おいてみることにしましょう。
そうすると、自然と心が落ち着いてきます。
怒りを感じたら、その感情のまま接するのではなく、その気持ちを客観視することで静まっていくことがあります。
自分に合った方法をみつけて、現場でイライラしたときにぜひ実践してみてください。
アンガーマネジメントで快適に仕事ができた体験談
筆者は、アンガーマネジメントを自分でよく実践していたので、その一例を紹介します。
例えば、ご利用者様に「お前はバカだ!」と怒鳴られたことがありました。
ご利用者様は認知症を患っている方で、致し方のない出来事だったと思いますが、その当時は悲しさと怒りの感情が沸き起こってきました。
そこで、自分のなかの固定観念を疑ってみることにしたのです。
筆者はこれまで「バカ」と人に向かって言うということは、相手を見下している行為に違いないと思ってきました。
しかし、そうとは限らないかもしれないと考えるようにしたのです。
そう考えるようにした後は、そのご利用者様にもフラットな気持ちで接することができました。
関わっていくうちにわかったことですが、ご利用者様はさみしい感情をわかってほしいときに「バカ」と発言するようでした。
自分のなかの固定観念を疑い、一旦フラットな感情を手に入れることで、そのご利用者様の行動の原因や本質に目を向けることができるようになったのだと思います。
アンガーマネジメントは、ご利用者様に対してはもちろんのこと、自分にとってもマイナスをプラスにする力のあるものです。
自分に合った方法で、アンガーマネジメントをぜひ試してみてください。
イライラしたときの対処法
職場でイライラしたときには、どのような対応をしたらよいかわからないという人もいると思います。
そこで、ここからは介護の仕事中にイライラしてしまったときの具体的な対処法を紹介していきます。
上司や同僚に相談する
業務中、イライラが止まらず悩んでいるときには、一人で抱え込まず上司や同僚に相談してみましょう。
イライラの原因によっては、自己解決が難しいこともあるからです。
例えば、イライラの原因が人手不足によるものだった場合、人材の確保やシフトの調整などが必要になります。
相談して思うように解決できるとは限りませんが、一人で悩んでいるより誰かを頼ってみるのも一つです。
すぐに解決してもらえなかったとしても、悩んでる事実を職場内で把握できていれば時間をかけて解決へと何かしらのアクションを進めてくれるかもしれません。
業務の仕方を見直す
イライラしたときは、自分の業務の仕方を見直すのも一つです。
業務を効率化するために、手順を見直すことで、状況が改善できる可能性があるからです。
例えば、排泄介助に時間がかかってイライラしてしまうとします。
その場合は、どこの部分に時間がかかっているかを自己分析するようにしましょう。
物品が足りなくて途中で取りにいくことが多い場合は、先に必要物品を全て揃えておくことで解決します。
このように、どの部分で自分が困っているかを今一度考え、それに向けた解決策を考えていくとイライラせずに業務に集中できる可能性が高まります
おすすめストレス解消方法
介護の仕事でストレスを感じたときには、上手に解消していきたいところです。ここからは、介護の仕事でストレスを感じたときのおすすめな解消方法を3つ紹介していきます。
- マッサージをする
- 良質な食事や睡眠にこだわる
- 休日は思いっきり遊んでオンオフをきっちりとわける
- 有給休暇を取得する
- 業務中にクスっと笑う
マッサージをする
介護の仕事でストレスを感じたときのおすすめ解消法の一つは、マッサージです。
体と脳はつながっていますので、疲れや凝りを感じたときにはSOSのサインかもしれません。
マッサージでリラックスし、凝りを解消すると、心も癒され、次の日に元気に仕事ができることがあります。
筆者も介護の仕事で疲れたときには、よくマッサージ屋さんに行っていました。
疲れたときには、マッサージで癒されることも選択肢の一つとしてご検討ください。
良質な食事や睡眠にこだわる
介護の仕事のストレスを解消するためには、良質な食事や睡眠にこだわることがおすすめです。
なぜなら、ストレス解消には、健康的な生活が基本となるからです。
例えば、睡眠の質を高めるために寝る前のスマホをやめる、または健康な体づくりのためにバランスよい食事を意識するなどがよいでしょう。
良質な睡眠や健康的な食事を意識して、ストレスに強い体づくりを心がけることが大切です。
休日は思いっきり遊んでオンオフをきっちりとわける
オンとオフをきっちりわけるようにするのも、ストレス解消にはおすすめです。
仕事とプライベートが混同して上手く分けられないと、常に緊張感を持ちながら生活することになり、疲れてしまいやすいからです。
プライベートな時間は思い切り楽しむようにするとストレス発散にもなります。
また、オン・オフを切り替えることで、より仕事にも身が入りやすくなるでしょう。
介護職員の休日の過ごし方についてはこちらの記事もぜひご参照ください。
有給休暇の取得をする
溜まったストレスを解消するために、有給休暇を取得するのもいいでしょう。
介護業界は施設であれば基本的にシフト勤務が多いため、自分で自由に休日を取得することは難しい場合もあります。ですが、介護職の有給取得率は約66.8%となっており、全産業の平均約65.3%と比較するとやや高い水準となっています。
また、2019年の労働基準法の改正によって、企業は社員に年間5日以上の有給休暇を取得させることが義務付けられました。そのため、タイミングを見て有給休暇を取得し、ストレスが溜まる前にリフレッシュすることもおすすめです。
さらに、年間の休日数が多い職場を選ぶこともストレスを抱えず介護職として長く働くことができるポイントとなります。
介護職の年間休日については、こちらの記事にてくわしく解説していますのでご参照ください。
業務中にクスッと笑う
業務に追われイライラすることも多い介護現場ですが、その中でも介護現場の「あるあるエピソード」でクスッと笑ってみると気分転換になります。
笑うことでイライラしている自分から一瞬でも離れることができ、心身共にリラックスができます。
例えば、食事介助中にスプーンをご利用者様の口に運びながら、自分も一緒に口を開けていたり、ご利用者様が日常的に観ているNHKにくわしくなったりと、自分で自覚した時にクスッと笑ってしまう事があります。
そういった、介護職員ならではの日常的に起こるエピソードにクスッと笑ってみると自分に余裕ができ、イライラしていた気持ちがリセットできるでしょう。
介護職のイライラを解消をしたい方は、クスッと笑える「あるあるエピソード」をご紹介しているこちらの記事をぜひご一読ください。
まとめ
介護の仕事でずっとイライラしてしまうと空気が悪くなり、ご利用者様にとって不利益な結果となってしまいます。
また、ご自身にとっても常にマイナスな感情に支配されることになり、辛くなってしまうでしょう。
その状況を回避するために、ぜひ記事で紹介した方法を参考にしてみてください。
上手く自分の感情をコントロールしながら、お互いに気持ちよく介護ケアができるようにしていきましょう。
この記事を書いたのは・・・

中村 亜美/Webライター
保有資格:介護福祉士
特別養護老人ホームでユニットリーダーとして11年程勤務。
その後はフリーライターとして活動中。在宅介護者や介護事業者、介護職員向けのコラム・取材記事を執筆している。