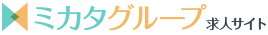「男性介護職員の強みって何?」
「介護業界で男性って必要とされてるの?」
女性職員が多い介護業界で、このような疑問をお持ちの方は多くいると思います。
介護業界は、女性が従事する比率が高い業界ですが、男性介護職員にしかできないこともあるため、需要が高まりつつあります。
本記事では、男性介護職員の強みを解説します。
男性介護職員が期待されている理由や、勤務して直面する問題とその解決方法なども紹介していきます。これから介護施設で勤務する男性や、介護業界への転職を検討している方は、本記事を最後までチェックしてみてください。
この記事の内容
男性介護職員の採用状況
令和3年度の公益財団法人介護労働安定センターによる介護労働実態調査では、女性の介護職員が73.9%なのに対して、男性の介護職員は26.1%となっています。
訪問介護員だと差は更に広がり、女性職員が87%に対して、男性職員は12.9%でした。
| 介護職員 | 訪問介護職員 | |
| 男性 | 26.1% | 12.9% |
| 女性 | 73.9% | 87.0% |
上記の点から見ても、男性介護職員の比率の低さがうかがえます。そのような理由から、次章で紹介する男性介護職員の強みを把握すると、着実にキャリアを積むことができます。
男性介護職員が期待されている理由
男性の介護職員が期待されている理由は、主にこの3つが考えられます。
- 力仕事をお願いできる
- 長期的な活躍が期待できる
- 男性のご利用者様をお願いできる
ご自身の強みを活かしたい方は、最後までチェックしてください。
力仕事をお願いできる
男性介護職員の強みは、力仕事をお願いできるところです。
男性と女性では筋肉のつき方が違うため、力仕事は男性の方が有利に働きます。介護以外の重いものの移動や、2人介助が必要なご利用者様の対応などを、安心して任せられます。
ただし、重いものを持つことは危険もあります。特に、腰への負担は気をつけなければいけません。ご自身の体を憂慮しておこなうようにしてください。
体の負担を少しでも軽減するためには、ボディメカニクスが有効です。こちらの記事も参考にしてみてください。
長期的な活躍が期待できる
男性介護職員は、長期的に活躍してくれる点でも期待されています。
介護の職場は福利厚生が充実しているところが多いです。結婚などの転機を迎えても、家族手当などが充実しているため安心して働き続けられます。
そのような視点からみても、男性介護職員は長期的な活躍ができると判断している方が多いです。
男性のご利用者様対応をお願いできる
男性ご利用者様の介助や対応をお願いできるのも男性介護職員の魅力の1つです。
男性のご利用者様は、女性のご利用者様と比べて大柄で力もあります。筋肉が多い分体重の重い方もいるので、女性介護職員のみで対応するには難しいこともあるでしょう。
なかでも、介助を強く拒否する男性ご利用者様がいると大変です。最悪の場合、力負けして怪我してしまうことも考えられます。そういった点からも、男性介護職員は頼りにされている存在です。
男性介護職員が勤務して悩むこと
男性介護職員が介護業界で働いていると、いくつかの点で悩むこともあります。特によく悩むのは以下の2つです。
- 男性介護職員が少ない
- 異性のご利用者様の介助がむずかしい
男性が介護職員として活躍していくなかで、この2点は悩むことが多い課題です。より男性介護職員の強みを理解して勤務に励みたい方は、ぜひ一読ください。
男性介護職員が少ない
介護業界全体を見ると、女性の介護職員に比べて男性介護職員は多くありません。
従事する母数が少ないため、男性介護職員は肩身の狭い思いをしている方も多いでしょう。ただし、男性介護職員に期待されていることもあります。男性介護職員にしかできないことを理解し行うことで、着実にキャリアを構築できることは魅力の1つです。
異性のご利用者様の介助がむずかしい
介護の仕事をしていると、性別問わず排泄介助や更衣介助を行います。
男性介護職員が女性のご利用者様を介助するとき難しい点がいくつかあります。
- 拒否される場合がある
- プライバシーへの配慮が必要
- 体の違いを理解できていないことがある
女性のご利用者様を介助するとき、上記の問題は起こりうる内容です。実際に、男性介護士に介護されたくないご利用者様はいらっしゃいます。その反面、男性介護職員の方が頼りがいがあって安心するというご利用者様もいます。
ご利用者様への配慮と、丁寧な介助をする必要があることは間違いありません。
男性が介護職員になるメリット3つ
男性が介護職員として活躍するメリットは、主に3つ考えられます。
- 業界が安定している
- 男性介護職員が増加している
- 処遇改善加算などの給与改定が進んでいる
上記の3つは、男性介護職員にとって大きなメリットです。3つのメリットを詳しく理解すると、介護業界で安心して働けるでしょう。
業界が安定している
現在、日本は少子高齢化のため、介護の人材を求めています。
しかし、需要と供給が合っていない状況で、介護職員の人手不足が深刻な業界でもあります。そのような理由から人材を求めている介護施設が多いため、就職できるチャンスが広がっています。
第9期介護保険事業計画の介護サービス見込み量等に基づき、厚生労働省が算出した介護職員の必要人数は徐々に増えています。以下の表をご参照ください。
| 年度 | 必要人数 |
| 2022年 | 215万人 |
| 2026年 | 約240万人 |
| 2040年 | 約272万人 |
このように、介護士の人材を必要としていることが分かります。介護職員としてキャリアを形成していきたい男性にとっても1つのチャンスと言えるでしょう。
ただし、どの施設でも就職できるわけではありません。各施設の採用基準を満たすことが大切です。しっかりと準備をして採用活動に臨んでください。
男性介護職員が増加している
さきほど、男性介護職員は女性の職員より少ないとお伝えしました。
女性の多い職場で働くのは、感性の違いからプレッシャーを感じる男性もいます。そのような理由から、同じ男性の介護職員がいると安心して働けるでしょう。
公益財団法人介護労働安定センターによる介護労働実態調査で、令和元年度の調査と令和4年度の調査を比較すると、少しずつ男性介護職員が増加しています。
以下が令和元年度と、令和4年度の比較表になります。
| 男性 | 女性 | |
| 令和元年 | 25.4% | 74.2% |
| 令和4年 | 26.5% | 72.8% |
※参考資料:交易財団法人 介護労働安定センター|令和4年度介護労働実態調査 事業所における介護労働実態調査結果報告書
データからも、男性介護職員の人数は増えていることが分かります。採用したい職場も多いので、積極的な応募をおすすめします。
処遇改善加算などの給与改定が進んでいる
厚生労働省は、人材不足を補うために、処遇改善加算を一本化し、さらなる介護職員の処遇改善を進めています。このように、職員の人材確保や地位向上のため、生活を心配せずに働ける環境構築を推進しています。
男性介護職員についてよくある質問
男性介護職員の強みを理解できても、気になることや不安を抱えている方もいると思います。
本章では、男性が介護する上で問題視されている以下の質問に、実体験を踏まえて回答します。
介護士は給料が低いって言われるけど本当ですか?
介護士の給料は、一般的な企業などと比べると決して高くないと思います。ただし、給与の問題は職場選びで解決できます。
同じ介護士でも、給与面は職場によって大幅に変化します。
そのため、面接に行く前は求人票の給与面や、待遇などをよくチェックしましょう。確認した上で、面接のときに求人票の詳細が間違いないか、確認すると尚良いでしょう。
介護士の給与について詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にご覧ください。
男性介護士です。仕事が原因で女性職員との人間関係に悩んでいます。
女性介護士との人間関係は、筆者もよく聞くトラブルの1つです。介護現場で仕事をしていて感じることは、女性と男性の仕事への取り組み方の違いです。
介護現場の仕事は、一度に複数の業務を同時に並行して行う必要があります。
たとえば、どなたかがトイレに座っている間に、別のご利用者様の更衣介助をするなどです。私の経験上、男性職員は同時並行でさまざまな業務をおこなうことを苦手とする方が多い傾向です。
反対に、女性職員はいくつかの業務を同時並行ですすめられる人が多く、すごい職員だと3つの業務を同時並行で行う猛者もいました。仕事が原因なのであれば、そのような部分で噛み合わないことがあったのかもしれません。
もし話せるならば、本人に聞いてみると良いでしょう。もし難しそうならば、職場の上司に相談して解決への糸口を見つけることをおすすめします。内容によってはデリケートな問題なので、慎重に取り組むよう注意してください。
まとめ
今回は、男性介護職員の強みを知りたい方に、介護士になるメリットや、男性の介護職員が期待されている理由を解説しました。
男性介護職員の強みは、頼り甲斐のある存在として一目置かれている点が考えられます。
男性の強みを活かして介護を行うことで、ご利用者様の信頼を得られるだけでなく、職場でも信頼される存在になれるでしょう。ぜひ介護職員としてのキャリアアップに活かしてください。
この記事を書いたのは・・・

かきざき/Webライター
保有資格:介護福祉士/終活ガイド1級/エンディングノートセミナー講師/食品衛生責任者
介護福祉士として介護職を13年経験。ライター歴3年。
特養でのユニットリーダー経験や、珍しい定期巡回の経験を活かして記事執筆しています!