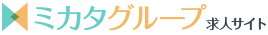介護職員として働くなかで、「地域包括支援センター」の仕事内容に興味を持つこともあるでしょう。地域包括支援センターは、高齢者の総合相談窓口として知られていますが、ほかにも多くの重要な役割を担っています。
本記事では、地域包括支援センターの具体的な仕事内容や職種ごとの役割、メリット・デメリットなど、介護経験者だからこそ気になる情報を解説します。将来のキャリアとして地域包括支援センターへの転職を考えている方は、ぜひ最後までお読みいただき、あなたのキャリアプランの参考にしてください。
この記事の内容
地域包括支援センターとは
地域包括支援センターは、市町村が設置主体となり、地域住民の保健医療の向上および福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設です。高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、介護、医療、福祉、権利擁護など、さまざまな面から包括的に支援する機関です。
人口2~3万人に1ヶ所程度を目安に、地域の実情に応じて(主に中学校区に)設置されています。市町村直営の場合は公務員が勤務している場合もありますが、業務委託の場合は委託先の法人職員が勤務しています。
地域包括支援センターの主な仕事内容は以下の4つです。
- 高齢者やその家族からの相談に応じる「総合相談支援」
- 高齢者の権利を守る「権利擁護」
- 地域のケアマネジャーをサポートする「包括的・継続的ケアマネジメント支援」
- 介護予防を推進する「介護予防ケアマネジメント」
これらの業務を担うため、センターには、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員(主任ケアマネジャー)といった専門職が、原則としてそれぞれ1名以上配置されています。
地域包括支援センターの仕事内容
ここでは、地域包括支援センターの4つの仕事内容について詳しく解説します。
1.総合相談支援
高齢者やその家族からの、介護、医療、福祉、生活に関するあらゆる相談の最初の窓口となるのが総合相談支援です。「最近物忘れがひどくなった母のことで相談したい」「介護保険サービスを利用したいがどうすれば良いかわからない」といった相談への対応です。
電話や訪問、来所による相談対応で、相談内容によって以下のような対応をします。
- 介護保険制度や医療機関などの情報提供
- ケアマネジャーや行政との連絡調整
- 虐待や認知症症状への対応など緊急度の判断
介護職員としてのコミュニケーションスキルやアセスメント能力を活かせる場面も多いでしょう。
2.権利擁護
高齢者が安心して暮らせるよう、その権利を守るための業務です。虐待や悪質な訪問販売などから高齢者を守る役割も担っています。
具体的には以下のとおりです。
- 成年後見制度の説明や手続きといった利用支援
- 高齢者虐待に関する相談や関係機関との連携、緊急時の保護など
- 消費者被害に関する情報提供や相談対応、関係機関との連携
- 講座や体操教室などを通した地域住民への啓発活動
介護職員としての経験は、相談者との信頼関係を構築しやすかったり、虐待の兆候に対しての感度が高かったりするため、これまでの経験を活かせるでしょう。
3.包括的・継続的ケアマネジメント支援
地域全体のケアマネジメントの質を高めるべく、ケアマネジャーが円滑に業務をおこなえるようサポートする業務です。具体的には、胃ろうやがん患者など医療的ニーズの高い高齢者や、認知症の症状の強い方、家族が問題を抱えている方など、支援困難ケースに対応しているケアマネジャーからの相談を受けることです。
必要に応じて地域ケア会議を開催し、他職種共同による課題解決へ向けた支援をおこないます。地域包括支援センターが主催する地域ケア会議は、個別の高齢者の問題解決を医療・介護・福祉の関係者や行政職員などの多職種で話し合う会議です。介護職員は他職種連携の考え方がすでに身についていることが多いため、ケアマネジャーや医療関係者との連携面で経験が役立つでしょう。
4.介護予防ケアマネジメント
高齢者が要介護状態になるのを防ぎ、自立した生活を継続できるよう支援する業務です。具体的には、以下のような業務です。
- 介護予防に関する相談対応
- 介護予防プランの作成
- 介護予防教室の開催や情報提供といった地域住民への啓発活動
- 介護予防プランに基づくサービスの実施状況の把握と評価
「最近、体力が落ちてきた」「閉じこもりがち」といった高齢者の状況を把握し、適切なサービスにつなげます。介護予防に関する知識や、高齢者の意欲を引き出すコミュニケーションスキルなど、介護職での経験が活かせるでしょう。
地域包括支援センターで働く3つの専門職と仕事内容
地域包括支援センターでは、主に保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員(主任ケアマネジャー)の3つの専門職が連携して働いています。ここでは、それぞれの仕事内容と必要な資格について解説します。
1.社会福祉士
高齢者やその家族の総合相談窓口となり、介護保険サービスだけでなく、医療、福祉など、さまざまな制度やサービスの情報提供、関係機関との連絡調整をおこないます。また、成年後見制度の利用支援や虐待防止など、権利擁護に関する業務も重要な役割です。
社会福祉士(国家資格)が必要であり、福祉系大学等での指定科目履修や、相談援助実務経験などが受験資格となります。
社会福祉士になる方法については、こちらの記事を参照してください。
2.主任介護支援専門員
地域のケアマネジャーへの指導・助言、困難事例への対応支援など、包括的・継続的ケアマネジメント支援の中心的な役割を担います。また、研修会の企画・運営などを通して、地域全体のケアマネジメントの質の向上を目指しています。
主任介護支援専門員研修の修了が必要であり、その前提として、介護支援専門員としての実務経験が必要です。介護職員の場合は、まずは介護支援専門員(ケアマネジャー資格)を取得することからはじめましょう。
ケアマネジャーになる方法については、こちらの記事をご参照ください。
3.保健師
主に介護予防ケアマネジメント業務を担当し、介護予防プランの作成、介護予防サービスの利用調整、健康相談などをおこないます。また、地域全体の健康課題の把握、健康教育、感染症予防対策など、公衆衛生の専門家としての役割も担っています。
保健師(国家資格)が必要であり、看護師免許取得後に保健師養成課程を修了するか、国家試験に合格する必要があります。介護職員から保健師を目指す場合は、まず看護師資格の取得が必要となるため、道のりは長いでしょう。
地域包括支援センターで働く3つのメリット
ここでは、地域包括支援センターで働くメリットについて、以下の3点を解説します。
- 地域の高齢者の生活に直接貢献できる
- 夜勤がなくワークライフバランスを保ちやすい
- 専門性を高められる
ひとつずつ見ていきましょう。
1.地域の高齢者の生活に直接貢献できる
地域包括支援センターで働くことで、高齢者やその家族の生活を直接支えることができます。具体的には、独居で生活に不安を抱える高齢者に必要なサービスを提案し、安心して暮らせるよう支援することで「あなたのおかげで助かった」と感謝の言葉をいただきやりがいを感じるでしょう。介護職員としての経験を活かし、地域貢献できるやりがいのある仕事です。
2.夜勤がなくワークライフバランスを保ちやすい
地域包括支援センターの仕事は、基本的に日勤のみで夜勤がありません。そのため、生活リズムを整えやすく、家族との時間や趣味、自己啓発など、プライベートの時間も大切にできます。
土日祝日が休みの場合も多く(自治体による)、仕事とプライベートを両立しやすい環境です。筆者が介護職員からケアマネジャーへ転職した際は、朝の目覚めが良くなり、休日を長く感じるといった変化を実感しました。夜勤が体力的に難しくなってきた方、規則正しい生活を送りたい方にとって、特に魅力的な働き方と言えるでしょう。
3.専門性を高められる
地域包括支援センターでは、それぞれの職種がそれぞれの専門性を活かしながら、さらに幅広い知識やスキルを習得できる環境です。研修制度も充実していることが多く、継続的なスキルアップが可能です。
例えば、困難ケースへの対応を通して相談援助技術を磨いたり、ケアマネジメントの知識を深めたりできます。経験を積むことで、将来的には管理者や指導者へのキャリアアップも目指せるでしょう。
地域包括支援センターで働く3つのデメリット
地域包括支援センターで働くことは、やりがいがある一方で、大変な側面もあります。ここでは「幅広い知識が必要」「困難ケースへの対応」「業務量が膨大になることもある」という3つのデメリットについて解説します。
1.幅広い知識が必要
地域包括支援センターでは、介護保険制度だけでなく、医療や福祉、権利擁護など、高齢者に関するあらゆる分野の知識が求められます。そのため、常に新しい情報を学び続ける姿勢が不可欠です。
例えば、介護保険制度の改定があれば、厚生労働省のホームページを見ながら膨大な資料に目を通すこともあります。成年後見制度を利用する高齢者の支援など、専門知識が必要な場面も多くあります。これらは自分から情報にアクセスしなければ身につくことはないため、積極的に学ぶ意欲が必要です。
2.困難ケースへの対応
地域包括支援センターには、虐待や貧困、認知症による徘徊など、複雑な問題を抱えた高齢者からの相談も寄せられます。こうした困難ケースの対応に精神的な負担を感じることもあるでしょう。
例えば、家族関係がこじれているケースでは、介入することで理不尽な叱責を受けることもあります。また、虐待を受けている高齢者を保護する際は、高齢者のケガを見たり、家族を引き離したりすることもあり、何ともいたたまれない気持ちになることもあります。一人で抱え込まず、チームで課題に立ち向かう意識が必要です。
3.業務量が膨大になることもある
地域包括支援センターの業務は、相談対応だけでなく、書類作成や関係機関との連絡調整、会議、研修など多岐にわたります。担当地区の高齢者人口や相談件数によっては、業務量が膨大になることもあるでしょう。
例えば、年度末の報告書作成時期には残業が続くことがあります。また、当番の際は休日に専用の携帯電話に連絡がくることもあります。業務を効率的に進める工夫や、周囲との協力が不可欠な仕事です。
介護職員が地域包括支援センターで働くための準備
介護職員が地域包括支援センターで働くためには、まず必要な資格を取得する必要があります。社会福祉士、主任介護支援専門員、保健師のいずれかの資格が必要ですが、介護職員からのキャリアアップとしては、まずはケアマネジャーを目指すのが最も現実的です。ケアマネジャーとしての実務経験を積みながら、主任介護支援専門員研修の受講を目指しましょう。
転職を考える際は、求人情報やセンターの情報を集めることも重要です。ハローワークや求人サイトをこまめにチェックするだけでなく、気になるセンターがあれば直接見学したり、話を聞いたりするのも良いでしょう。また、転職エージェントに登録し、非公開求人を紹介してもらったり、相談に乗ってもらったりするのも有効です。
「介護転職のミカタ」では、非公開求人の紹介だけでなく、キャリア相談や面接対策など、転職活動を全般的にサポートしています。費用はかからないため、お気軽にご相談ください。
まとめ
地域包括支援センターの仕事内容や職種、働くうえでのメリット・デメリット、介護職からの転職に必要な準備について解説しました。地域包括支援センターは、高齢者の生活を支えるやりがいのある仕事ですが、幅広い知識や困難ケースへの対応、業務量の多さなど、大変な側面もあります。しかし、介護職員としての経験を活かし、専門性を高めながらキャリアアップできる選択肢と言えるでしょう。
地域包括支援センターへの転職を考えている方は、「介護転職のミカタ」のような転職エージェントも活用しながら、準備を進めてみてはいかがでしょうか。
この記事を書いたのは・・・

さとひろ/Webライター
保有資格:ケアマネジャー/社会福祉士/介護福祉士/公認心理師
介護業界で22年の経験をもつ、特別養護老人ホームの現役ケアマネジャー兼生活相談員。介護職員・ケアマネジャー・生活相談員としての経験をもとにわかりやすい記事を執筆します。