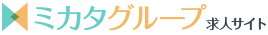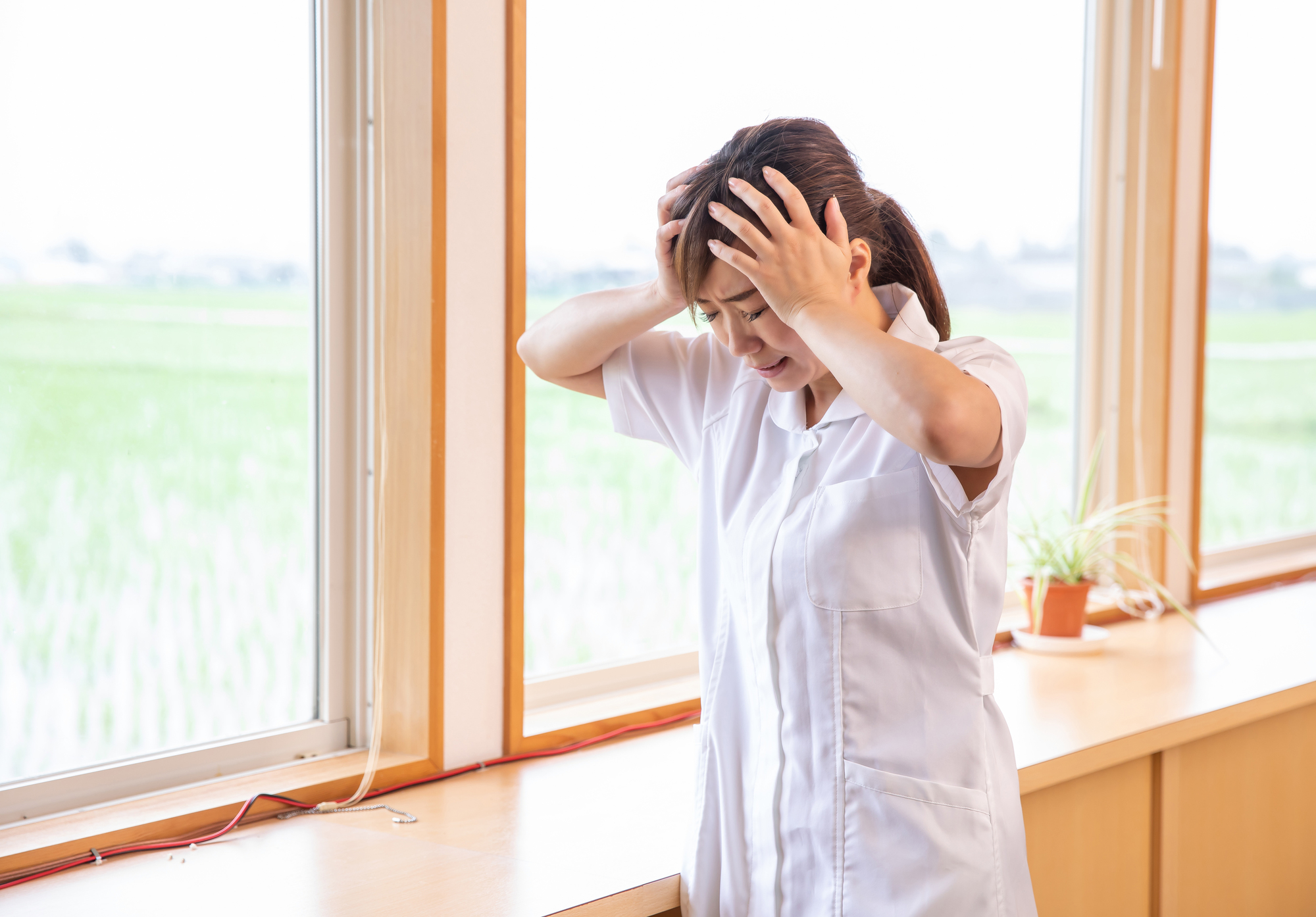
「日勤と夜勤の繰り返しで体が休まらない」
「もっと効率よく稼げない?」
介護の仕事を続けていると、このような悩みを抱える方もいるでしょう。介護業界では深刻な人材不足から、夜勤を担う職員の確保が課題となっており、働き方のひとつとして「夜勤専従」が注目されています。
夜勤専従とは、夜間の勤務だけを専門とする介護職員のことです。日勤はなく、8時間程度のショート夜勤や16時間程度のロング夜勤という働き方があります。
「夜勤ばかりできつそう」と思うかもしれませんが、収入面や時間の使い方など、メリットも少なくありません。本記事では、夜勤専従がきついと言われる理由や仕事内容、メリットなどを、現役で特養の職員をしている筆者が解説します。今後の働き方を検討している方はぜひ最後までお読みください。
この記事の内容
介護の夜勤専従がきついと言われる3つの理由
ここでは、介護の夜勤専従がきついと言われる理由を以下の3点にまとめています。
- 夜間業務の連続による疲労
- 夜勤専従ならではの孤独感とプレッシャー
- ほとんどない正社員の求人
ひとつずつみていきましょう。
夜間業務の連続による疲労
夜勤専従は、日勤とのローテーションがないため、夜勤が連続することによる肉体的な疲労や睡眠不足、生活リズムの乱れによる精神的な疲労が蓄積しやすい働き方です。
疲労が蓄積すると、集中力や判断力が低下します。その結果、転倒しそうなご利用者様を支えきれない、薬を飲ませる方を間違えるといった思わぬ事故につながるリスクが高まります。
夜勤専従ならではの孤独感とプレッシャー
夜勤専従は、日勤のスタッフと顔を合わせる機会が少なく、情報共有の不足や相談できる相手がいない状況に陥りやすいという側面があります。ご利用者様の日中の様子が分からず不安を感じたり、緊急時にたった一人で対応しなければならなかったりするプレッシャーは大きいものです。
こうした孤独感やプレッシャーは、精神的なストレスとなり、燃え尽き症候群につながる可能性も否定できません。
ほとんどない正社員の求人
夜勤専従の求人が、パートやアルバイト、派遣などの非正規雇用が中心のため、正社員の求人はほとんどありません。収入の不安定さや、福利厚生の不十分さなど、非正規雇用ならではのデメリットがあるのが現状です。
そのため、キャリアアップの難しさや、将来への不安を感じる方もいるでしょう。明けや休日に別の仕事をして効率的に稼ごうとする方もいますが、Wワークは健康管理に十分な注意が必要です。
介護の夜勤専従の仕事内容
夜勤専従の仕事内容は、コール対応や日中にできない雑務が中心です。ここでは、ショート夜勤とロング夜勤それぞれの業務の流れの一例を紹介します。
ショート夜勤の場合
| 時間 | 仕事内容 | ||
| 22:00 | 出勤、情報収集、申し送り、掃除、物品の消毒 | ||
| 23:00 | 巡回、排泄介助、体位変換、翌日の物品補充 | ||
| 0:00 | 休憩 | ||
| 1:00 | 巡回、体位変換、コール対応 | ||
| 3:00 | 記録、コール対応 | ||
| 5:00 | 起床介助、更衣介助 | ||
| 6:00 | 朝食準備 | ||
| 7:00 | 申し送り、退勤 | ||
ショート夜勤は8時間勤務で休憩が1時間の9時間拘束が一般的です。休憩を2時間にして10時間拘束としている施設もあるので面接時に確認する必要があります。
就寝介助が終わってからの出勤となるため食事介助はなく、排泄介助やコール対応が中心です。日中にできない掃除や物品補充などの雑務をおこなうこともあるでしょう。
勤務が8時間のため、夜勤明けの日は「明け」ではなく「休み」として扱われます。休日数を確保するため、夜勤明けの日に2日連続で夜勤をおこなう施設もあります。
(例)
| 1日目 | 2日目 | 3日目 | |
| ロング夜勤の場合 | 夜勤入り | 明け | 休み |
| ショート夜勤の場合 | 夜勤 | 夜勤 | 休み |
ロング夜勤の場合
| 時間 | 仕事内容 | ||
| 16:30 | 出勤、情報収集、申し送り | ||
| 17:00 | 離床、夕食準備、配膳 | ||
| 18:00 | 食事介助、服薬介助、口腔ケア | ||
| 19:00 | 就寝介助、排泄介助 | ||
| 20:00 | 就前薬介助、水分補給 | ||
| 21:00 | 夜勤者の夕食 | ||
| 22:00 | 掃除、物品の消毒・補充 | ||
| 23:00 | 巡回、排泄介助、体位変換、コール対応 | ||
| 0:00 | 休憩・仮眠 | ||
| 2:00 | 巡回、排泄介助、体位変換、コール対応 | ||
| 5:00 | 排泄介助、体位変換 | ||
| 6:00 | 起床介助、更衣介助 | ||
| 7:00 | 朝食準備、配膳、食事介助 | ||
| 8:00 | 申し送り、記録 | ||
| 9:30 | 退勤 | ||
ロング夜勤は夕食から朝食までの長時間の勤務となります。16時間勤務の2時間休憩で18時間拘束となることが多いでしょう。夜勤明けの日は「明け」として出勤扱いになります。
実際の仕事内容は施設によって少しずつ異なるため、面接や見学の際に質問をして確認すると良いでしょう。
介護職員の夜勤専従の給与相場
日本医療労働組合連合会がおこなった2024年介護施設夜勤実態調査結果によると、通常の夜勤手当はショート夜勤で4,559円、ロング夜勤で6,290円程度でした。
一方夜勤専従の場合は、一回の夜勤で15,000〜30,000円程度の収入になるため、月に10回夜勤をおこなえば、15万円〜30万円程度の収入になることもあります。夜勤専従の給与は、保有資格や経験年数、地域や施設の種別によって大きく異なるため、面接の場で確認することが大切です。
引用:2024年介護施設夜勤実態調査結果|日本医療労働組合連合会
介護の夜勤専従の3つのメリット
夜勤専従はきついというイメージがある一方で、以下のようなメリットもあります。
- 高収入が期待できる
- 自由な時間が増える
- 人間関係のストレスが少ない
それぞれみていきましょう。
1.高収入が期待できる
夜勤専従の最大の魅力は高い収入を得られる点です。夜勤専従の一回の夜勤の相場は15,000円から30,000円程度で、時給制の場合でも、深夜割増賃金により日勤よりも高い時給となります。
例えば、2024年度の最低賃金の全国平均1,055円をベースに計算すると、深夜時間帯(22時から5時まで)は1.25倍の1,319円になります。ショート夜勤の場合、以下のように計算できます。
- 22時から朝の5時までの6時間(休憩除く):1,319円×6時間=7,914円
- 5時から7時の2時間:1,055円×2時間=2,110円 合計:10,024円
このように、ショート夜勤でも1万円を超える収入を得られることもあります。短時間で高収入を得たい方や、効率的に稼ぎたい方には夜勤専従が向いています。
2.自由な時間が増える
夜勤専従は拘束時間が長く、2日間に跨って仕事をするため、出勤する回数が少なくてすみ、日中の時間を使いやすいというメリットがあります。日勤のように毎日出勤する必要がなく、週に2〜3回程度の勤務ですむことも多いでしょう。この時間を活用して、副業や趣味、家族との時間、資格取得のための勉強など、自分の好きなことに時間を使えます。
また、銀行や役所などの公共サービスを利用する時間も確保しやすく、日常生活の用事も平日の日中にすませられます。そのため、プライベートの時間を大切にしたい人や、Wワークで収入を増やしたい人には夜勤専従が向いているといえます
3.人間関係のストレスが少ない
夜勤は日勤に比べてスタッフの人数が少ない配置です。そのため、職場の人間関係に悩むことが少なく、精神的なストレスを軽減できると感じる人もいます。日中のように多くのスタッフやご利用者様と関わる必要がなく、比較的静かな環境で仕事に集中できると思う方も多くいます。
また、業務内容もご利用者様の見守りや定時の巡回など、ルーティン化されていることが多く、予測可能な業務が中心です。人間関係を気にせず一人で黙々と作業するのが好きな人には夜勤専従が向いています。
きついと言われる介護の夜勤専従を続けるポイント3選
夜勤専従は高収入や自由時間の確保などのメリットがある一方で、体力的・精神的な負担も大きい働き方です。ここでは、夜勤専従を長く続けるためのポイントを3つ紹介します。
体調管理と生活リズムの工夫
夜勤専従を続けるには、体調管理が最も重要です。勤務時間は一定ですが、夜間の業務は自分が思っているよりも身体的に負担がかかっています。夜勤前の「寝だめ」はかえって疲れる原因になるため避け、普段通りの睡眠時間を心がけましょう。夜勤明けは早めに睡眠をとり、午後からは通常通り活動することで生活リズムを整えられます。
睡眠環境の整備も大切です。遮光カーテンや耳栓を使用して、日中でも質の良い睡眠がとれるようにするとよいでしょう。また、食事は夜勤中に消化の良いものを少量ずつ摂ることで、眠気を防ぎつつ体調を維持できます。
なお、心身を癒す休日の過ごし方に関しては、こちらの記事をご参照ください。
緊急時対応の準備と知識の習得
夜勤は少人数で対応するため、緊急時の判断力や対応力が求められます。施設の緊急時対応マニュアルを事前にしっかり確認し、いざという時に冷静に対応できるよう準備しておく必要があります。
夜勤専従の場合は、日中の様子が記録や他のスタッフからの話でしかわからないため、特に確認が必要です。
緊急時には一人で判断しなければならない場面もあるため、日頃から「もしも」の状況をシミュレーションしておくとよいでしょう。オンコールの連絡先やその他の対応について確認しておくと、実際の場面でも冷静に対応できるようになります。
介護職員に必要な緊急時の対応についてはこちらの記事をご参照ください。
休憩時間の確保と工夫
労働基準法では、6時間を超える勤務では45分以上、8時間を超える勤務では1時間以上の休憩が必要と定められています。夜勤専従では特に休憩時間の確保が重要で、16時間に及ぶ長時間勤務の場合は、2時間以上の休憩時間を設けることが望ましいとされています。
休憩時間を有効に活用するためには、休憩室や仮眠室の環境を整えることも大切です。快適な休憩環境があれば、短時間でも効果的に休息を取ることができます。休憩時間中は業務から完全に離れ、リフレッシュする時間として活用しましょう。
まずは夜勤専従の求人を探してみよう
介護の夜勤専従は、「きつい」という側面がある一方で、高収入や自由時間の確保、人間関係のストレス軽減といった大きなメリットもあります。夜勤専従ならではの疲労や孤独感、正社員求人の少なさといった課題はありますが、体調管理の工夫や緊急時対応の準備、休憩時間の確保などの対策を講じることで長く続けることも可能です。
まずは夜勤専従の求人情報を調べ、施設見学や面接で具体的な勤務条件を確認してみましょう。転職支援サービス「介護転職のミカタ」では、専門の担当者が、あなたの意向に沿った求人をご案内します。まずはお気軽に登録してみましょう。
この記事を書いたのは・・・

さとひろ/Webライター
保有資格:ケアマネジャー/社会福祉士/介護福祉士/公認心理師
介護業界で22年の経験をもつ、特別養護老人ホームの現役ケアマネジャー兼生活相談員。介護職員・ケアマネジャー・生活相談員としての経験をもとにわかりやすい記事を執筆します。