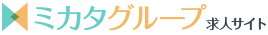「最近食欲がなくなってきた」
「最近、外に出るのが億劫になってきた」
加齢にともない、このような状態が感じられたら、フレイルの可能性があります。
フレイルとは健康と要介護の中間状態を指し、フレイルの対策を取らないと要介護状態に陥る危険性がありえるのです。
本記事ではフレイルの種類とチェック方法、お手軽に始められる予防法などについてまとめました。運動や食事の改善、社会交流といったフレイルの対策を早期に始めれば、将来の介護予防につながりますので、ぜひ参考にしてください。
この記事の内容
フレイルとは要介護の一歩手前
フレイルとは、健康な状態と介護が必要な状態の中間の段階です。年齢を重ねるにつれて、筋力低下や疲労感の増加、外出を控える傾向など身体機能や活動性の低下が生じ、要介護になるリスクが高い状態です。
フレイルは、2014年に日本老年医学会が提唱した言葉で、英語の「Frailty:虚弱」が語源とされています。また、特徴によって身体的フレイル、精神・心理的フレイル、社会的フレイルの3つに分かれます。フレイルについて、具体的にみていきましょう。
3つのフレイル
フレイルは身体的フレイル、精神・心理的フレイル、社会的フレイルの3つに分かれます。特徴は以下の通りです。
身体的フレイル
身体的フレイルとは、骨や関節の障害により歩くといった移動機能が低下したり、筋肉が衰えたりする状態です。筋肉の衰えは、歩行速度の低下や握力の低下といった、さまざまな身体機能に影響を及ぼします。
また、身体機能の低下により活動する機会が減ると、心臓や呼吸器といった内臓機能の低下にもつながりかねません。
精神・心理的フレイル
精神心理的フレイルとは仕事を定年で退職したり、パートナーを失ったりといった環境の変化で起こる、高齢期のうつ状態や軽度の認知症の状態を指します。物忘れや気分の落ち込みなどの心の変化が特徴です。
社会的フレイル
社会的フレイルとは年を重ねるに連れて社会とのつながりが少なくなることで生じる状態です。一人暮らしにより人と接する機会が減少したり食生活のバランスが崩れたりすることにより起こります。
また、経済的な困窮による引きこもりの影響もみられています。
フレイルは上記で述べた3つの要素が互いに関係し合い、違いに悪影響を及ぼす可能性も少なくありません。
フレイルと介護予防の関係
フレイルは、健康な状態と要介護状態の中間の段階であるため、何も対策をとらずに放置していると、要介護状態になる恐れがあるでしょう。
また、病気の治療や、食生活・運動習慣などの生活習慣が整えば、フレイルの進行を緩め健康な状態に戻せることもわかっています。自分がフレイルに該当するか早めに気づき、早期の対策が要介護状態を予防する上で大切です。
あなたのフレイル度をチェック!
加齢にともない、自分がフレイルになっているのか気になる方も少なくないでしょう。
フレイルの状態や何をチェックするかの確認は、現在の健康状態を把握し必要に応じてフレイル対策を進める上で非常に大切です。チェック方法について、具体的にみていきましょう。
フレイルを疑う状態
フレイルの特徴には以下のようなものがあります。
・おいしいものが食べられなくなった
・疲れやすく何をするのも面倒
・体重が以前よりも減ってきた
・以前より歩くスピードが遅くなった
上記のような状態が現在みられていれば、フレイルを疑う必要があるでしょう。
フレイルかどうかチェックしてみよう
以下のチェック表は、令和元年に厚生労働省が高齢者を対象にフレイルの可能性を把握するために作成したものです。
以下の項目を定期的にチェックし、現在の健康状態を把握しましょう。
| 類型名 | No. | 質問文 | 回答 | ||||
| 健康状態 | 1 | あなたの現在の健康状態はいかがですか | ①よい ②まあよい ③ふつう ④あまりよくない ⑤よくない | ||||
| 心の健康状態 | 2 | 毎日の生活に満足していますか | ①満足 ②やや満足 ③やや不満 ④不満 | ||||
| 食習慣 | 3 | 1日3食きちんと食べていますか | ①はい ②いいえ | ||||
| 口腔機能 | 4 | 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか ※さきいか、たくあんなど | ①はい ②いいえ | ||||
| 5 | お茶や汁物等でむせることがありますか | ①はい ②いいえ | |||||
| 体重変化 | 6 | 6ヶ月間で2~3kg以上の体重減少がありましたか | ①はい ②いいえ | ||||
| 運動・転倒 | 7 | 以前に比べて歩く速度が遅くなってきたと思いますか | ①はい ②いいえ | ||||
| 8 | この1年間に転んだことがありますか | ①はい ②いいえ | |||||
| 9 | ウォーキングなどの運動を週に1回以上していますか | ①はい ②いいえ | |||||
| 認知機能 | 10 | 周りの人から「いつも同じことを聞く」などの物忘れがあると言われていますか | ①はい ②いいえ | ||||
| 11 | 今日が何月何日かわからない時がありますか | ①はい ②いいえ | |||||
| 喫煙 | 12 | あなたはたばこを吸いますか | ①吸っている ②吸っていない ③やめた | ||||
| 社会参加 | 13 | 週に1回以上は外出していますか | ①はい ②いいえ | ||||
| 14 | ふだんから家族や友人との付き合いがありますか | ①はい ②いいえ | |||||
| ソーシャルサポート | 15 | 体調が悪いときに、身近に相談できる人がいますか | ①はい ②いいえ | ||||
今から始めるフレイル予防
フレイル予防となる3つの柱である、食事・運動・社会参加についてそれぞれご紹介します。
フレイル予防となる食事
フレイルを予防するには朝昼晩の3食をしっかり摂ることが大切です。主食、主菜、副菜を組み合わせて、いろいろな種類の食品を食べるよう心がけましょう。
高齢になるとたんぱく質が不足しやすいです。たんぱく質は筋肉を作る栄養源なので、適度なたんぱく質の摂取は筋力の低下を防ぎ、転倒や骨折の予防にもつながります。
肉や魚、卵などのさまざまな食品から、たんぱく質をしっかり摂りつつ、バランスのよい食事を心がけましょう
フレイル予防におすすめの運動
フレイル予防におすすめの運動は、ウォーキングや筋トレ、ストレッチなどです。どれか1つをおこなうのではなく、組み合わせて行い運動習慣をつけましょう。各運動のポイントは以下の通りです。
- ウォーキング
ゆっくりのペースでもよいので、まずは10分間のウォーキングから始めてみましょう。ウォーキングは道具を使わず、手軽にできる有酸素運動の1つです。外を歩くことで、体だけでなく心のリフレッシュにもつながるでしょう。
ウォーキングに慣れてきたら、週に150分以上を目標に歩きましょう。また、1人で歩くのもよいですが、夫婦や友人同士で歩くと、目標を共有できより続けられやすくなるのでおすすめです。
- 筋トレ
おすすめの筋トレは「椅子スクワット」です。太ももの筋肉を強化し、膝の痛み予防にもつながります。椅子に座り、手を使わずにゆっくりと立ち座りをおこないましょう。ゆっくりおこなうと、筋肉に負荷がかかるのを確認できます。
10〜20回を目標に実施しましょう。
- ストレッチ
運動前後でストレッチを取り入れることも大切です。関節痛や筋肉痛の予防にもつながります。首、腕、体幹、足などのストレッチを組み合わせて行いましょう。
1日10分程度、週に2日以上を目安に取り組んでみましょう。
ストレッチについては以下の記事でもご紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
フレイル予防のための社会参加
フレイル予防には食事や運動に加え社会参加も欠かせません。地域のボランティアや、趣味のサークルに参加するなど、外出の機会を増やし人と交流する機会を設けましょう。
社会参加はフレイル予防に加え認知症の予防にもなります。人との交流はさまざまな認知機能を必要とします。
まずは近所の方との挨拶から始めてもよいでしょう。できることから少しずつ始め、無理なく続けられる活動を見つけて、健康寿命を延ばしましょう。
まとめ|フレイルを予防し介護予防に繋げよう
フレイルは身体的、精神心理的、社会的な3つの側面から成り立っており、早めの予防が要介護状態を防ぎます。
フレイル予防は、食事・運動・社会参加の3つをバランスよく実践することで、健康寿命を延ばし、介護予防につながります。まずはできることから始め、無理なく継続することが大切です。
介護現場でもフレイル予防は利用者様の健康を維持する上で非常に大切です。地域の高齢者の健康を支え、感謝されやりがいのある介護の仕事を「介護転職のミカタ」で見つけてみませんか。
この記事を書いたのは・・・
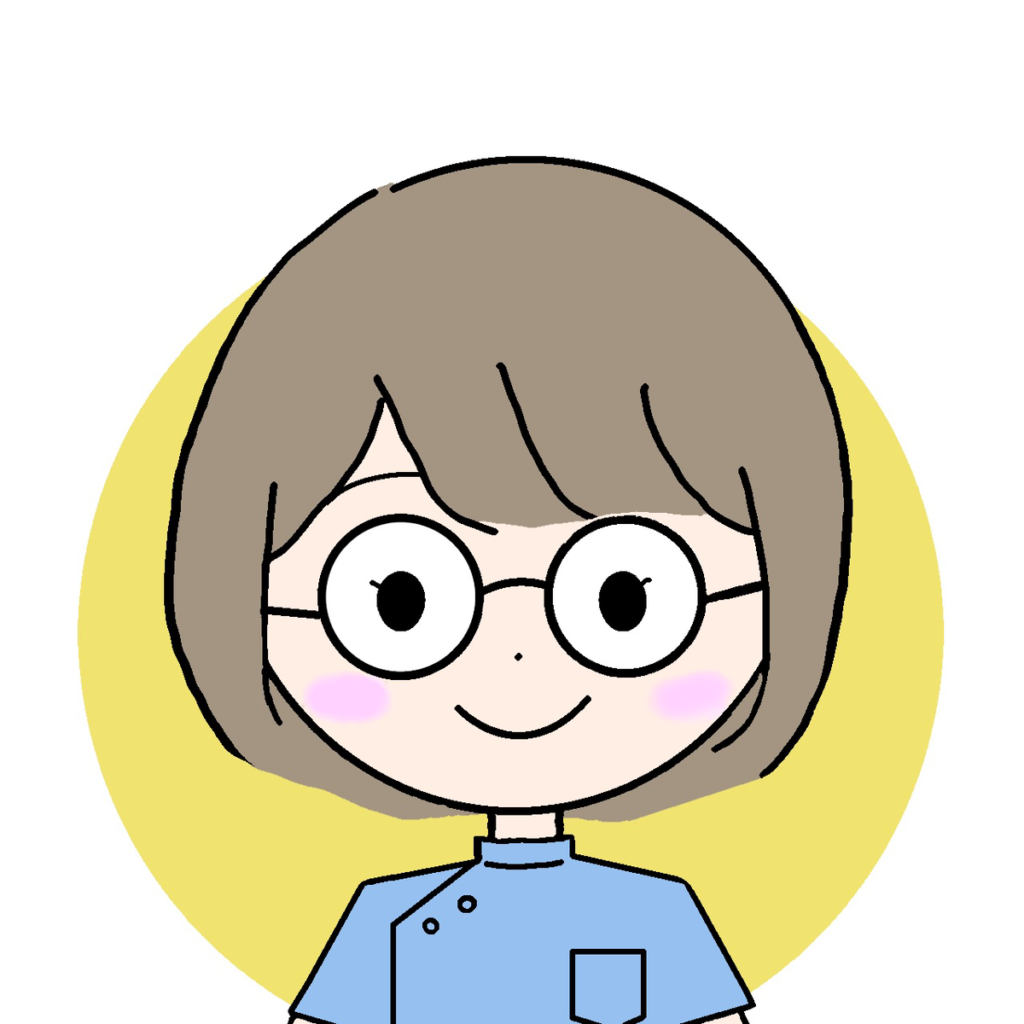
椎野みいの/Webライター
保有資格:作業療法士/福祉住環境コーディネーター/福祉用具プランナー/認定心理師
病院、介護老人保健施設、リハビリ専門学校を経て、現在は特別養護老人ホームにて機能訓練指導官として勤務中。