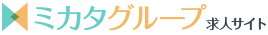「ご利用者様のAさんが介護を拒否されることが多く、どう対すればよいか悩む…」
「今日一人夜勤だけど、いつも介護拒否があるAさんにうまく対応できるか不安…」
このように、介護施設で介護拒否をされるご利用者様への対応に、悩んだ経験がある方は多いのではないでしょうか。
介護拒否を改善するためには、ご利用者様のペースや背景を尊重した関わり方が大切です。
本記事では、介護拒否に対する具体的な対応方法や、介護拒否が起こる理由についてくわしく解説します。
介護拒否の対応スキルを身につけることで、介護に自信を持てるようにまとめようまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
この記事の内容
介護拒否の対応
介護拒否があるご利用者様に無理やり介護をおこなうと、かえって拒否が強くなり逆効果になることがあります。
介護拒否が見られた場合は、まずご本人の動きを待つことが大切です。また、声かけの工夫や信頼関係を築くことで、介護拒否が和らぐ場合もあります。
本章では介護拒否への具体的な対応方法について、くわしくご紹介します。ご利用者様の介護拒否でお困りの方は、ぜひ参考にしてください。
本人の動きを待つ
ご利用者様に介護拒否が見られたときは、ご本人の動きを待つことで拒否が和らぐことがあります。
たとえば、ご利用者様の体調がすぐれなかったり、今は動きたくないと感じていたりする場合、介護を受けたくないタイミングがあるものです。
ご利用者様のペースを無視して介護を進めると、不快な気持ちになり、さらに拒否につながることもあるでしょう。
無理に介護を進めるのではなく、ご利用者様の動きを待ちましょう。
また、状況によっては少し時間をおいて再度声をかけると、うまくいく場合もあるため、ご利用者様のペースを尊重することが大切です。
声かけの仕方を工夫する
声かけの仕方を変えるだけで、介護拒否が改善される場合もあります。
介護をはじめる前に「これから何をするのか」を伝えると、ご利用者様も安心されることがあります。
たとえば、移乗介助をおこなう場合、いきなりご利用者様を動かすのではなく、まずは説明をしましょう。「今からベッドから車椅子に移りますね」など、これからおこなう介助についての説明があれば、ご利用者様も安心感を持てるかもしれません。
また、「前にかがみますね」や「腕を上に上げますね」など、具体的な動きを一つずつ伝えることも大切です。動きを具体的に伝えることで、ご利用者様が次に何をされるのか予測でき、不安が軽減される場合もあります。
信頼関係を作る
ご利用者様との信頼関係が築けていないことが、介護拒否につながるケースも少なくありません。たとえば、はじめて介護を受ける方は、体に触られることに抵抗を感じる場合もあるでしょう。
信頼関係を築くために、普段からご利用者様と関わる時間を増やすことが大切です。筆者は作業療法士ですが、リハビリの時間以外にもご利用者様の居室を訪れ、様子をうかがったり世間話をしたりしています。
普段から関わる機会を増やすことで、ご利用者様に顔や名前を覚えていただき、「いつも来てくれるこの人なら安心して任せられる」と感じていただくことが目的です。
最初はリハビリを拒否されていたご利用者様も、関わる時間を増やすことで、次第に受け入れてくださるようになった方がいらっしゃいました。
介護が必要な時だけでなく、定期的にご利用者様の居室を訪れ「困っていることはありませんか」「体調はお変わりないですか」などと声をかけてみましょう。
介護拒否をする理由
介護を拒否する理由には、さまざまなものがあります。介護拒否があるからといって、関わりを減らすのではなく、なぜ介護拒否が起こるのか理由を考えてみましょう。
理由を理解することで、より適切な対応方法を検討できるでしょう。本章では介護拒否をのおもな理由について、くわしく解説します。
自尊心や羞恥心があるから
ご利用者様の中には「まだ自分でできる、自分でやりたい」と思っている方や、「人に介護されるのは恥ずかしい」と感じている方も少なくありません。
とくに介護職員が異性の場合、羞恥心が強まる方もいらっしゃいます。
ご利用者様の性格や気持ちについて、事前にご家族様に確認しておくと、介護拒否の背景がわかる場合もあるためおすすめです。
迷惑をかけたくないから
介護職員にできるだけ迷惑をかけたくないという思いから、介護を拒否される方もいらっしゃいます。スタッフが慌ただしく働いている様子を見て、自分が負担になるのではと気を使い、介護を断る方も少なくありません。
すべてを介助するのではなく、ご利用者様にも手伝ってもらう旨を伝えてみましょう。「この部分は私が手伝いますので、この部分はご自身でやっていただいてもよろしいですか」などと、ご利用者様にも協力をお願いする声かけをすると、遠慮が軽減されるかもしれません。
疲労感があるから
体が辛かったり、痛みがあったりすることで、介護を拒否される方もいらっしゃいます。中には、疲労感をうまく伝えられず、その結果、介護拒否のように見えてしまう方もいるでしょう。
ご利用者様の体調やバイタルサイン、顔色などをしっかり観察し、いつもと違う様子がないか気を配りましょう。
認知機能の低下がある
認知機能の低下が原因で、介護拒否される方も少なくありません。
認知機能が低下すると、今いる場所がどこなのかわからなくなったり、介護職員が自分を介護してくれる人だと認識できなくなったりします。
また、介護が必要な自身の体の状態について把握できず、介護は必要ないと思い込んでいる方も少なくありません。
たとえば、認知機能の低下によって帰宅願望が強い方に無理に介護をおこなうと、興奮や暴力につながる場合もあるでしょう。
認知機能が低下している方には、安心できる環境を整えることが大切です。ご利用者様の心理状態をくみ取り、ご利用者様が安心できるような声かけや、環境づくりを心がけましょう。
介護拒否に関するよくある質問
本章では介護拒否に関する、よくある質問についてまとめました。
介護する側が介護拒否をするとネグレクトになるのか?
介護職員など介護をおこなう側が、ご利用者様の介護拒否を理由に必要な介護を提供しなかった場合、ネグレクト*に該当する可能性があります。
介護拒否があるご利用者様に対しては、介護職員が専門職として「介護を受けない場合の危険性や介護の必要性」について説明し、納得してもらえるように説得する必要があります。
また、説明と説得を怠り、必要なケアをしなかったことが原因で事故が起こってしまった場合、介護事業者側に責任を問われるケースもあるでしょう。
ネグレクト*:世話をする責任があるのに、世話を放棄・放任すること
特定の職員に介護拒否をする理由は?
ご利用者様が特定の職員にだけ介護拒否をされる背景には、いくつかの心理的・環境的な原因が考えられます。
たとえば、職員の表情に笑顔がなかったり、言葉や態度がきつかったりすると、ご利用者様の不安につながるでしょう。
筆者も以前、ご利用者様から特定の職員に対し、「あの人は口調がきついから、関わりたくない」と相談を受けたことがあります。その職員は決してきつく伝えたという自覚はなかったようですが、言葉の選び方や声の大きさなどがご利用者様にとって不快に感じられたようです。
話し方の癖は自分では気づきにくいものです。声のトーンや話す速さ、説明の仕方など自分の話し方について、普段から「どう話せば相手にとって聞き取りやすいか」を意識していれば、このような相談は起こらなかったかもしれません。
ほかにも、介護職員が自信なさそうに見えると、「この人に任せて大丈夫だろうか」と心配になり、不信感から介護拒否を示す方もいるはずです。
さらに、介護職員の性別や年齢によって、介護を受けることに抵抗を感じる方もいらっしゃいます。
介護拒否の背景には必ず理由があるので、ご利用者様の気持ちや状況をていねいに観察し、対応を検討することが大切です。
介護拒否の対応スキルをつけて仕事に自信をもとう
ご利用者様の介護拒否には必ず何らかの原因があり、その原因を分析して適切に対応することで、介護拒否が軽減される可能性があります。
なぜ介護拒否されるのか、利用者様の性格や精神的・身体的状況など多方面から分析し、対応スキルを身につけましょう。
介護拒否の対応スキルが身につくと、今まで以上に介護に対する自信がつき新しいことにも挑戦できるかもしれません。
本記事を参考に、介護拒否の対応スキルを身につけて、ご利用者様へ質の高いケアを提供していきましょう。
この記事を書いたのは・・・
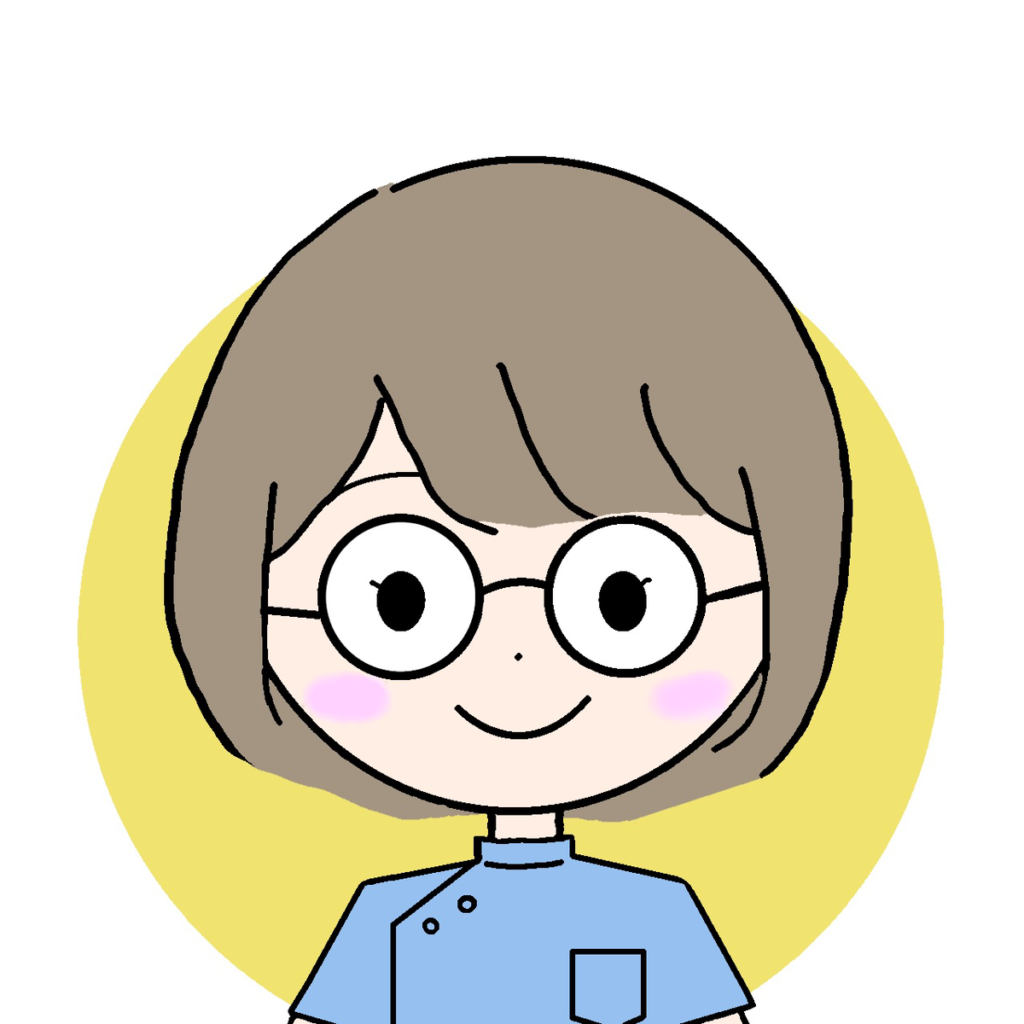
椎野みいの/Webライター
保有資格:作業療法士/福祉住環境コーディネーター/福祉用具プランナー/認定心理師
病院、介護老人保健施設、リハビリ専門学校を経て、現在は特別養護老人ホームにて機能訓練指導官として勤務中。