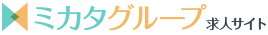「最近足腰が弱ってきたけど、もしかしてロコモティブシンドロームかも…」
足腰の筋力が衰えてくると、転倒や骨折をしてしまうのではないかと不安になる方も少なくないでしょう。
筋力やバランス能力などの衰えや、骨や関節の病気はロコモティブシンドロームの原因となります。また、ロコモティブシンドロームは要介護の要因となり、健康寿命を縮める可能性があるでしょう。
本記事では、ロコモティブシンドロームの概要から原因、ロコモ度チェック、予防法までを、作業療法士の筆者が詳しくご紹介します。本記事を参考に運動習慣や食生活を見直し、早期のロコモ予防につなげましょう。
この記事の内容
ロコモティブシンドローム(ロコモ)とは
ロコモティブシンドローム(以下、ロコモ)は、骨や関節、筋肉といった運動器が衰え、「立つ」「歩く」といった移動機能が低下した状態を意味します。2007年に日本整形外科学会が提唱した概念です。
要支援や要介護状態を招く原因の1つでもあり、健康寿命を縮めるリスクがあるため、早期からの対策が重要です。
本章ではロコモの概要についてまとめています。ロコモについて具体的な概要を知り、早期のロコモ予防につなげていきましょう。
運動器の障害が生活に支障をきたした状態
ロコモティブシンドローム(以下、ロコモ)とは、日本整形外科学会が提唱した概念で、以下の状態を指します。
運動器の障害のために、移動機能の低下をきたした状態
引用:ロコモティブシンドローム予防啓発公式サイト|日本整形外科学会
運動器は、骨・関節・筋肉・神経といった体を動かす組織で構成されています。
運動器の障害とは骨折や転倒、関節の病気などを指し、運動器の障害により立ったり歩いたりといった移動機能が低下した状態がロコモです。
20代からロコモは進行
ロコモの進行は20代からすでに始まっているとされています。とくに足の筋肉量は腕の筋肉量よりも減少しやすく、男女共に20代から減少を認めています。
また、ロコモは高齢者も問題とイメージされがちですが、実は40代の5人中4人はロコモ予備軍と言われているのです。近年では、小学生くらいの子どもでもロコモ予備軍が指摘されており、どの世代でもロコモが健康に影響する可能性があるといえるでしょう。
ロコモが原因で要介護状態に
ロコモは要支援や要介護の状態を招くきっかけになりかねません。
厚生労働省の「2022年国民生活基礎調査の概況」によると、介護や支援が必要となった主な原因の第3位は、骨折や転倒などのロコモ関連でした。
ロコモが原因で要介護状態や寝たきりの時間が長くなると、身体機能だけでなく人との交流や精神面の低下にも影響を及ぼす可能性がありえます。
活動量が減ると認知機能の低下にも影響しやすく、認知症など運動器以外の病気を引き起こす可能性も少なくありません。
ロコモの原因
ロコモの原因には以下の3つがあげられます。
- 筋力の低下
- バランス能力の低下
- 骨や関節の病気
ロコモの予防に取り組む中で、原因の理解は非常に重要です。各原因について詳しくみていきましょう。
筋力の低下
ロコモの原因の一つは筋力の低下です。とくに体幹や足の筋力低下により、立つ・歩くなどの基本的な動きが困難になり、日常生活での活動量が低下します。活動量が減ると、筋力の低下はさらに進むため、悪循環を招きます。
また、筋力低下により骨や関節への負担も増加するため、変形性関節症や脊柱管狭窄症などの運動器疾患のリスクも高まるでしょう。筋力低下の予防はロコモ予防を考える上で、大変重要です。
バランス能力の低下
ロコモの原因には、バランス能力の低下もあげられます。高齢になると筋力の低下に加え、重心の動揺も増え、猫背といった姿勢の悪化も加わり、バランス能力が低下しやすいです。
また、バランスを崩した際は倒れないよう足が一歩でたり、とっさに手が出たりといった姿勢を保つ反射がみられます。高齢になると反射能力も低下するため、転倒や骨折のリスクが高まります。
骨や関節の病気
ロコモに関連しやすい病気に、変形性膝関節症、変形性脊椎症、骨粗鬆症、脊柱管狭窄症などがあります。どれも運動器疾患であり、高齢者がなりやすい病気です。
上記の病気は症状として痛みや痺れ、筋力低下、バランス能力の低下を招く可能性があります。また、高齢者の場合、上記の病気を重複して持っているケースも決して少なくありません。
運動器疾患になると生活に大きく支障をきたすため、早めに病院で適切な診断や治療を受ける必要があるでしょう。
あなたのロコモ度をチェックしよう
日本整形外科学会が運営するロコモの予防啓発公式サイト「ロコモオンライン」では、ロコモに該当するかについて、チェック方法を紹介しています。
本章ではロコモ度テストの内2つをご紹介しますので、ロコモに当てはまるかを確認してみましょう。
参照:日本整形外科学会:ロコモティブシンドローム予防啓発公式サイト ロコモオンライン
立ち上がりテスト
立ち上がりテストは下肢の筋力を測るテストです。まずは両足、次に片足の順で台から立ち上がります。
<準備するもの>
- 40cm、30cm、20cm、10cmの台
<実施方法>
- まず40cmの台に両手を組んだ状態で座ります。両足は肩幅程度に広げ、床に対し脛(すね)が70度の角度(40cm台の場合)になる位置に脚を置きます。
- 反動をつけずに立ち上がり、立ち上がったらそのまま3秒間保持します。
- 両足での立ち上がりができたら、次は片脚で立ち上がります。両手を組んで台に座り左右どちらかの脚を上げ、上げたほうの脚の膝を軽く曲げて床から離します。
- 反動をつけずに立ち上がり、立ち上がったら3秒間保持します。立ち上がったら、反対の脚でもおこないます。
- 40cm台から片脚でも立ち上がり、左右どちらの脚でも立ち上がれたら、30cm台、20cm台、10cm台の順に低い台に移ります。左右とも片脚で立ち上がれた一番低い台がテスト結果になります。
- 片脚で40cm台から立ち上がれなければ、30cm台から両脚での立ち上がりテストを実施します。両脚で立ち上がれたら10cmずつ低い台に移り、両脚で立ち上がれた一番低い台がテスト結果になります。
<注意点>
- 無理をしないように注意する
- テスト中に膝の痛みが出現しそうな場合は中止する
- 反動をつけると、バランスを崩し後方に転倒する危険性がある
参照:日本整形外科学会:ロコモティブシンドローム予防啓発公式サイト ロコモオンライン|立ち上がりテスト
2ステップテスト
2ステップテストは、歩幅の測定結果から下肢の筋力やバランス能力、柔軟性などの歩行能力を評価するテストです。
<準備するもの>
- テープ
- メジャー
<実施方法>
- スタートラインを決め、スタートラインに立ちます。この際、両足のつま先は合わせます。
- できる限り大股で2歩歩いた後、両足をそろえます。
この際、バランスを崩した場合は失敗となるため、やり直してください。
- 2歩分の歩幅(スタートラインから、着地点のつま先まで)を測定します。
- 1〜3を2回実施し、距離が長いほうの記録を採用します。
- 以下の計算式を用いて、2ステップ値を算出します。
2歩幅(cm) ÷ 身長(cm) = 2ステップ値
<注意点>
- 介助者のもとで実施する
- 滑りにくい床で実施する
- 準備運動をおこなってから実施する
- バランスを崩さない程度におこなう
- ジャンプはおこなわない
参照:日本整形外科学会:ロコモティブシンドローム予防啓発公式サイト ロコモオンライン|2ステップテスト
各テストの結果判定
立ち上がりテストと2ステップテストの、結果の判定方法は以下の通りです。ロコモ度は数字が上がるに連れて、移動機能の低下が増します。
立ち上がりテストの結果の判定
立ち上がりテストの測定結果に対する判定は次の通りです。
| 測定結果 | 判定 |
| どちらか一方の足で40cmの台から立ち上がれないが、両足で20mの台から立ち上がれる | ロコモ度1:異動機能の低下が始まっている状態 |
| 両足で20cmの台から立ち上がれないが、30cmの台から立ち上がれる | ロコモ度2:異動機能の低下が進行している状態 |
| 両足で30cmの台から立ち上がれない | ロコモ度3:異動機能の低下が進行し、社会参加に支障をきたしている状態 |
2ステップテストの結果判定
2ステップテストの結果判定は2ステップ値をもとにおこないます。判定結果は以下の通りです。
| 2ステップ値 | 判定 |
| 1.1以上1.3未満の場合 | ロコモ度1: 移動機能の低下が始まっている状態 |
| 0.9以上1.1未満の場合 | ロコモ度2: 移動機能の低下が進行している状態 |
| 0.9未満の場合 | ロコモ度3: 移動機能の低下が進行し、社会参加に支障をきたしている状態 |
今から始めるロコモの予防法
ロコモ度チェックでロコモ度が高い方は、早めに予防をはじめましょう。ロコモの予防は、早ければ早いほど良いとされています。足腰の筋力低下が気になっている今こそ、予防のはじめどきです。
ロコモの主な予防法は以下の2つです。
- 運動習慣を身につける
- 食生活を整える
予防法について、具体的にみていきましょう。
運動習慣を身につける
若い年代から筋力の衰えは始まるため、ロコモ予防では早期に運動習慣を身につけることが大切です。筋力やバランス能力を維持できれば、転倒や骨折のリスクが低くなるでしょう。
健康的な生活の継続は、高齢者にとって負担となりやすい医療費や介護費などの費用も抑えられます。
気軽にできるおすすめの運動はスクワットです。下肢の筋肉やお尻周りの筋肉を鍛えられます。また、道具を使わず、場所を選ばずに実施できます。方法は次の通りです。
- 両足を肩幅と同じくらい広げて立つ
- ゆっくりと5秒かけて膝を曲げる。この際、膝がつま先より前に出ないように、注意する
- ゆっくり5秒かけて膝を伸ばし、もとの状態に戻る
上記の方法で、10〜15回を目安におこないましょう。スクワットはゆっくりと動くことがポイントです。ゆっくり動くことで、どの筋肉がはたらいているかを意識できます。
実施時は息を止めないように注意が必要です。高齢者の場合、運動に集中し過ぎるあまり、息を止めてしまう方も少なくないため、適宜声掛けをおこないましょう。
食生活を整える
ロコモ予防を意識する場合、運動と食事はセットで取り入れましょう。運動を積極的におこなっても、栄養が偏ってしまうと筋肉を鍛えることはできません。
筋肉を作るにはタンパク質の摂取が必要です。肉や魚、大豆製品、卵などはタンパク質が多く含まれています。
ただし、タンパク質を多く取り過ぎると、カロリーが増えてしまい肥満を招いてしまう可能性があります。取り過ぎは腎臓や肝臓に負担がかかってしまうため、過剰摂取にならないように気をつけましょう。
また、タンパク質だけを取ればよいというものではありません。運動にはエネルギーが必要となるため、エネルギー源となる炭水化物や脂質も合わせて摂取しましょう。
骨を強くするためにはカルシウムだけでなく、ビタミンDやビタミンKの摂取も大切です。ビタミンDは鮭や真いわし、きくらげなどに含まれています。ビタミンKは納豆やブロッコリー、ほうれん草などに豊富です。
さまざまな栄養素をバランス良く摂取することが、健康を維持する上で大切でしょう。
介護の仕事はロコモ予防になる
ロコモは要介護の原因となりやすいですが、運動習慣や食生活の見直しなど早めの予防で、ロコモの状態を防げるかもしれません。
要介護状態を防ぐためにも、今からできることを無理のない範囲で少しずつ始めてみましょう。
また、介護の仕事は体を動かす業務が多いため、ロコモの原因である筋力やバランス能力、柔軟性などが自然と鍛えられます。
ご利用者様の役に立ちながら、自分自身の健康も維持できる魅力的な仕事です。
ロコモ予防を意識しながら、長く健康に介護の仕事を続けられるように、日々の業務に取り組んでいきましょう。
この記事を書いたのは・・・
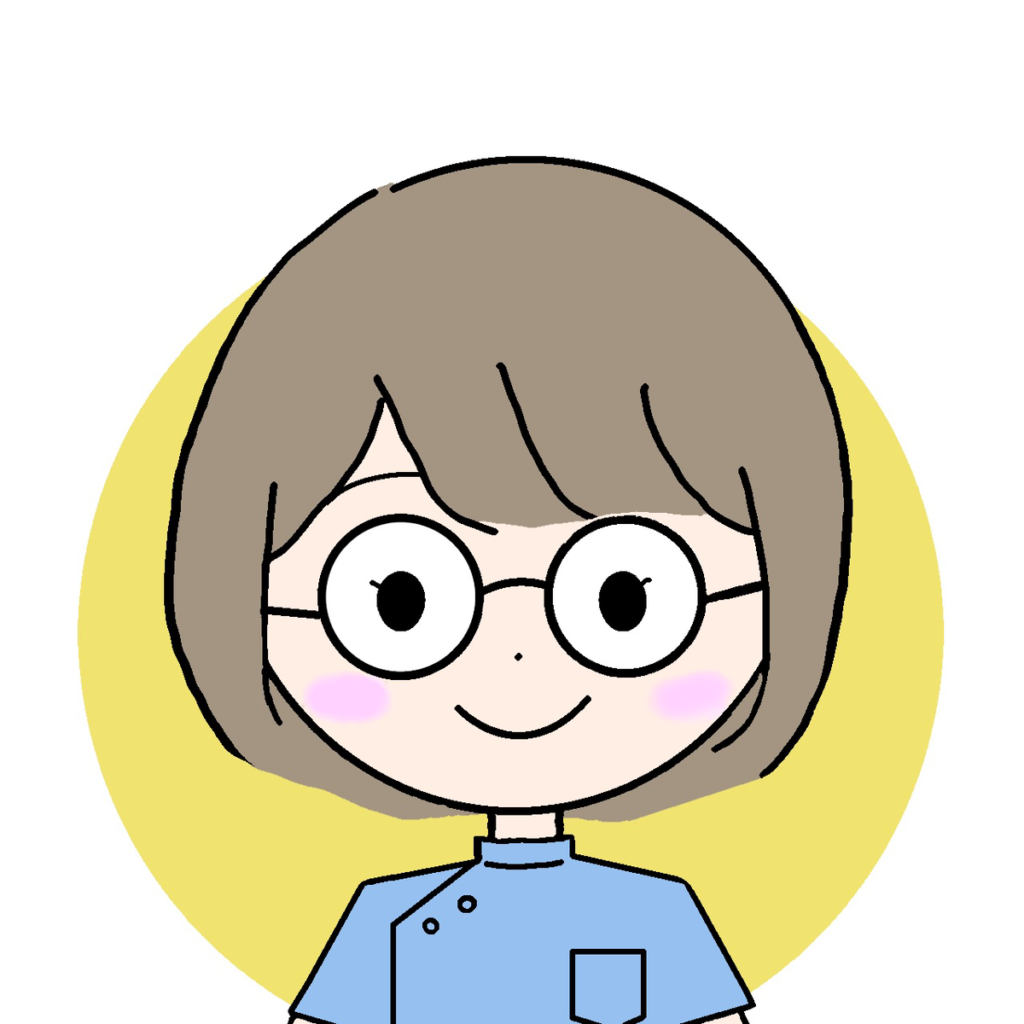
椎野みいの/Webライター
保有資格:作業療法士/福祉住環境コーディネーター/福祉用具プランナー/認定心理師
病院、介護老人保健施設、リハビリ専門学校を経て、現在は特別養護老人ホームにて機能訓練指導官として勤務中。